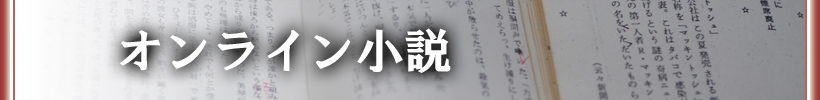オンライン小説
●第2章
その日、わたしはまだ地球にいた。主人が仕事の都合で、国連本部に顔を出すことになっていたのだ。今や国際連合は名ばかりの存在で、そこはビジターズの統率機関となってしまっているのだが、不服を言う者は現在この地球にはいない。いや、ありえないと言った方が正確だろう。そういった人間は、存在を許されていないのだから。
ニューヨーク、マンハッタン。かつては人種の【るつぼ/傍点】と呼ばれ、コーヒーに落としたミルクのように、白と黒が回っていた街。しかし黒人はハーレムに追いやられ、その日の糧にもありつくことができなかったという。黒人女性がミスワールドになるとニュースになり、ビジターズの最初の拠点となった南アフリカが、悪名高きアパルトヘイト政策をとっていた時代、クー・クラックス・クランが派手な例祭を開き、肌の色で、人間が差別されていた世紀の話だ。今は違う。今は肌の色で、人間が排除される時代になった。それも、白人が。
わたしは今まで、【白人/コーカソイド】、【黒人/ニグロイド】という言葉をあまりに安易に使い過ぎたようだ。実際には白人に限りなく近い黒人、ちょっと目には白人と変わらない黒人もいるのだから。【混血/カラード】の問題を考えれば、肌の色だけで“【人種/ヒューマン・レース】”を決めることは難しい。
ビジターズが訪れる前の地球――我々は便宜的に、“旧時代”と呼んでいる――の社会科学者は、人種をこう定義していた。“自分たちで、あるいはほかの集団から、内在的・固定的特性のゆえに他に違うと規定された人間集団”と。つまり社会が人種を決定するとしたのだ。
しかし現在において、ビジターズの引いた一線は明確だ。すべては色だけで区別される。【色素細胞係数/ピグメント・セル・インデックス】――PCIと略される。皮膚、毛髪などの色の濃さの度合いを計量化したもの、それと【虹彩色判別法/アイリス・カラー・チェック】――ICC、その名の通り、虹彩の色を調べ、“青い目”をチェックする――これらのテストにより、世界中の人間は二つにわけられた。つまり、“【有色人種/カラード】と“【非有色人種/ノンカラー】”である。
ビジターズは肌の色を問題にしたが、“血”に関しては考慮しなかった。つまり、いくらニグロイドの血が混ざっていると本人が主張したとしても、PCI、ICC共に真陰性ならばその者は【非有色人種/ノンカラー】なのである。もっとも実際にはきわどい線上にいる者たちに、【指紋形状/フィンガー・プリント】テスト、目鼻口のつり合いを検査する三点配置形状テストなどの“血”を考慮するチェックを行いはしていた。
その結果として、旧時代の大部分のニグロイドとモンゴロイドが【有色人種/カラード】として認められ、大部分のコーカソイドが【非有色人種/ノンカラー】とされた。そしてビジターズと供に生きることが許されたのは【有色人種/カラード】のみであった。
現在では、白人と言えばそれは【非有色人種/ノンカラー】を指している。
その昔、世界有数の危険な街と呼ばれたニューヨークも、ビジターズの治安管理と完全福祉政策のおかげで、夜間の女性の一人歩きさえできるようになっていた。
とは言えわたし自身は昼間だというのに公的な立場からと理由づけられ、護衛二人につきそわれながら、その街を歩いていた。表向きはメトロポリタン美術館へ行くために。セントラルパークは96番通りを境に、高い壁で分断されている。そちらは第三非有色人種自治区と公式文書には書かれるが、一般には白人街――スラム、最近では【牢獄/プリズン】などとも呼ばれている。
世界各所に点在し、壁で囲まれている非有色人種自治区は、自治とは名ばかりで、つまりは俗称通り監獄なのだ。そこはあらゆる情報を断たれ、医療設備はおろか、電気やガスさえ通じていない。食糧や水に関しても、自給自足が原則である。彼らは旧時代の飢える人々と同じ生活を強いられているのだ。壁のすぐ外側では、少年たちがかじりかけのホットドッグを道ばたに捨てていくというのに。
もちろん、壁の外への逃亡や、暴動を企てる者もいるのだが、彼らはそれを実行に移す前に処分されている。それというのも、そういった行動を密告したものは、“【名誉有色人種/オノラリー・カラード】”の地位を与えられ、家族共々壁の外に合法的に出られる、となっているからなのだ。もっとも、実際に出られた人間など一人もいないということを、彼らはしらない。
非有色人種自治区からの逃亡や、暴動が起こらないことを、ビジターズはこう宣伝している。“彼らは非有色人種だけの社会を形成し、快適に暮らしている。我々が訪れる以前に望んでいたことを、我々が成し遂げてやったのだ”と。
ビジターズにとってみれば、白人を生かしておいてやるだけでも、まったくの慈善事業にほかならないのだ。彼らは、非有色人種の烙印を押された者全員を殺戮することも可能だったのだから。わたしはもっと非道い案があったのも知っている。遺伝子構造まで同じなのだから人体実験に使う、臓器移植の提供者として生かしておく――この案は、“白い臓器”など移植したら、かえって健康にさしつかえると、一部の猛反対があったようだ――。原子炉、高所作業など危険作業に使う。死んだら死んだで構わない。非有色人種は【人間ではない/傍点】のだから、家畜として飼い、食料とする。エトセトラ、エトセトラ……。
この内のいくつかは、公表されてはいないが、実際に行われている。半年前、ヨミウリ新聞社の記者二人と、フリージャーナリスト一名が乗っていた飛行機が墜落、炎上した。生存者なし。彼らがつかんでいたニュースビート、それはビジターズがアフリカに支給している鶏肉の中に、金髪や、衣服の切れはしが入っているというものであった……。
現在、多分普通に暮らしている人間――むろん、有色人種――にとっては、白人はもはや、古い映画でしかお目にかかれないものとなった。
と、言っても、自治区以外で身を隠しながらも暮らしている白人もいることはいる。いわゆる“【名誉有色人種/オノラリー・カラード】”、“【既婚者/マリッド】”、そして“【協力者/コーペレータ】”である。
“名誉有色人種”は芸術、社会科学などに能力を持つと認められた白人であり、しかもビジターズが訪れる以前にも親有色人種であった者でなければならない。理系の科学者たちはこの範疇には入らなかった。ビジターズの科学に比べれば、当時の地球科学など、とるにたらないものであったからである。つまり“名誉有色人種”とは、まだビジターズが利用できると踏んだ人間たちなのだ。
“既婚者”とは、言葉通り有色人種と結婚している白人を指している。滑りこみ結婚が殺到したため、数から言えば三者の中で一番多い。ただ、配偶者が非有色人種となると、社会的にかなりのハンデを負わされることがわかっていたので、そうそう白人の思惑通りにはいかなかったようだ。旧時代その美貌だけで売っていたため、名誉有色人種の選に漏れたある人気シンガーは、自治区に送られる二週間前からあせり、もう誰でもいいと道行く有色人種女性数百人を口説いたが、結局誰にも相手にされず、しまいにはゲイ同士の結婚が許されている州にまで出向き、男にまでプロポーズしまくったという笑い話が残っている。
また、“既婚者”として自治区入りを免除されても、彼らの扱いは配偶者のペット並みとなっている。出歩く地域は厳しく限定され、配偶者の一方的な意志で離婚が成立する。この場合、彼らは自治区へ送られてしまうのだ。滑り込み結婚を果たした白人の八十パーセントは、結局現在は自治区で暮らしているという。
“名誉有色人種”にしろ、“既婚者”にしろ、彼らは禁治産者であり、また“優生保護”上から全員が去勢、不妊手術を受けさせられている。生まれてしまっていた子供に関しては有色人種と認められればそのまま、もう非有色人種となれば、やはり“既婚者”と同じ扱いとされた。
禁治産待遇というのは変わらないが、前二者と違い、去勢、不妊手術が免除されている者たちもいる。それが“協力者”である。彼らはビジターズに迎合し、ビジターズの統率に手を貸した政治家たちなのだ。むろん、彼らのような“人種”が、何の見返りもなしにそのようなことを行う訳がない。ビジターズは彼らにこう言って協力させた。“あなたたちには【新しい世界/傍点】に住む権利を与える。よって【それなり/傍点】の努力をしてほしい”と。
彼らは、【新しい地球/傍点】で、【それなり/傍点】の地位と権力が手に入ると信じ、自らの手で自らの同胞たちを裏切ったのである。
その挙句に与えられたのが、つまるところ旧時代の【黒人/傍点】以下の生活であったのだ。また、彼らには前二者と違って地球に永住権がない。彼らは仮住まいの新時代で、旅立ちの日を待っているのだ。旅立ち――アフリカーナの“【大移動/グレート・トレック】”にちなんで、GT【計画/プロジェクト】と名づけられた“移民”計画。彼らは現在木星のラグランジェ点で造られている世代恒星船に乗せられ、船内で社会を造り、子を生しながら、新しく人の住める惑星を探さなくてはならないのである。かつてビジターズがそうやって地球を見つけだしたように。
つまりこれは、“移民”の名のもとに行われる追放なのだ。ビジターズの言っていた“【約束の地/プロミスト・ランド】”とは、決して地球のことではなく、それなりの努力というのも、勝手に探しだせという程度の意味だったのである。逆らえば当然、自治区送りとなる。
“協力者”とは要するに、ビジターズにとってはもう用済みの人間たちのことなのだ。
これらの処置により、あと数世代後には、自治区以外で登録されている白人は消えてなくなる。
登録されている、という言葉を使ったのは、彼らに対し、“登録されていない”白人も、僅かながら暗躍しているからなのだ。有名なのがアメリカのKKKと南アフリカの【兄弟同/ブルーダ・ボンド】の残党らである。あの悪名をはせたKKKや兄弟同盟が、今や抑圧されている白人たちを解放するために闘っているのだ。昔の黒人解放運動のように。
もっとも、今のわたしにとっては、それらより規模の小さい、弱小解放組織の方が問題であった。
わたしはできるだけゆっくりと歩いていた。約束の時間よりまだ早い。ついてきている二人には、疑われないように足が痛いと言っておいた。
「だから車でいらっしゃればよろしかったのに」
「車は苦手なの。酔ってしまうわ」
一人が同情してきた。「では宇宙では大変でしょう」
「オービターではね。でもわたしはステーションにしかいないから」
「僕はまだ宇宙に行ったことがないんですよ。今度の週末にどうかなと思っているんです。パンナムの予約はまだ取れるかな」
「さあ、どうかしら。主人に頼んであげてもいいわよ。でも、地球の眺めは最高だけど、他はどうかしら。ハネムーンには向かないと思うわ」
彼は含み笑いで応えた。
「何かおかしいことを言ったかしら? わたし」
「いえ、そうじゃないんですよ。ただね、こんな会話を七年前にしている者がいたら、僕は石を投げつけてやるんじゃないか、なんて思って」
「それはそうね」
ビジターズが地球を訪れてから七年、たったの七年で彼らは地球の歴史を塗り変えてしまったのだ。
「……あなた、疑問に思ったことはない?」
「何を?」
「あ、いえ――」訊かずとも、答は知れているというのに……。わたしはごまかした。「月や火星まで観光地にしてしまうってことに。日本の言い伝えでは、月には兎が住んでるって、わたし、気にいってたんだけど」
「いいんじゃないんですか。別に。奥様はロマンティストですねえ」
「ちょっと待って――」
妙なことに感心してみせた彼をさえぎり、わたしは立ち止まった。歩道の隅で警官二人が尋問している。相手は黒いベールを頭からすっぽりかぶり、声からすると、どうやら女性らしい。
「すみません。通して下さい。急いでるんです」
「ですから、お顔を拝見――」
「勘弁して下さい。事故でひどい傷が……」
そっと窺うおびえた青い瞳を、警官は見逃がさなかった。瞬間、有無を言わさずベールをはぎ取る。そこにいたのは金髪の、身なりはきちんとしているが、面やつれは隠せない白人女性だった。
警官の口調が、がらりと変わった。
「どこに傷があるんだよ、ああん?」
「許して下さい!」彼女は言った一人にしがみつき、涙声をあげた。「薬と、食べ物を買おうと思ったんです」
「パスを!」手を出したもう一人に、彼女はおそるおそる身分証明カードを渡す。自治区外の有色人種は、外出するときは必ずパスを身につけていなければならない。
確認した警官は、鼻を鳴らして嗤った。
「【既婚者/チェンジ・ラック】か?」
「そうです」
「お前も知っているだろうが、このエリアは【有色人種専用/カラードオンリー】だ。パスがあろうがなかろうが、【非有色人種/ノンカラー】の立ち入りは禁止されている。このパスは没収だな」
「そんな……」彼女の目に恐怖の色が浮かぶ。パスを没収されるということは、自治区に送られることを意味している。「許して下さい! 主人が病気で倒れて――わたしのエリアでは、誰もわたしに物を売ってくれないんです。だから仕方なく――」
警官は耳をほじり、そっぽを向いた。「聞こえんな」
「待ちなさい」あまり首を突っこむような真似をしたくはなかったが、警官のあまりに横柄な態度が癪にさわった。わたしはつっぷして泣く彼女を助け起こした。「あなた――、あなた間違えてここに入ってきてしまったのよね、そうよね」
「何だ、お前――」わたしに手をかけようとした警官の腕を、護衛は素速く止め、彼に耳打ちした。警官の目が疑いに揺れる。「まさか」
返事をせず、護衛は小さくうなずいた。警官は慌てて立ち上がり、気の毒なほどに狼狽し、訝かって訊ねてきた仲間に何事かささやくと、二人で数歩さがって、ぱっと敬礼してきた。
わたしは手帳を破り、彼女に特別通行許可を与える旨を記してサインを加え、握らせた。「これを持っていれば、今日一日はこのエリアでも買物ができるわ。不売をされたら、これを見せなさい。お金は持っているの?」
「はい、あの――」彼女は、ためらうことなく、その場に土下座をした。「ありがとうございます」
その時になって、わたしは自分のしたことに嫌気がさした。当然のように地べたにひれ伏すことができるこの夫人も、また彼女にそうさせてしまった自分にも。
「早く行きなさい」自分でも尖っているとわかる声でそう言い、わたしは背を向けた。後方で、さっきの警官二人がひそひそと話す声が耳に入ってきた。
「何で【人種関係局/RRB】の局長夫人が、こんなとこ歩いてんだよ」
「知るもんか。そんなこと。チェ、間が悪かったよなあ」
「奥様――」いくらわたしが早足で歩いても、大柄の護衛たちには苦にもならないらしい。すぐに追いつかれてしまう。
わたしは時計を盗み見た。時間だ。【彼ら/傍点】はもう、わたしをマークしてくれているのだろうか。あたりをそっと窺う。今の騷ぎはまずかったかもしれない。彼らが警戒し、【接触/コンタクト】をやめるかもしれなかったのに。
「奥様」何も知らない護衛が忠告してくる。「お言葉かもしれませんが、さきほどのようなことは、あまりなさらないほうがよろしいかと」
「そうね、本当にそうだわ。心配させて、ごめんなさい」
舌打ちして、歩道を蹴る。わたしたちの横を、フォンをして陽気に躍る逞しい男がすり抜けていった。と、脇の護衛が目を見開き、その男にゆっくりと振り向いた。
「おまえ――」
男はニヤと笑みかけた。「こんちは」
親しげに肩に手をかける。とたん、護衛は膝を折った。その背に、一本のナイフが突き刺さっていた。
(第3章へ続く)