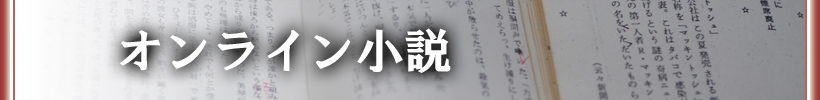オンライン小説
PAPA STILL SMOKEN'
「主人は地位も立場もある人間ですので、このことは是非とも内密に願いたいのですが――」
いくぶん青ざめた表情のその夫人は、わけ知り顔で座る白衣の精神科の医師に言った。「わたくしも、もうほとほとに困り果てておりまして、こうして先生のもとに連れてきたわけでございます――」
「もちろん、患者さんの秘密は厳重にお守りしますよ。医者の常識としてね」
医師は人あたりのよさそうな笑顔で応えた。夫人はその言葉にほっとしたようだ。
「それをお聞きしてして安心しました。主人ももともとは、まじめで優しい人なんです。それが――今年の春にアメリカ支局帰りの方が、こちらの新しい局長として着任されましてね、それで、ストレスがたまってしまったらしくて――」
「なるほど。ご主人は部長さんでいらっしゃるから、その局長と部下との板ばさみになってしまったわけですな――ありがちですが、気の毒な話ですねェ」
「いえ、仕事のほうでは、みなさんとうまくやっているんですのよ」夫人は顔を上げると、心外そうに首を傾げそして眉を寄せた。「ただ――」
「ただ?」
「その――先生はタバコをお吸いになりますか?」
しばらく言いよどんだあげく、こう訊ねてきた夫人に、医師は目を丸くした。
「タバコ、ですか!? ぼくは吸いませんが」
「そうですか――。それは、おやめになったからですか?」
「いえ、産まれたときから、一本も吸ったことがありませんよ」
「実は主人は、ヘビースモーカーだったんですの」
「だった、というのは過去形ですね。そうか、やっとわかりましたよ。ご主人は、そのアメリカ帰りの上司に禁煙を申し渡されたんでしょう?」
「そうなんです。それで主人はあんなふうになってしまったんですわ」
夫人は身震いすると、付け足した。
「あんな妄想にとりつかれてしまって!」
* *
となりの診察室に医師がうつると、そこには一人、落ち着いた風貌の中年男性が座っていた。
鬢をきれいになでつけ、たくわえた口髭も刈りそろえられている。服装も整っているし、多少腹は出ているが、それがかえって恰幅のよさを人に印象させるようだ。ブローフレームのメガネが、知的な雰囲気をかもしだしている。
ようすも、どこといっておかしいところはない。ゆったりと椅子に腰かけ、手もちぶさたに雑誌のページをめくっている。視線もいたずらに泳ぐことはない。
ここにいることが不似合いなぐらい、ごく普通の紳士といった印象である。
医師が入ってきたことに気づくと、彼は雑誌をおき、座りなおすと挨拶をしてきた。
「やあ、どうも、こんにちは――」
「こんにちは」
相手はどことなく体を強張らせてはいるが、それは馴れない場所で緊張しているからであろう。医師はまわりこむと、自分の椅子に腰をおろして、まず、微笑みかけた。
「どうも天気がすぐれませんね。こういう毎日だと気分が滅入りますよ」
「そうですね、はやく梅雨明けしてほしいものですな――妻のようすはどうでした?」
「ええ――。少しお疲れのようですね。でも、たいしたことはありません。しばらくお休みになれば、すぐに回復できるでしょう」
「それはよかった――」紳士は安堵のためいきをつくと、椅子に深く腰を下ろしかえ、医師に小刻みにうなずいてみせた。「妻は最近、たしかに疲れぎみのようでして――。あげくの果てには、わたしが妙な妄想にとりつかれているなどと言いだしましてね。わたしも困り果てて、こうして連れてきたわけです」
夫妻がそろって同じことを言っている。医師は真顔で、なるほど、とうなずき返した。こうでも夫人が言わないと、この紳士はここになどこなかったのであろう。
となれば、診察せねばならないのは、この紳士のほうだ。医師は椅子をくるりと回すと、腰を折って膝の上で手を組みあわせ、身を乗りださせた。
「その、“妄想”のことなんですがね。いったいあなたは、奥さんになにを言ったんですか? なんでも、タバコがどうとか」
紳士はぎょっとしたように身をすくめ、そして次の瞬間には敵意を含んだ目つきになり、探るように訊ねかえした。
「妻はなにか話したんですか? そのことで――」
「あなたの新しい上司が激しい嫌煙派で、オフィスに全面禁煙を申し渡したせいで、ヘビースモーカーのあなたが泣く泣く禁煙を余儀なくされた、とは聞きましたがね」
「それだけ?」
「それだけですよ。あとはあなたに聞いてくれ、と」
「そうですか。では、その話は聞かなかったことにしてください。いやァ、わたしが悪かったんですよ。不用意にあのことを妻に話したりしたものだから――」
「あのこと?」医師は首を傾げ、そしてひときわ紳士に身を乗りだした。「是非ともお聞かせ願えませんかね? 奥さんの治療のためには、そういったことも知っておきたいんですよ」
「しかし――」紳士は目の色を変えた。この、根ほり葉ほりほじくりかえそうとする医師に、なにかしら疑わしさを抱いたようなそれである。「あのことはですね、先生。その――、そう簡単には話せないんですよ。どこにあの連中の目が光っているかわからないし」
「あの連中? あなたの会社の方ですか?」
「いえいえいえ。そうじゃない。あの連中は今やこの世界中いたるところにはびこってるんです。もしわたしがあの連中に気づいていることがわかったら、殺されるか、そうでなければ、縄で縛られて好き放題にムチでいたぶられたり、ロウソクをたらされたり、女王さまに跪かされて、洗脳されちまうに決まってる……うふふ。それもいいな。うふふふ」
ブツブツとなにやら口を半開きにして、自分を納得させるようにつぶやき続ける紳士である。医師は口をはさんだ。
「あの連中とは?」
瞬間、しまった、という口もとになった紳士は、なにを思ったか、ばっと医師からのけぞると立ち上がり、まるで手品師のように素早く、両手になにかをつかみだしていた。一本のタバコとライターである。
そして、医師がそれに気づく間もあらば、あっという間にそれを吸いつけ、大きく胸をふくらますと、一息、彼は面くらっている医師に向けて煙をふきかけた。
頭のまわりに、ふわりとたちこめた紫煙を、医師は手ではらうこともせず、患者のおかしな行動には馴れている、とでもいいたげに、ようすをじっと観察している紳士に向けて、一言。
「これが、なにか?」
「いや、いやいやいやいや、失礼しました」あわてて自分で煙をはらい、紳士はペコペコ頭をさげると、照れかくしに頭をかきながら、再び椅子に腰をおろした。「驚かれましたか? しかし、これがあの連中と人間とを見分ける、唯一の方法なんですよ。ところで先生はタバコをお吸いになりますか?」
「いや」否定したあと、医師は後からとりなすように、こう付け加えた。「それでも、今の嫌煙権運動は、多少いきすぎのような気がしますねえ。個人の喫煙は憲法で保証された権利なんですから、他人に迷惑をかけるようなことは論外としても、その習慣で、その人のパーソナリティまで判断してしまう今の風潮は、ちょっとおかしいと思いますね」
「なるほど――どうやら先生は信用できるかたのようだ」紳士は、ふうと大きくひとつ息をつくと、あたりをうかがうように目を左右に配り、そして声をひそめた。「では先生は、こんなバカげた運動が、なぜこんなに隆盛を誇るようになったか、おわかりですか?」
「それは――やはりタバコが、健康に害があるものだからじゃないですか?」
「それが違うんですよ。先生。タバコというのはね、人間にとってはそれほど害のないものらしいんですよ。むしろストレスをとり肥満を防止し、緊張力をたかめ想像力を増大させる薬なんです。それが証拠に、あの死ぬまで生きてた泉重千代さんもタバコを喫んでたじゃないですか」
自分の悪癖を正当化するために、悪いことには目をつぶり、良いことだけをことさらに並べたてる。合理化というやつだ。医師もそのようなことは百も承知だが、うんうんとあいづちを打ってみせ、紳士はいっそう能弁になった。
「なのに、なぜ、世界中でこんなにもタバコが悪者になってしまったと思います。変でしょう? なにか、何者かの大きな“意志”が働いていると考えなければ合点がいかないでしょう?」
「は、はあ――」
「そうなんですよ。実はいるんです。それがあの連中なんです。あの連中は、そうやって徐々に地球を占領しようとしてるんです」
相手のあまりの気迫に怖じ気づき、身をのけぞらせた医師に、ギラついた目で紳士はせまり、噛みつきそうなほどすり寄って、言った。
「あの、【嫌煙異星人/ノンスモーカー・エイリアン】どもは!」
そして彼は、ベロリと下で唇をねぶらせて、話し始めた
* *
「隠れてトイレでタバコを吸うなんて、キミ、高校生みたいなマネをして、恥ずかしいとは思わないのかね?」
キザな縦縞のスーツを、雑誌のモデルのようにスマーで上背のある体に羽織り、見事な銀髪を乗せた、そのアメリカ帰りの新局長は、デスクをはさんで恐縮しきりの彼に、怒鳴ることなく、かといって妥協するスキも見せずに言っていた。
「それも率先して部下にそれをそそのかすとは――。今月から、このフロアはすべて禁煙になったことを忘れていたわけでもなかろう? タバコの悪臭はね、キミ。壁や床にも染みついて、そう簡単にはとれんのだよ。悪い臭いはモトからたたねばダメ、という諺もあるだろう?」
さすがアメリカ帰りだけあって、日本語のほうは多少危なくなっているらしい。
「わたしはキミの将来をかっているからこそ、キミにもタバコなんぞという毒ガス吸煙の悪癖をやめてもらいたいと思っているんだ。そんなことでは一流のエグゼクティブにはなれんよ、キミ。一流のエグゼクティブは健康には人一倍気を使い、睡眠や食事もきとんととる。もちろんタバコなど喫まんし、腹も出さん。そういうことがやりたいのなら、キミ。今からでも遅くないから、小説家か編集者になりなさい」
「しかし、ですね、局長――」ついにたまらず、反論してしまう彼であった。「いきなりこのフロア全面を禁煙にするというのは無茶ですよ。部下のなかにも不平をもらしているものがおりますし、せめてどこかに喫煙コーナーを設け、分煙の方向から始めるということで――」
「ああ、それは馬の耳に念仏だよ。キミ」顔を横に向け、手を振ってみせる。聞く耳を持たない、と言いたかったのであろう。「今度の件では、早々に責任を取らせるつもりだ。覚悟しておきなさい」
「責任!? たかがタバコのことじゃないですか! どうしてそんなに、タバコを毛嫌いするんです? 局長の目の前で煙をまきちらしたのならまだしも――」
食い下がった彼に、相手はぎろりと目を向け、そして書類をバサバサとまとめると、立ち上がった。そして構わず扉のほうへ行ってしまう。
「理由などないよ。キミ。わたしはね、この地球から、タバコなどという毒ガスはなくしてしまいたいと思っているだけだ。我々地球に住む者の明日のためにね」
言い捨てて、あとはまるっきり無視して出ていってしまった相手に、彼は慌ててきびすを返したが、隣の秘書室には、もうその姿は消えていた。
「あら、いけない」帰り支度をしていた秘書が、デスクの上の書類封筒を取り上げた。「局長にお渡しするはずでしたのに――。すごい権幕でお帰りになったものだから、ついうっかり忘れてしまったわ」
はっと気をとりなおし、彼は秘書に向き訊ねた。「大切な書類かい?」
「ええ。明日はお休みだから、今日中にお渡しして、休日明け一番にそちらに連絡をいれないと――」
「わかった、わたしが届けよう。まだ間に合うだろう」
「ええ!? そんな、あたしが――」
「いいんだ。どうせ途中までは道が一緒だし、話したいことが残ってるから――」
言い終わらないうちに、彼はその書類をひっつかみ、エレベーターホールに向かって馳せていた。
* *
あいにく追い掛けた相手は、早々にタクシーに乗り込み、もう遅い夜の街に消えかかっているところだった。彼はすぐに後続のそれを無理矢理つかまえ、その後を追った。
終電が終わった後の街は、車と酔客、ネオンサインの洪水である。
そこを抜け、数十分もとばしただろうか、相手の乗ったタクシーは、ある街角でついに停まった。
「おかしいな」金を払い、外にでてあたりを見回した彼は、ふとつぶやいた。「局長の家は、こんなところじゃないはずだが――」
ふと見ると、その相手は道路脇の茂みに身を翻し、影を隠そうとしているところである。おかしいと思う余裕もなく、彼は見逃してはならじと、さっとその後を追った。
なにか声が聞こえるようだ。
『合い言葉は?』
『ドント・スピーク・×××』
どこかで聞いたような台詞である。茂みから中に顔を出した彼は、そこに小さなコンクリ作りの部屋があり、つけられた扉がしまるのを見た。さっと消えていく縦縞の背広は、局長のものに違いない。
彼はおそるおそる近くに寄ってみた。と、脇につけられたインターホンから、急に声が飛んだ。
『合い言葉は?』
「かっ、かっ、川! じゃない。ドント・スピーク・×××!」
日本人の悲しい習性でヘマをしかけたが、危うく持ち直した。と、扉の鍵がカタリと空いた。彼は好奇心というよりも、なにかに追い立てられるように、その扉をあけ、中に飛び込んでいた。
そこにあったのは階段であった。深く地下続いている。響いてくる足音は、先に降りた局長のものであろう。彼は忍び足になり、そっとその暗い階段を降りていった。
下にもひとつ、扉があった。重いそれを開く。と、さっとまばゆい光と、声の波がこぼれてきた。身をすりこませ、中にはいりこみ、彼はしばし茫然とした。そこは地下とは思えぬ広さの、まるでコロッセウムのような空間だったからだ。
中央の円形広場には、檻がおいてあり、その横にはムチを持ち、肌もあらわな出で立ちの女性が一人、それをふるってなにかをわめいていた。檻の中では、なにかがうごめいている。人間だ。
彼を驚かせたことはもうひとつある。林立して口々に叫んでいる人々の中に、テレビや雑誌でみかける、文化人や各界の著名人たちが、多々いたのだ。これがまさか、秘密のナントカいうクラブなのか、と、根が真面目な彼はよろよろとよろめいた。
しかし、彼の予想は裏切られた。壇上の女はこう叫んでいたのだ。
「我々がこの地球に降り立って、もう十年にもなる。その間、我々は人間と同化し、気づかれることなくここまで移住を完遂した!」
一斉に拍手と声が沸き上がった。その中にあの局長の姿もあった。
と、突然檻の中の男が叫んだ。
「きみたちはいったいなんなんだ。わたしを誘拐して、こんなところに連れてきて、なんのつもりだっ!」
「わたしたちは、あなたたち地球人の友人ですわ。遠い星を追われて、この地球にたどりついた――。あなたたちにすれば、そう。“異星人”というわけね」
女は眉を上げて、ニヤリと笑い、言った。「長い年月でしたわ。この地球という惑星を見つけだすまで。しかも、この星の住人である“人間”が、わたしたちと姿かたち、まるっきり同じだと知ったときのわたしたちの喜びようが、あなたにわかるかしら?」
「い、い、い、異星人!?」
「そう。そしてわたしたちは、あなたたちに気づかれないよう、徐々に移住を始めたわ。もう十年も前の話。けれど、わたしたちはひとつ見逃していた。あなたたち人間が、タバコという毒ガスを好んで吸える動物だということをね!」
女は忌ま忌ましげに、びしりとムチをふるった。
「いくら姿かたちが同じだとはいえ、わたしたちの遺伝子構造は、あなたたちのそれとは細部ではことなっていたわ。それが顕著に顕れたのが、タバコの煙だった。わたしたちがタバコの煙を吸うと、あなたたち地球人よりも格段にガンの発生率が高かったのよ。ひと箱も吸えば、必ず死んでしまうほどにね」
「な、な……」
唇を震わせる檻の中の男に、女は冷たく微笑んだ。
「もうあなたが、ここに連れてこられたわけがおわかりでしょう? あなたは厚生省の官僚でありながら、タバコはほどほどに吸えば健康にもいいなどとおっしゃったわね。わたしたちは、そんな野蛮な考えを、あなたに改めてもらわなくてはなりませんの――」
続く悲鳴と、万雷の拍手、割れんばかりの歓声に、陰で一部始終を見ていた彼は耐えられなかった。全身に震えがきて止まらなかった。扉を開け、階段をかけのぼる。外に転げ出て、走り出したところでつまづき転んだ。「おう、あんちゃん、飲むかい?」
ベンチに寝そべっていた男がウイスキーのポケット瓶を差し出した。彼はそれをむしりとると、遮二無二駆け出した。
どこをどう帰ったか、彼は次の日の夕方、自宅のベッドで目を醒ました。ひどいうなされようでしたわ、と告げる妻の後ろで、ゆうべあの檻で見た、厚生省の役人が、昨日の発言は全面撤回します、と平々に陳謝しているテレビニュースを見て、彼の震えが頂点に達したことは言うまでもない。
* *
「それにしても、あなたは幸運です。こうして早くお話しできてよかった」紳士の話をついに最後まで聞き終えたあと、難しい顔をしていた医師は、組んでいた腕をほどいて、こう言った。「もう少し遅れていたら、手遅れになるところでしたよ」
紳士はさっと身構え、かたい口調でまくしたてた。
「まさか、先生も妻と同じように、今わたしの話したことが、妄想かなにかだと言うんじゃないでしょうねっ。これはほんとうにあったことなんだ、現実なんだ――」
「わかっています。わかってますよ」医師は両手で彼を押し戻した。「その逆です。あなたが体験したこと、知ったことは、まごうことなき現実そのものです。なぜならね――」
さっと声を落とし、医師は相手の目をのぞきこんで、続けた。「ここ数年というもの、あなたが今言ったようなことを不注意に口走って、わたしのところに連れてこられるかたが、もう六人もいらっしゃるんですよ。ぼくも最初は一笑にふしていましたが、それでも、お互い面識もなにもない何人もの人々が、みなさん、そのタバコが嫌いな異星人が、地球を乗っ取ろうとしているという話を異句同音におっしゃる。これが――偶然だと思えますかね?」
紳士は目を見開き、子供のように大きく、ぶるんぶるんと首を横にふった。
「すると、わたしのほかにも、このことを知っている、つまり――同志がいるというのですね!」
「そうですそうですそうです。そして、このぼくも今はその一人なんです。ぼくはタバコは吸いませんが、ことはそんな瑣末なことじゃない。なにしろ人類の存亡がかかっているんですからね」
「おゝ……」感きわまったのか、紳士は五体を震わせると、はっしと医師の両手を、さっと自分のそれで包みこんだ。「やはり先生にお話ししてよかった。一目見たときに、なんとなく、そんなインスピレーションが働いたんですよ。このかたはわたしの味方だって」
「同じ正真正銘の人間同士、やはりどこか通じあうものがあるのかもしれませんね」
今にも涙をこぼさんばかりに、感激をあらわにしていた紳士は、やがてきりりと唇を引き締め、そして強く拳をにぎりしめた。
「闘いましょう、先生。今すぐその同志のみなさんを集めて、あの連中の正体を暴くんです。でないと地球はあの連中に乗っ取られてしまう!」
「いやいや、ダメですよ。あせってはいけません。今はまだ我々の力が小さすぎる」闘志をみなぎらせ武者ぶるいをする紳士をなだめるように、医師は曇りのない真剣な瞳でささやきかけた。「だからこそ、あなたをあの連中よりはやく見つけられてよかったと言ったのです。もう少し遅れていたら、あなたは連中の手に落ちて洗脳されてしまっていたかもしれない。連中はどこに目を光らせているかわかりませんからね――」
「すると、わたしはどうしたらいいんですか、先生。連中がこの地球を征服していくのを、指をくわえて見ていろというのですか?」
「とりあえず、我々の力が大きく、深くなるまで、なりをひそめておかないと。かなりの数の連中が、もうこの地球に降り立ち、人間のふりをして生きているんですからね。中には権力者になった者もいるし、洗脳されて連中の手下になった政治家もいる。目立った行動は危険です」紳士は、尊敬する上官の言葉を聞く一兵卒のように、医師の一言一句に、懸命に耳を傾けていた。「ぼくは、あなた以外の、連中の秘密を知っているみなさんにも、今は連中のことを気づかないふりをして、普通に生活してくださいと伝えてあります。あなたも、まずはタバコをきっぱりとやめてください」
「タバコをやめろですって? なぜ?」紳士は手に持ったタバコの箱を医師に押し出して、声を上げた。「これは連中に対する唯一の武器なんですよ。それをやめろだなんて。みすみす敵にやられろと言うんですか?」
「そうではありません。裏をかくんです」確信と強い意志に裏打ちされた医師の言葉に、憤っていた紳士も口を閉じた。「ここはひとまず、連中に洗脳されたふりをしておくんですよ。でないと連中は、これからもあの手この手を使ってあなたを狙ってくるでしょう。命さえ容赦なく奪うかもしれない。最近、サラリーマンの過労死というものがクローズアップされているのを、あなたも知らないわけじゃないでしょう?」
「そうか、あれは、あの連中の仕業だったのか――」紳士は血もにじまんばかりに唇を噛むと、やがて決意をこめて、手にしたタバコの箱を握り潰した。「わかりました。タバコはきっぱりとやめておきましょう。今は個人の自由を云々している場合じゃない。人類の存亡がかかっているんですからね」
「そうですとも。安心してください。同志は日本だけじゃない。アメリカにもヨーロッパにもソ連にもいる。しかし、同志が相互に連絡を取るのは危険です。芋づる式に連中に捕まる恐れがありますからね。その日がきたら、あなたにはわたしから連絡を入れます。そして一気に決起するんです! 地球を連中から取り戻すために」
「やりましょう、先生!」
「その意気です。ごらんなさい――」
医師は立ち上がると、オレンジ色の夕日がまばゆく差し込んでくる窓辺に歩み寄った。緑なす木々の葉が涼しい風に吹かれ、のんびりと揺れている。まるで平和の歌を奏でるように。
「この美しい地球を、あんなタバコも吸えない連中に、乗っ取られてたまるものですか――」
* *
「大丈夫ですよ。奥さん。ご主人はノイローゼのあげく強迫観念に囚われて、あんな被害妄想を抱いたんでしょうね」
医師はハンカチを握って神妙に聞いている夫人に言った。
「じっくりと話を聞いてさしあげたら、ご自分でも納得されたようです。もうあんなおかしな作り話を言って、奥さんを困らせることもないと思いますよ」
「そうですか――。よかった……」
夫人は見てわかるほどに肩の力を抜き、椅子にその体重をあずけていた。
「でも――。主人もそうとう追い詰められていたのでしょうね。ふだんは冗談のひとつも言えない堅物ですのに、突然、あんな荒唐無稽な話をしだすんですから……」
「“【嫌煙異星人/ノンスモーカー・エイリアン】”ですか」
医師は邪気なく、くすりと笑うと、棚から一冊の医学雑誌をとりだした。
「実は最近、アメリカや西欧圏をはじめとして、この日本でも、似たような症例が続々と報告されているんですよ。ほら、ごらんなさい。これはアメリカの例です。ご主人と同じようなことを言っているでしょう?」
雑誌を受け取った夫人は、開かれたページを読んで、目をパチクリさせた。
「ほんと……。不思議ですわね」
「不思議でもなんでもありませんよ。妄想や幻覚というものはね、奥さん。その時代その状況を反映して、伝染していくものなんです。たとえば戦後はマッカーサー妄想なんてのが流行りましたよね」
「はあ――」
「最近は映画で、地球を侵略する“エイリアン”ものは珍しくありませんし、嫌煙権ムーブメントのせいで、めっぽう立場の悪くなった喫煙者たちが、同じような妄想を抱くのも不思議ではありませんよ。それに、この情報時代ですからね、ご主人もこの“嫌煙異星人”妄想の話を聞いたことがあるのかもしれません。自分ではしかと覚えていなくともね」
「はあ――。そんなものですか」
夫人はなるほど、とか、ははあ、だとかつぶやきながら、雑誌を閉じ、医師に深くおじぎをすると、礼の言葉を篤く言い、帰っていった。
* *
「それにしてもまいったな――」
医師は、誰もいなくなった病室で、もう暗くなった窓の外のようすを眺めながら、ほっと息をつき、つぶやいた。
「まったく、“嫌煙異星人”とは、おかしな――」
言葉を切り、咳き込むと、彼は背をかがめ、指を曲げて鼻梁にあて、息ばった。と、彼の手になにかが落ちた。鼻に栓を詰めていたのだ。
「よもやと思って、こいつを鼻に詰めておいてよかった。さもなければ、あの毒ガスを吸わさせられるところだったからな――」
わからないように、鼻に栓をつめていたのだ。彼はそれを、ぽいとゴミ箱に捨てた。
「それにしても、“嫌煙異星人”とは、宇宙一の知性を誇るおれたちに、おかしな名前をつけやがる。プライドが傷つくぜ。ま、それもあと少しの辛抱か」
彼は、ニヤリと唇の端を持ち上げて、勝ち誇った笑みをこぼした。
「二十一世紀には、この地球にタバコなんぞという有害物質は、なくなっているに違いないんだからな」
(了)