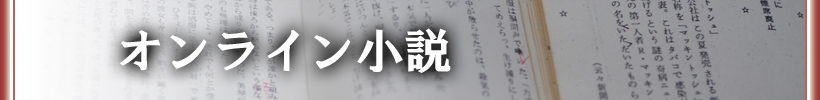オンライン小説
●第3章
ただ待ってはいられない。蘇我野神父はバイクを斜めにして健緑病院の門を出て、この地域の管轄をしている警察署へ行くことに決めた。
以前、この地に住んでいただけあって、土地鑑は健在である。管轄署は数年前まで区の外れにあった。今もそこにあったら、かなりのロスタイムを覚悟しなくてはいけないが、現在、そこは車両基地になり、新しい警察署が高速のバイパス脇に移ったことを蘇我野神父は知っていた。
頭の中のナビにルートを描く。まずは一直線に行って大きな交差点を左折、そこからは緩やかに上下する坂があるが、バイパス前を右折すればすぐに目的地へ到着できるはず。
クルマの通りは多いが、まずは三車線の道を快調に飛ばして黄色信号で左折。もし警官が見ていたら注意されたタイミングだったかもしれないが、一度速度を落とすと次の坂でスピードが落ちる。坂を登り切ったところで、信号に引っかかり、数台の車列の後ろに着かざるを得ない。
しかし、この信号を越えれば、もう警察署は目と鼻の先だ。
警察署はのんびりとしたものだった。特に門衛すらいない。
そこの駐車場にバイクを停め、ヘルメットを脱ぐのももどかしく、蘇我野は警察署のロビーへ飛び込んだ。
その剣幕とは対照的に、カウンターの奥から、のっそりとした警官が、ゆっくりとやってきた。
「どうしました? 事故ですか?」
「事故と言えば事故なんですが、先日、この市で、電車に轢かれそうになったおばあさんを男性が救った事件がありましたよね」
「いや、ちょっとわたしは――」のんびりとした警官は後ろをふりかえり、同僚と二言三言。「ああ、ありましたねぇ、そんな事件が」
奥の方では、はっはっは、と笑い声が聞こえてくる。本当にのんびりとしたものだ。
蘇我野神父は神妙な顔つきを作った。「わたしは、そのとき亡くなられた男性、小山内秀樹さんが所属していたカトリック教会の神父です。その事故について、お訊ねしたいことがあってまいりました」
「神父さんでしたか。どうりで。その格好。暑くないですか?」
もちろん暑いですよ! と声を荒らげそうになるのを抑え、蘇我野神父はトーンを落とした。「地獄の業火はもっと熱いですよ。このぐらい、どうってことありません。いいですか? わたしは今、ひとりの女性を救えるか救えないかの瀬戸際に立たされています。その方は、亡くなられた男性の奥さまです」
真剣さは伝わる。特に、若く溌剌とした、そして瞳にうそ偽りのない男性のそれは。
警官の様子が変わったのがわかった。「それで、どのようなことをお訊ねですか?」
「事故の詳細を知りたいんです。現場検証を行ったのは、この警察署の方ですよね」
「少々お待ちください。詳しい者がいないかどうか確かめてみます。ここの奥、トイレの前に部屋があるんですが、そこでお待ちいただけますか?」
指示された奥の部屋にはいくつかのパーティションで囲まれたエリアがあり、それぞれには机と椅子がそろえられていた。
椅子に座り、腕時計の針を見る。午後二時四十五分。待つ価値があるのかどうか、蘇我野神父は迷った。
が、すぐに部屋に入ってきた背広の男が、片手を挙げて対面に座ってきた。
「お待たせしました。あの事案の被害者の神父さんでいらっしゃるとか。わたしも子どもの頃、教会へ行ってましてね。いやあ、本物の神父さまとお会いできるなんて何年ぶりだろう」
こういう手合いはけっこう多い。蘇我野神父は、ずい、と体を乗り出した。「それでしたら、来週から早速、また教会へいらしてください」
「いやあ、それは――」この若い神父が冗談で受けているわけではないことと、その真摯ぶりが伝わり、私服警官は咳払いをひとつ。「さて、あの事案は、わたしが鉄警と一緒に現場検証をしました。現場の写真などはお見せすることはできませんが、なにかお知りになりたいことがあるとか?」
「つまりですね、その――」小山内秀樹に自殺の兆候はなかったか? と直裁に訊ねるわけにはいかない。それは告解室で聞いた信徒の告白を漏らすことになる。「わたしがニュースで聞いたことですが、小山内さんはおばあさんを抱いて踏切の外に出て救ったあと、線路に引っかかっていたカートを取りに戻って、列車に接触されたと聞いています。それは――本当にですか?」
「ええ、まったくその通りです」私服警官はファイルをめくった。「あの踏切は小さいので、監視カメラは設置されていませんでした。ですので、目撃者の証言からですが、確かに今、神父さんがおっしゃった状況だったそうですよ」
「そこが納得できないんですよ」と、蘇我野神父は指を立てた。「どうして小山内さんはそんなことを。まるでその――それは自殺行為じゃないですか。たかがカートでしょう?」
「そう思われるのも無理はありませんが――」私服警官も真面目にうなずいた。「ところがねぇ。わたしの経験則ですが、こういう状況になると、不思議と人は不合理な行動を取ったりするものなんですよ。ほら、踏切で立ち往生して、クルマから出ていれば死なずに済んだのに、そのまま列車とぶつかって亡くなる事故というのは尽きないでしょう?」
「小山内さんもそういうケースだったと」
「おばあさんの大切なものがカートに入っていると思って、それを線路から外そうと必死になってしまったのかもしれませんねぇ」
蘇我野神父は長いため息をついた。この私服警官の漂わせている雰囲気から、彼はこういった事例に手慣れていることがわかる。その彼であっても、特にこの事件に怪しい陰は感じなかったということだ。
「それで――そのカートはどうなりました?」
「事故現場からかなり吹っ飛んだところで見つかりましたよ。確か、鑑識のあと、助かったおばあさんのところへ、もう返却されているはずです」
蘇我野神父は、サラリと訊ねてみた。「そのおばあさんの住所とかはお教え願えませんかね? こちらからもご挨拶に向かいたいのですが」
「申しわけありませんが――」値踏みするような目でもなく、私服刑事も首をわずかに横に振り「今回、先方さんのご意向で、ご住所やお名前の類いは、一切公開しないということで。ほら、マスコミが押しかけて行くでしょう?」
「わかります。今、わたしの教会にも押しかけてきていますから」
結局、情報らしい情報を得ることはできなかった。蘇我野神父は立ち上がって、腕時計を見る。午後二時五十分。多田井が約束してくれた時間までまだ時間がある。
病院、警察署と回ってきても、蘇我野神父が小山内潤子の告白から受けた違和感はぬぐい去れていなかった。脳裏に〝光から、あらゆる善意と正義と真実とが生じるのです〟という聖句がひらめいた。小山内秀樹は、最後の瞬間に、光を見たのだろうか。それとも闇を?
まだできることが、きっとあるはずだ。
* *
警察署を出たあと、行く先は決まった。腕利きの刑事たちも「現場百遍」と言うではないか。小山内秀樹が事故に遭ったという踏切へ行ってみよう。そこで、なにか自分が感じていた違和感の正体がつかめるかもしれない。
正確な場所はわからなかったが、朝のワイドショーでも事故のニュースは流れており、その画面は記憶に残っているし、蘇我野神父には土地鑑があった。
事故がJRの踏切で起こったことは承知している。だとすれば、JRの線路に沿って走って行けば、それらしいところにマスコミや人混みがあるはずだ。
信号が青になると同時に右折し、JRの線路方面へバイクを走らせる。道行く若者二人が、蘇我野神父の姿を二度見して、言葉を失っていた。無理もない。黒のスータン姿にアライのヘルメットをかぶった大型スクーターが真横を疾走して行ったのだ。なんのアクション映画のいちシーンだろう。
JRの高架下を今度は左折。この一本道をずっと行けば、必ず事故現場に出るはずだ。
チラリと腕時計を見る。すでに教会を出てから四十分が経過している。現在、午後三時――。
やがて、ヘルメットの視界の中に、線路脇にある人だかりと、並んでいるマスコミの放送中継車が見えてきた。
しかし、ああ、主よ。蘇我野神父は射祷を飛ばす。現場の踏切は、想像より、ずっと人が多い。警官も出て現場整理にあたっているくらいだ。
蘇我野神父は少し離れたところにスクーターを停め、ヘルメットを脱いだ。九月の大気は熱を持ち、ぼうっと首回りから暑気が立ち昇る。髪も額も汗でびっしょりだ。頭を振ると、その滴がアスファルトにパパッと散った。
一瞬、自分が着替えて教会を出てこなかったことを後悔した。普段着姿ならば、あの人混みにまぎれこみ、現場を見ることができたはずなのに。
短く、それでも大きく深呼吸。と、蘇我野神父は、スクーターを停めた横に、飲料の自動販売機が立っていることに気がついた。
ひらめくものがあった。むしろ、今、自分が〝いかにも神父〟であるという姿でここにいるのは神の計画なのだ。
今の若者らしく、蘇我野神父はスマートフォンのプリペイド機能を使って、その自販機から、一本の透明な清涼飲料水をガタリと買った。そしてそのペットボトルについているセロハンを剥がして丸裸にする。
そして意を決して、現場の線路に向けて歩きだした。
目ざといマスコミのカメラが早速こちらを捉えるのがわかった。リポーターがディレクターと目配せし、こちらへ飛んでくることも。主よ、すべてあなたにおまかせします。
マスコミのカメラは、この若い神父が、気後れすることなく、堂々と現場の踏切へと、自信をみなぎらせて歩いてくる様を映していた。
「申しわけありません。ムニテレビの者です。あなたは見たところ――」女性のリポーターがいきなりマイクをつきつけてきた。「小山内さんの教会の神父さんですか?」
「そうです。そのことについては、あとできちんとお話しします。今は宗教的儀礼の問題で、まずはそちらにいらっしゃる警官の方とご相談したいことがあります」
歩速を緩めず、スータンを翻して凜として言い放ったのが実に効果的であった。
踏切の前には、ワイドショーで見た通り、たくさんの献花と、聖書が何冊か、それに十字架、小さなマリア像なども供えられていた。おそらく、事件に感動した人々だけでなく、芝浦教会の所属信徒や、近隣のプロテスタント教会の信者なども祈りにきてくれていたのだろう。
踏切は小さく、バイクが通るのが精いっぱいの幅である。JRの線路が上下二本。それでも遮断機は備えられ、生活道路として使われているのがわかる。
警官二名が踏切の両端に配備されているのは、交通整理のためと、また、マスコミが線路に入り込み、鉄道の運行を邪魔することがないように配慮するためであるようだ。
ちょうど、カンカンカン! と遮断機の音がやかましく鳴り始め、警告ランプが左右に明滅しだした。
「はい、みなさん、少し離れてください。列車が通ります」警官が声を大きくする。「危ないですよ。下がってください」
遮断機がゆっくりと下りる。この音ではマイクで音は拾えず、リポーターもいったんひかざるを得ない。
警官の視線が自分に向けられた。蘇我野神父は堂々と彼の横に立ち、話しかけることができた。
「お仕事お疲れさまです。わたしは、ここで亡くなった小山内さんの所属カトリック教会の助任司祭で蘇我野と申します。本日十六時からの葬儀ミサの主司式を務めさせていただくことになっています」
「あ、はい……」
おそらく、今まで〝カトリックの生神父〟を見たことがない警官は、少し面食らっているようだった。
「失礼ですが、お巡りさんは、カトリックの宗教儀礼についてご存じですか?」
「い、いえ。まったく――」
「そうですか。実は、こういう事故で信者の方が帰天、つまり天国に召された場合、葬儀ミサの前に、その地を聖水で清めなければならないのです」
蘇我野神父は、さっき自販機で買った、セロハンを剥がしたペットボトルの清涼飲料水をチラリと見せた。
「お祈りとともに、この聖水をこの現場にまかなければいけないのですが、こうマスコミが多くては――そこで申しわけないのですが、お巡りさんにご協力いただいて、聖水をまく間、人払いをお願いできませんでしょうか。もちろん、次の電車がくる前に、手早く済ませるつもりです」
もちろん、口からでまかせのうそ八百である。
しかし、ローマンカラーにスータン姿の蘇我野神父がまったくの迷いもなく、いかにも慣れた神父面で言うものだから、警官もふむ、ふむ、とうなずいていた。
「そういうことでしたら、わかりました。この電車が行ったら、どうぞ神父さんはその――」
「宗教儀礼です。死者を悼むお祈りを、父と子と聖霊にささげます」
「それを行ってください。わたしと相方が人払いを行いますので」
警官は胸元の無線機のマイクを使い、通過中の電車の向かい側にある踏切出口の警官を呼び出して、二言三言話し始めた。
通過する電車の風圧が、汗に塗れた髪に流れて心地よい。カンカンカ……と踏切の警報音が途切れた。ゆっくりと遮断機が上げりだす。
わっと詰め寄ってきたマスコミのカメラとマイクの前に、さっきの警官が手慣れた様子で割り込んできた。
「はい、ごめんなさいねー。今、こちらの神父さんが、シューキョーギレーをしなければいけないので、ちょっと邪魔しないであげてください」
手刀で礼を表して、蘇我野神父は遮断機が上げった踏切の中に入った。
線路とその周囲はすでに洗い流され、特に事件現場と知らされていなければ、なにも変わったところは感じないだろう。枕木からは夏の蒸気に混ざり油の臭いが漂ってくる。
蘇我野神父は周囲を注意深く観察しながら、それらしく、胸の前で十字を切った。「父と、子と、聖霊の御名によって、アーメン」
マスコミのカメラが一斉に自分に向けられていることを感じる。しかしそれに構っている余裕はない。
小山内秀樹が自殺だとしたら、そして、自殺ではないとしたら、なにかその痕跡が、この現場に残ってはいないだろうか。
「主よ、ここであなたが天に召された小羊を心にとどめてください。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとおっしゃったあなたの言葉を守った信徒の魂が、迷うことなくあなたのもとへと向かうことができますように」
そして〝聖水〟に見立てた清涼飲料水をあたりにパパッとまく。
若く端正な顔立ち、ローマンカラーにスータンが決まるスマートな〝神父〟が、聖水をまいて祈りをささげている――これはむしろ彼ひとりの方が絵になる! と、マスコミのカメラが集中し、警官の手をすり抜けてインタビューしようとするリポーターがいなかったのは幸いだった。
祈りの言葉を口にしながらも、蘇我野神父は周囲を注意深く観察していた。
踏切に流れたであろう、生々しい事故の痕跡は、すでに洗い流されてしまっている。が、線路には真新しい銀色の傷跡が少し。ここにカートの車輪が引っかかったのだろうか。しゃがんで触れてみる。九月の熱が指先に伝わるが、特になにか感じるものがあるわけではない。そこにも〝聖水〟を掛け、両の親指を組み合わせた合掌で祈る。
「父よ、この地の穢れを除いてください。聖母マリア、すべての天使と聖人、特にあなたが召された小羊の霊名聖人クリストフォロス。彼のためにお祈りください」
あっそうか! 蘇我野神父は、自分の祈りを反芻し、【そのこと/傍点】に気がついた。違和感のひとつはそこにあったのだ。
それは確信に変わった。小山内秀樹は自殺などしていない。絶対に。
「神父さん、そろそろ――」
警官がうながしてくる。蘇我野神父の心に焦りが油のように浮かんでくる。
主よ、このままでは小山内夫人の疑いを晴らすことはできません。天を仰いで、蘇我野神父がそう祈ったとき、ふと、線路の脇、砂利のあたりにキラリと光るものがあった。
「聖霊は父と子から出て、父と子とともに礼拝され――」
聖水をまくパフォーマンスをしながら、蘇我野神父は砂利のところへと降り、その光るものを手に取った。輝いていたのは金具だった。引きちぎられた革のようなものについている。 蘇我野神父はそれをなんの気なしに手に取ってみた。最初は、ひょっとしたら小山内秀樹の〝ロザリオ〟かと思ったが、違う。薄汚れたただの革バンド――
「神父さん、そろそろ――」
警官に声を掛けられ、蘇我野神父はハッとして、取りあえず【それ/傍点】をスラックスのポケットにすべり込ませた。
「わたしは、聖なる、普遍の、使徒的、唯一の教会を信じます。罪の赦しをもたらす唯一の洗礼を認め、死者の復活と、来世の命を待ち望みます。アーメン!」
最後は〝使徒信条〟で締めくくった。
「ありがとうございます」と、警官二人に「これで、この場のわたしの役目は終わりました。感謝します」
そのとたん、わっと、各局のリポーターたちが蘇我野神父の周りに駆け寄ってきた。「ムニテレビです。今のお祈りは小山内さんのためですか?」
「テレビナポンの小林です。小山内さんのお人柄についてなにか一言」
「小山内さんの教会の神父さんでいらっしゃいますよね。小山内さんはどんな方でしたか?」
「すべては――」蘇我野神父は、よく通る、澄んだ大声で言った。〝地声に魅力があること〟は、神父の必要条件ではないが、十分条件としては確かにあるのであった。「午後四時から教会で開かれる葬儀ミサの説教でお話します。今、この場ではなく、教会の十字架の下で!」突き出されるマイクやICレコーダーにもみくちゃにされるのは避けようがない。腕時計の針は午後三時五分。多田井と約束した時間だ。
「失礼、ちょっと失礼。電話を――」
マスコミ群から転ぶように逃げながら、スマホをポケットから出し、スクーターへと駆け出しながらメールを確認する。
* *
+主の平和。蘇我野神父さま。
お世話になっております。多田井です。
件の件ですが、
森村美枝子さん。九十二歳。
住所は「中央区重富町五‐二十三‐九」。
それでは、とりいそぎ。
神に感謝。
* *
きたぁーっ! と、蘇我野神父は心の中でガッツポーズを取りたくなった。やはり多田井はただ者ではない。さすが芝浦教会のCIA。それに、中央区重富町ならば、ここから二十分弱で行ける。
短期記憶した住所をスマホのマップにたたき入れる。ピンポイントではわからないが、近くまでは行ったことがある。
ヘルメットをかぶるのももどかしく、マスコミの一群にバイクの煙を浴びせて、蘇我野神父はさっき来た道を引き返して猛然と走りだした。
(第4章へ続く)