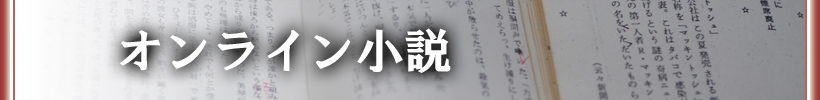オンライン小説
コードレス・ガール
「えーいっ。絶対、探し出してやるからね、〝コードレス・ガール〟っ」
学籍名簿を繰りながら、あたしは内心、唾を飛ばしたりして。だって、たとえ本気でないにしろ、『殺してやる』、なんて言われたのよ。その前にこっちから見つけだして、逆襲してやるンだ。
なんでこんなことになっちゃったかってのを説明するには、時計の針を、先週の土曜日に戻さなくちゃなんないんだけど――
聞いてくれる?
* *
「♪ン、フッフ、フーフ。ンッフーフフ」
見なさい、このむきたての桃みたいな、みずみずしい肌。シャワーの粒を弾かせて、思わず鼻唄がでちゃう。
だって、今日でやっと、地獄の前期試験が終わったンだもン。結果はともあれ、明日の日曜は、久々にすべてを忘れて、お寝坊できそう。徹夜続きで体はバテバテだけど、いままでずっとキツかった心の枷が外れたから、この疲労感だって、心地好いんだ。
「♪ンッフーフ、フーフッフー、フゥ」
お湯が玉ンなって、ビニールのカーテンにこぼれてく。ま、女子学生の住まいにはありがちの、小さくて不便なユニットバスだけど、実家の古いお風呂でナメクジが出るたびに、悲鳴を上げまくって家族の顰蹙を買ってたあたしみたいなヒトには、この清潔感だけで、もう、大満足。
ほ~んと、この寮に入って良かった。
そう、ここ、実は寮なンだよね。あたしの行ってる聖沢女子短大の学生寮なンだ。去年できたばかりのホヤホヤで、どこもかしこもピッカピカなの。
〝寮〟って聞いて、狭い部屋、暗い日々、哀れにも軟禁され、生糸を紡ぐ乙女たちの泣き声、門限を破った咎人は地下室に閉じ込められ、そこからは毎夜、ムチの音が響く(あるかっ)――を想像した人は、はっきり言って、感覚が古ぅい。
この〝清新寮〟は、一人一個室の完全防音ワンルームマンション仕立て。バスは自分専用だし、冷暖房は当然完備、電話はもちろん、テレビはなんと衛星放送まで入ってるし、加えて、共同施設にはテニスコートからプールまであるって豪華さがウケて、マスコミがこぞって取材に来たほどの寮なンだよ。
男子禁制ってのが玉に傷としても、都心に近くてこれだけの生活ができるなんて、最高じゃない? あたしもそうだったけど、清新寮に入ることを目当てに、この学校を受験した学生ってのも、珍しくないの。
受験生の絶対数が減りつつある現在、旧態依然としていては、大学もやっていけませぬ、ってことで、新しい魅力を開発するための試みだったらしいんだけど、それは大成功、大学側も嬉しい悲鳴ってとこみたい。
もっとも、こういうとこだから、そこはそれ、かなりおゼゼは取られちゃうんだけどね――ま、それは家の父上さまのスネが、ゴボウになれば済む話でして、あたしには関係ございませんと。なはは。でも、変に一人暮らしをされちゃうよりは、いくらお金が掛かっても、こういう男子禁制の寮に入っててくれる方が、安心できていいって両親が多いのも、また、事実みたい。うン。
シャワーの栓を、きゅっとひねって止める。タオルを取って体を拭きふき、さて、これからどうしようかしら。せっかく自由になる時間が戻ってきたってのに、すぐ眠っちゃうのも、なんとなくもったいないじゃない。
でも、土曜の夜八時ってのは、なにをするにしても、なかなか難しい時間よね。彼氏でもいれば、別なんだろうけど――外出許可は、三日前までに寮庶務課まで提出のこと。だったっけか。入学以来、一度もやったことないぞお――悲しいかな、そんな人のいない現実を噛みしめるの。うっ。
久しぶりに、高校ンときの友達に、電話でもしようかナ。そう思いながら、バスルームの扉を開こうとしたんだけど――そこで、あたし、ぎょっとしちゃった。
消したはずのテレビの音が、聞こえてきてるんだもの。
あたしの勘違い? ううン、違う。お風呂に入る前、嫌いな女優のCMが流れそうになったンで、足で蹴っ飛ばして(おほほ)消したこと、よく覚えてる。第一、人の気配がするンだ。物音だってガサゴソしてるし。
そういや――って、あることを思い出して、せっかくシャワーを浴びたのに、あたしはタラーリと冷汗落としてしまった。この清新寮には、数カ月前から、土曜日の晩に、盗難事件が相次いでたンだ。
寮の入口は、守衛さんが四六時中見張ってるし、部屋にもそれぞれ鍵がかかってるから、まず間違いなく内部犯行だろうってのが、警察の見解。で、一時は寮内が、かなり気まずい雰囲気になっちゃったけど――残されてた足跡が男のものだったとか、真夜中に男の影を見たとか、噂が流れだして、みんな気をつけようってことで、そのままうやむやになっちゃった。
もしかして、その犯人が、今、あたしの部屋に!? ヴ、ヴぞっ。内部犯行だとしたら、友達の犯行現場を押さえることになっちゃうし、もし、犯人が男だったら――うう、その先は考えたくないっ。
でも、このままバスルームに籠もってて、みすみす犯人を逃したりしたら、あとあとなに言われるかわかんないし……。変な噂にされたりしたら、一生おヨメに行けなくなっちゃう。ここは一番、勇気を奮わなくっちゃ! 狭いユニットバスん中でパジャマを着こみ、せめて武器の代わりにと、トイレ詰まりに使う、ゴムのついた棒をしっかと握り、ごくりと唾を飲んでから、あたしはエイヤッと飛び出した。
「か、覚悟ーっ!」
その瞬間、部屋の中に確かに人の影を見て、肌が泡立ってしまった。けどこうなったら、もう遮二無二、突進するしかない。
「ひ、ひえっ」
相手は悲鳴を上げたけど、こっちは目をつぶって思い切り、顔面目掛けて、トイレ棒を突き立ててやった。手応えありっ。敵は顔に、ゴムの部分を吸盤みたいくっつけたまま、後ろにぶっ倒れちゃった。
「や、やったあ――」
「あ、あのなあ……」と、その不法侵入男は、みょーに冷静に、一言。「あねきは、はるばる訪ねてきた、血をわけた弟を出迎えるのに、こんな仕打ちをするわけ?」
「そ、その声、まさか――た、孝明!?」
「そうだよ」ぶすくれた声で答えると、トイレ棒をすぽんと抜く。丸く赤い輪がついたその顔は、おお、確かに我が弟ではないですか。「この顔を、見忘れたとは言わせねえぜ」
おまえは遠山の金さんかッ。おっと突っ込んでる場合じゃない。「あ、あんたこそ、なんでこんなとこにいンのよっ。あたしゃ情けないわっ。あんたが連続土曜日盗難事件の犯人だったってことにゃ、目をつぶるとしても、こともあろうに姉の部屋に侵入して捕まるドジを踏むなんてっ」
「はあ?」
「だから、あんたが連続土曜日――」
「なにわけのわかんないこと言ってんの? オレはただ、遊びにきただけなんだぜ」
「え? あ――そうなんだ。ゴメン」なんという勘違い。ま、冷静になってみれば、そんなことがあるわきゃないよね――と納得しかけて、ハタと気づくあたし。「って、ゴマカされるかっ。ここはたとえ父親と言えども、絶対に中に足を踏み入れられない、男子禁制の女子寮なのよ。どうやって、忍び込んできたのよっ」
孝明は、バツが悪そうに舌を出すと、窓を指差した。
「窓!? 冗談。ここ、三階なのよ――」
「屋上につながってる、非常梯子があるだろ? そこを登って、梁を伝ってここまでやってきたのさ。スリルあったぜ」
「ウソでしょう!? 門はどうしたのよ。守衛さんが見張ってたでしょ?」
「ふ。遅刻を常習とするこのオレさまにかかりゃ、どんな塀もひとっ飛びだね。裏の塀の鉄条網を切っちまえば、あとは簡単さ」
遅刻の常習というより、泥棒の常習者みたいな口ぶりで言うんだから、まったく。
「信じらんなぁい。この寮、赤外線なんとか装置ってので守られてるって聞いてたのに。そんな簡単に入ってこられるわけぇ?」
「ああ、ああいうハイテク防犯システムはね、たいてい脅しだけで、スイッチ切ってあるとこも多いのさ。ネコとかネズミとかでも反応しちまうから、うるさいだろ?」
言葉もなかったりする。こんな悪ガキ高校生にやすやすと侵入を許すなんて、大事な娘サンをお守りするって名目で、高い金取ってるわりには、この寮もズサンなのねえ……。「しっかし、女子寮って言うからさ。てっきりみんな軟禁されてて、泣きながら生糸を紡いだり、地下室でムチ打たれたり、どこかに売られたりしてんのかと思ってたけど、ここ、すっげえじゃん。衛星放送まで入るなんて、贅沢すぎるぜ」なるほど、消したはずのテレビをつけたのは、こいつだったのよね。考えてみれば、泥棒がテレビを横目に仕事するわけないけど。「遊びにきて良かった。ところで、可愛い弟がはるばるやってきたんだから、今晩くらい泊めてくれるだろ?」
「じょっ、じょっ、冗談じゃない。えーい、くつろぐなっ。ここにきた本当の理由を話しなさいよ。どうせまた、親子ゲンカでもしたんでしょ」
「あたり」
寝っ転がってテレビを見ながら、いけしゃあしゃあとこの返事。我が弟ながら憎たらしい。首締めてやろうかしらん。
「〝あたり〟じゃないでしょ。そんなとばっちりをあたしン方に持ってこないでよ。男を部屋に入れたなんてバレたら、いくら血の繋がった弟っつったって通用しないんだから。追い出されるのはあたしなンですからね」
「冷たいこと言うなよ。だいたい、ケンカの原因の遠縁は、あねきにもあるんだぜ」
「どーいうことよ」
「あねき、ここに入る前に、週末と日曜は、家に帰るって約束したくせに、全然守ってないだろ。親父はあねきが可愛くて仕方ないタチだから、いらいらしてオレにあたってくんのさ。オレの身にもなってくれよ」
う~む。痛いところをつかれてしまった。でも、うるさい親の小言が待ってンのを承知で、素直に週末、実家に帰る娘なんぞ、この世にいるわきゃ――訂正。少なくとも一人はいるな。あたしと同じ階に住んでる遠藤さん。彼女は律儀に毎週帰ってるけど、ま、そんなのは、例外中の例外よね。
あたしは電話をむんずと掴んで、孝明の目の前に突き出してやった。
「そんな屁理屈言ってないで、今すぐ家に電話しなさい。きっと心配してるんだから」
「やーだね、お?」孝明はあたしの出した電話を見て、目を光らせた。「あねきの電話、コードレスなんだ」
そう。あたしの電話は、入学したときにお祝い金で買ったコードレスホンなの。テレビドラマなんかで良く見るし、第一、お洒落でしょ? 寮でも使ってる人、多いんだ。そういや、遠藤さんとも、便利よねって話で盛り上がったことがあったっけ。
「いーだろ。うらやましいか」
「逆、バカだよ、バカ。特に、電波の飛びがいい小電力コードレスなんて、誰に聞かれてるかわかんないんだぜ」
孝明ったら、真顔で言うんだもん。さすがにどきっとしちゃうよね。
「まさかあ。そんなはずないわよ。それに、そーゆーのを聞ける無線機って、すごく高くって、なかなか手にはいんないんでしょ?」
「どっから、そんな迷信が出てくるんだい。これだから、ハイテクについていけない世代は困るよな――ジャン」自分の口でファンファーレを言うなり、孝明はポケットから何かを取り出した。小さな、ボタンのついた黒い箱。ネコのヒゲみたいなアンテナがついてる、ラジオだった。「秋葉原価格三万円弱。でも、これ一台で自動車電話もコードレスホンもばっちり受信できる、高性能受信機なりい。今日、電通部のダチから奪ってきたんだ」
「う、うっそでしょう!?」
「論より証拠、ってかぁ」
拍子をつけてそう言うと、スイッチを入れる――と、雑音に交じって、確かに人の声が聞こえてきた!
『でしょ、あのコ、ちょっと生意気じゃん。でさあ、あたし、言ってやったわけ。ちょっとは礼儀ってもんを勉強しろって』
『そうそう。言ってやりゃいいのよ。ガツーンとさ。で?』
『そしたらさあ、シュンとするどころか、先輩を見習ってるだけです、って言いやがんの。ふざけてると思わない?』
もう、びっくり。確かに電話の会話。女同士の生々しい話が、筒抜けになって聞こえてきちゃうんですもの。
コードレスホンの会話が、特殊なラジオで聞けるってのは、何かで読んで知ってたけど――まさかこんなに簡単に聞けちゃうなんて。あたしの電話も、今まで他人に聞かれたりしてたのかしら。おぞぞぞぞ。そう思うと総毛立ってしまう。
「たっ、たっ、たっ、孝明、やめなさいっ。盗聴なんて犯罪よ」
「なんにもわかってねえんだな、あねきは。こういうのは盗聴じゃなくて、傍聴っつうの。犯罪でもなんでもないんだぜ。電波法では、人の通信を聞くことは禁じてないのさ。もっとも、聞いた内容を人に話すのは、御法度なんだけどね」
「そ、それにしたって悪趣味よ。人の電話、盗み聞きして、面白い?」
「面白い」首締めたろかっ。でも孝明は平然と「だいたい、自分【家/ち】の隣に露天風呂が出来れば、誰だって覗いちまうだろ? 本来こういうのは、風呂の側で囲いをするのが当然なのさ。責めるんなら傍聴対策をしないメーカーを責めるべきだね」
なるほど、一理は、ある。けどねえ。
「この寮でコードレスを使ってる人の会話は、これでみんな筒抜けだぜ。あねき、聞いてみたくない?」
「いやーよっ。うちの寮にいる人は、みんなまじめで誠実な人ばっかりなんだから。そんな失礼なこと、できないわ」
ラジオから聞こえてくる会話は、今度は別の二人に変わってる。土曜日のこの時間、わりと電話してる人も多いみたい。
『なら、どうして電話、くれなかったの? 今さら遅すぎるのよ』
『じゃあ、もうオレたち、ダメなのか。おまえはもう、オレのこと――』
『――ゴメン。あたしが今好きなのは、あなたじゃなくって、タカシくんなの』
ヴ。今度の男女一組は、なかなかシビアな話してるんでないかい?
孝明は、あたしの顔色をうかがって、ニヤニヤ。「ま、あねきが聞きたくないっつーんなら。しょうがねえ。スイッチ切っちまお。せっかく土産代わりにって持ってきたのに」『教えろ、そいつの電話番号、教えろ。オレが直談判してやるっ』
『やめてよ。絶対イヤ!』
スピーカーから流れてくる会話は、手に汗握る緊迫の真っ最中。あたしが、スイッチに手を伸ばしかけた孝明を、思わずとめてしまったのも――無理ないよね。
「ちょ、ちょ、ちょっと待ってよ。今、いいところじゃない。もう少し、もう少しだけ聞かない?」
神さま、仏さま、ごめんなさい。千鶴は(これ、あたしの名前です)悪いコになってしまいました。
『今まで、楽しかったわ。思い出、ありがとう』
『いいのか、おまえ、本当にそれでいいのか。この電話を切ったら、オレたちほんとに終わりだぞ』
そう言いつつ、自分からは切ろうとしないんだから、こういうときの男って、未練がましいもんなのね、うん。勉強になるなあ。
『別にいいわよ。じゃあ、サヨナラ』
ガチャン。女のコの簡潔な別れの言葉を終いにして、あとはノイズが鳴り出した。
長い溜め息をつくあたし。「はあ。こっちも緊張しちゃった。今の女のコ、誰だったのかしらん。この寮の住人だってことは、確かなわけ?」
「コードレスホンの電波が届く範囲は、だいたい百メートルくらいなんだ。この寮は敷地が広いから、電話の主はまず間違いなく、寮内にいるね」
「そうなンだ……。今のはいったい、誰だったンだろ。わかる?」
「それはちょっと、無理だなあ。電話だと、声も変わっちまうしね。会話の内容とかで探るしかないんじゃない」
なるほど。聞くことはできるけど、その主を探すのは、難しいってことか。
ラジオからは、もう別のカップルの声が聞こえてきてた。
『ウン、もう。決まってるじゃない。好きなのは、あ・な・た、だけよ』
『ほんとに? 良かった。この前のデートんとき、なんかそわそわしてたろ。だから気になっちゃって、仕事も手につかなくてさ』
『もう、バカなんだからぁ。あたしが、あなた以外の誰を好きになるっての?』
……アセアセ。こっちのペアは、勝手に二人の世界を構築しておりますな。と、急に二人の台詞を切って、何かがプープー鳴り出した。
『あ、待って、キャッチホン入っちゃった。実家からかもしんないから、ちょっと待っててくれる?――ガチャ――もしもぉし』
『もしもし? あ、オレ。城南大のマモルくんでーす。元気してた?』
『あ、マモルくん? 元気元気。電話待ってたんだあ。うっれし~い。あ、ね、ちょっと待っててくれる? これ、キャッチで、今実家と話してたんだ。そっち切っちゃうから――ガチャ――あ、もしもし? やっぱり実家からだったの。話、長くなりそうだから、また電話してくれない?』
『いいよ。じゃあ、また、今度――』
こ、これは――このコ、ふたまたかけてたわけね。誰にもわからず、うまくやってると思ってンだろうな、本人は。まさかこうやって、ばっちり聞かれてるとも知らずに。
「この寮にいる人は、みんなまじめで誠実な人ばっかり、ねえ――」
「こ、こんな人は例外よ。そうに決まってるわ」
とは言ったものの、あたしの認識は甘かったみたい。だってそれから聞こえる電話という電話、内容的には、みいんなこれと五十歩百歩なンですもの。人の悪口、抜け駆けの相談、愚痴、厭味、口ゲンカ。たまぁに幸せそうに、デートの相談をしてるペアもいたりはするけど(男のコと話してる人が多いのにもびっくり。みんな、彼氏がいるなんて顔、全然してなかったのに)それはそれなりに、頭にきたりして。
「みんな、表と裏とじゃ、わりと違うンだなー。なんかすっごいショック。あたし、明日から、人見る目が変わっちゃいそう」
「な、社会勉強になったろ?」
「うン……」
こっちはもう、毒気を抜かれて、どつき返す気力もない。ラジオはこれでもかと、新しい会話をキャッチしてるし。
『あんな男を好きになったあたしもバカだけど、相手の女もひどいと思わない。彼にあたしがいるってのを承知で、モーションかけてきたのよ』
『ひっでえ女。とんでもねえな』
男女の会話だけど、恋人同士って感じじゃないみたい。女の方は、さっきから半分涙、半分怒りの口調でまくしたててる。
『彼ったら、あたしに内緒で、その女と会ってたの。問い詰めたら、二人で旅行に行ったって言うのよ。信じられる?』
『マジかよ。オレ、あいつに言ってやろうか? ふざけたことすんなって。友達として許せねえよ。そんなこと』
なるほど。電話の相手の男は、この女のコの彼氏の、友達なんだな。ふむふむ。で、このコは、自分の彼氏を他の女にとられて、この男に電話で愚痴をこぼしてるわけだ。
『やめて、もういいの。彼のことはあきらめたから。あなたからよろしく言っといて。でも――あの女だけは許せない。あたし、絶対復讐してやる。殺してやるわ。絶対っ』
おー。なんとまあ、恋の恨みは怖い。
『物騒なこと言うなよ。その女、なんてやつなんだい?』
『良くは知らないんだけど――あたしと同じ大学の文学部にいる、ワタナベ・チヅルって、フザケた女!』
「ひえーっ」
それ、あたしじゃない。聖沢女子短大で渡部千鶴ったら、あたししかいないもン。なんでなんでそうなるわけ!? 濡れ衣よぉ。
『とにかく、絶対許せない。どんな女か調べて、ひと思いに後ろから刺してやるっ。そんときは後のこと、よろしく頼むわよ』
『おいおい。冗談にならないぜ。頭を冷やせよ、ヒロミ。じゃあ、来週の土曜にでも、また電話すっから』
『あ、うん。じゃ――』
電話は、そこで終わってしまった。
「こ、こ、これ、どういうこと!?」
「よくわかんねえけど、要するにあねきが、誰かの男を奪って、恨みを買った、と」
「違~う! あたしゃそんなことしてないっ。まさか、どっかの男が、あたしの名前をダシに使って、別れの口実にしたんじゃ……。えーいっ。いったいどこのどいつだっ」
「男が誰かはわかんないけど、女の方なら手掛かりはあるぜ。ほら、名前、ヒロミとか言ってたじゃん」
「そ、そっか。この寮で、ヒロミって名がつく、コードレスホンを使ってる女。そいつが今の――」あたしは、星飛雄馬のごとく瞳に炎を燃やして、ずずずいっと立ち上がった。「む、むざむざ殺されてなるもんですか。こっちから逆襲して誤解を解かなくっちゃ」
* *
で、最初のあたしの台詞に繋がるってわけ。この清新寮の寮生で、コードレスホンを持ってる、〝ヒロミ〟。それ以外は、それこそ【手掛かりのない女/コードレス・ガール】。彼女に後ろから刺される前に、先に見つけだして誤解を解かないと、のんびり授業中の居眠りもできやしない。
こうして、あたしのコードレス・ガール探しは始まったンだ。
* *
っても、候補者をしぼりこむのは、そう難しくなかった。月曜日に庶務課で学籍名簿を借りて、まず寮に住んでいる〝ヒロミ〟を探す。弘美、浩美、博美、広美、裕美、宏美、洋美……。わりと多かったけど、この中でコードレスホンを使ってる人をふるいにかければ――ラッキーなことに、入寮名簿に、電話の有無、種別が記載されてたのよね――残ったのは三人しかいなかった。
今、中庭に呼び出して、目の前にいるのが、その一人目、相田博美さん。
「あたしに用って、なんですか?」と、彼女は不安そう。「確か、渡部さん、でしたよね? 清新寮の――」
おおっと、こっちの名前、わかってンじゃない。もしかしたら、後ろ手に刃物かなんか持ってンじゃないかしら。用心用心。
「実はネ、あたし、コードレスホン使ってるンだけど、最近、混線して、人の電話が嫌でも入ってきちゃうンだ」この言いわけは苦肉の策。実際にはこんなこと、絶対ないって孝明は言うンだけど、まさかラジオで傍聴してたなンて、言えないもン。「で、別に聞きたかったわけじゃないンだけど、たぶんあなたと思える人の、会話を、聞いちゃって――」
彼女が、さっと顔色を青ざめさせた。「え!? じゃあ、あなた、あのこと知ってるの?それであたしのところへきたのねっ」
間違いない、この反応。この人がコードレス・ガールだったんだわ。「そうよ。でも聞いて、あなたが考えてるようなことは――」
「ごめんなさい、見逃してっ」あたしが言い終わる前に、彼女は後ろに飛んで、手を併せて拝んでた。「ほんとはいけないことだって、知ってたのよ。けど、あのまま放っておくわけにはいかなくって。お友達にも、貰ってくれないって、聞きまくったんだけど、誰もいなくって、だから仕方なく――」
「は!?」なんか話がずれてやしないかい?「なんの、話?」
「だから、あたしが部屋で飼ってる、子ネコのこと――でしょう?」彼女はきょとんとして「雨の日に捨てられてて、あんまり可哀相だったから、拾ってきちゃったんだけど――その話じゃ、ないの?」
……どうやらこの人はシロだったみたい。
* *
「そう。あなた、あの電話、聞いてたんだ。まいったな――。じゃあ、あたしがやろうとしてたことも、バレちゃったわけだ」二人目、石井洋美さん。ショートカットで背が高くて、あたし、ビビッてしまいそう。第一、話し方が、すごく冷静なんだもん。「でも、あたし、やっぱり諦めきれないんだ。だからやっぱり、やるしかない。あなた、なに考えてるのかしらないけど、妨害しようったって、ムダよ。あたし、今度の決意には、命張ってんだからね」
げ、げげげっ。いきなり物騒な話になっちゃったあ。会談の場所を、昼休みで賑わってるカフェテラスにして良かった。ここでブッスリやられたりは、しないよねえ。
「あ、あのあの。ね、でも――あなたが思ってるようなことは、全然ないのよ。あたし、決して――」
「なに言ってんの。今更いい子ぶらないでいいわよ」ひええー。怖いー。洋美さんは、じろりとあたしを睨んで「どうする気? 寮長に言う? 大学にチクる? いくら払えば黙っててくれるの」
「お、お金なんかいりませんっ」これには、あたしもカッとなっちゃった。ビビッてたって、言うことは言ってやらなくちゃ。「あたし、あなたが思ってるような女じゃないンだからっ。それに忠告しとくけど、あなた騙されてンのよ」
「どういうこと?」
「だから、あなたの彼氏よ。あたし、名前を拝借されただけで、あなたの彼氏なんか見たことも会ったこともないンだから。あなたの彼氏はね、あなたと別れたい一心で、あたしと旅行に行ったなんてウソをついたのよっ」
「――あなた」彼女の目が、点になっちゃった。「なんの話してんの? 彼氏いない歴十八年のあたしを掴まえて」
「え!?」
「あなた――あたしとあにきの電話、聞いてたんじゃないの?」首をプルプル横に振るあたしを見て、彼女は豪快に笑い出した。「あはっは。なんか、互いに誤解があるようね」
今度は、あたしの目が点よ。「は、あ」
「こうなったら、ぶちまけちゃうけど。あたし、昔からの留学の夢持ってたんだ。けど、親の反対で、無理やりこの短大に入れられちゃってね。でもあきらめきれなくって――自費で頑張ろうと思って、夜のバイト始めたのよ。あにきにそれを、電話で相談したんだけどさ。大反対。それを聞かれたと思ってさ」
「あは、あは、あはは。そうだったンですか。なんか、あたし、間違ってたみたい。ごめんなさい」二人でクスクス。根は気のいい人で良かった。「あの、でも、夜、寮を抜け出すのはともかく、夜のバイトってのは、あたしも感心しないと、思うンですけど――」
「そうかなあ。あにきもそう言うけど――」彼女は、あたまをかきかき。「夜間道路工事の交通整理のバイトって。そんなに不健全?体も鍛えられるし、いいと思うんだけどな」
……お兄さん。このくらい許してやんなさいっ。
* *
三ひく二は一。もうコードレス・ガールは決まったも同然。あたしは覚悟を決めて、最後の一人、宇野博美さんを講義室に呼び出した。
「いつか、あたしと彼の前に、あなたみたいな人が現れると思ってたわ」あたしが例の電話ことを切り出すと、彼女は憂いを秘めた目で、この台詞。もう間違いないって感じ。「あなたがなにを考えて、あたしたちの仲を裂こうとしてるのかは知らないけど、あたしと彼の話、聞いてくれる?」
「あ、でも、あのね――」
「あたしと彼はね、昔っからの幼なじみなの」彼女はあたしの言葉なんか、まるっきり無視して「子供の頃から、いつも一緒だった。あたし、幼稚園のときから、彼のおヨメさんになるんだって、いつも言ってたわ――それがほんとの夢になったのは、高校のとき。お互い、好き同士なんだって気づいて……。でも彼の家は代々続いた鰻屋。対してあたしの家は老舗の梅干し屋。皮肉なことに、あたしたちの家は宿敵同士だったのよ。二人の結婚が認められるわけ、なかった――」
なんでそうなるのかはよくわかんないけど、ま、泣ける話だわね。
「しまいには駆け落ちまでしたけれど、結局見つかって、彼とは引き離されたわ。そして、無理やり寮に入れられた。彼と二度と会えないようにって、ね。でも、二人の愛はこんなことじゃ崩れやしない。親たちがどんな妨害をしてきても、あたしたちの愛は激しく燃え広がるわ」延焼すなっ。「わかった? どうせあなた、あたしか彼の親に頼まれて、あたしたちの仲を裂こうとしてるんでしょうけど、そんなこと、できやしない」
あれ? な、なんか話が違うんじゃない?「あのー、ひとつ伺ってもいいですか?」
「ええ。あなたが訊きたいことはわかってる」彼女は一言。「食い合わせなんて、科学的根拠に乏しいわ」
「へえー、やっぱり」って、自分でボケてどうすんのっ。「じゃないっ。あなたとその彼の仲は、うまくいってるんですか?」
「あたりまえじゃない。あなた、あたしたちが密会してるの、彼との電話聞いて、知ってるんでしょ?」
「じゃ、じゃあ、最近、彼が他の女に誘惑されたとか、旅行に行ったとかは――」
「彼がそんなこと、するわけないじゃない」
言いきるー。そこまで彼を信頼してるんだ。ちょっと羨ましいナ。
けど、これ、どーゆーこと? 最後の彼女まで、コードレス・ガールじゃなかったなんて、あたしが聞いたあの電話は、一体……。
* *
「すると、結局三人ともシロだったわけか」
と、孝明。今日は、この騒動が始まってからちょうど一週間目の、再び土曜日。コイツ、懲りずにまた、塀を乗り越え梯子を登って、あたしの部屋にやってきてるんだよね。
「そうなのよね。いったい、どういうことだと思う? あたしの調査漏れかなァ。それとも誰かがウソついてンのか――」
「でもまあ、いいじゃん。あれから一週間たつのに、あねき、後ろから刺されなかったんだから、相手もあきらめたんじゃないの」
なんちゅーお気軽なやつじゃ。ま、そうならいいけど、なんかすっきりしないのよね。「あ、いけね。オレ、電話しなきゃいけなかったんだ。あねき、電話貸してくんない?」
「バカが使うコードレスホンなら、貸したげるわよ」
「う~ん」孝明は、一声唸って「背に腹は代えらんねえか。今、電話しとかないと、後でめんどくさいことになっちまいそうだから」
そう言うと、孝明ったら、あたしのコードレスホンを掴んで、どこに行くかと思いきや、なんとバスルームに籠もろうとするのよ。「ちょっとちょっと。なんのつもりよ」
「当然だろ。あねきに聞かれたくないもの。オレにだってプライバシーがあるんだぜ」
さんざ人の電話聞きまくってたヤツが、よく言うわよねえ。って、呆れてる間に、籠城されちゃった。でもこいつ、我が弟ながらヌケてるの。だって、あのラジオがあたしの手元に置きっぱなしなンだもン。
当然、聞くっきゃない。見よう見まねでスイッチ入れて、ボタンを押して――おっと、入った! これ、バッチリ孝明の会話っ。
『だから、別に電話しなかったのは、嫌いになったとかそうじゃなくて、ただ単にクラブとかで忙しかっただけなんだって』
『ウソよ、ウソ。孝明君、高校に入ってから、全然会ってくれないじゃない』ははあ。相手の彼女は、中学ンときから愚弟を好いてくれてた、奇特なあのコだな。孝明のヤツ、懸命に隠してるけど、姉は二人が、街でデートしてたのを目撃したことがあるノダ。『高校、違っちゃったから、そっちの学校で、あたし以外に好きな人ができたのね、ぐすぐす』
『おまえなー、オレはホモか? オレの高校は男子校なんだぞ』
『それがどうしたのよっ。あたしは女子校よっ』取り乱してるなー。『男だろうと誰だろうと、あたしから孝明君を奪おうとする人は許せないっ。そんなことになったら、あたし、そいつを殺してやるうっ』
おーおー。どこもかしこも、最近は恋愛も命懸けだあ――って、思ったところで、半分微笑ましく、この痴話ゲンカを聞いてたあたしの頭ン中で、なにかが弾けた。
まさか、でも、そう、そうなのよ。ここから聞こえてくるのは、男女の会話。けど、この女子寮にいるのは、男の孝明の方。あたしたち、とんでもない勘違いをしてたんじゃ。「孝明っ」あたし、バスルームの扉を、力任せに開け放って「わかった、わかったわっ」
「な、なんだよあねき」と、便器に座ってた孝明は目を丸くして「あ、そのラジオっ。オレの電話、聞いてやがったなっ」
「ンなことより、聞いて。最初っから、コードレス・ガールなんていなかったのよ。あたしたち、ここが女子寮だから、当然電話してる女のコの方がここの住人だと思い込んでたけど、それが、男の方だったとしたら――」
興奮のあまり、あたしはラジオを床に落としちゃった。と、そこから流れてきた、この声。『もしもし? あ、ヒロミか? オレオレ。先週の話だけど、どうなった――』
バラバラだったいろんなことが、一つの像となって、あたしの頭に閃いた。連続土曜日盗難事件。毎週実家に帰る遠藤さん。留守の彼女の部屋には、コードレスホンがある!
あたし、サンダル引っ掛け、廊下に飛び出してた。走って廊下の角を曲がり、遠藤さんの部屋の前へ。別に確信があったわけじゃないけど、なんかピンとくるもんがあったの。
「こら、あんた、そこにいるのはわかってンのよっ」ドアをドンドン、手が痛くなるくらい叩いてやった。「観念して、もう出てきなさいっ」
ノブを回す、と、扉は簡単に開いちゃった。どういうこと? 一歩、暗い室内に足を踏み入れるあたし――と、突然、誰かが後ろから飛び掛かってきたの。
「ひ、ひえっ」
男の体臭。背後から首に腕を回され、あたしにはなすすべもなかった。ぎらっと光ってるのは、ナイフ? 部屋の床には、コードレスホンが転がってる。カンは当たってたんだ。けど、あたしったら、なんちゅー失態っ。「よくオレが、ここに潜入してるのがわかったな」男は押し殺した声で「気づかれたのならしょうがない。ただでは帰さ、ぐっ」
なんか知らないけど、一声呻いて、男の腕の力が抜けた。とっさに逃げたあたしが振り向くと、そこには、ファイティング・ポーズで立ってる孝明が。
「このガキ、不意打ち食らわしやがって」
って男が後頭部を押さえて立ち上がったところに、孝明の拳は、さらに二発、三発。大きな口とは裏腹に、男は泡吹いて倒れちゃった。我が弟ながら、カッコイイっ。
「あねき、大丈夫か、ケガないか?」
「ないない、孝明、見っ直したァ」
物音を聞きつけて、寮のみんなが何事かと覗きにやってきた中、あたし、孝明に抱きついちゃった。
* *
「遠藤さんは、自分の部屋は三階だからと思って、いつも窓の鍵をしめてなかったのね」あたしは紅茶を一口飲んで「でもあたしたちの寮は、屋上に繋がった梯子を伝って、窓から忍び込むの、そう難しくないから――」
「なーる。で、その連続土曜日盗難事件の犯人は、何度か寮に忍び込んでるうちに、週末は彼女の部屋が必ず留守になることを知って、そこに潜伏するようになったわけか」と、宇野裕美さん。「宵の口はそこで待機してて、深夜になったら、行動を起こしてたのね」
「それで、待ってる間、暇こいてた男は、彼女の部屋のコードレスホンで、友達に電話してた、と」と、石井洋美さん。「とんでもない男ねえ……」
ここは喫茶店。迷惑をかけた〝ヒロミ〟の皆さんに、真相を説明してるとこなンだ。
あたしが聞いたあの電話は、あの男が、この寮とは遠く離れたところにいる、女友達のところにかけてたものだったの。文学部のワタナベ・チヅルさんは、同姓同名の別人だったって、こういう笑い【話/オチ】。ほんと、人騒がせよねえ。
でも、怖い目にもあったけど、あたし、ちょっぴり今回の事件に感謝してるんだ。この三人、話してみるといい人で、素敵な友達になれそうなンだもン。
世のお父様方、お母様方。【親元から離れた娘/コードレス・ガール】たち、一見、不真面目なことしてるように見えるかもしれないけど、ほんとはみんな、すっごく自分の人生に真剣なンですよ。危なっかしく見えるだろうけど、暖かく見守ってやって下さいませ。
「それにしても、渡部さんだってやるわよねえ。最近、寮で評判よ」と相田博美さん。「事件のとき抱きついたあの彼氏、みんなで寮長には内緒にしてあげたけど、どういうご関係? 部屋に入れてたんでしょ? むふふ」
「違~うっ。それは大きな誤解よぉ」
思わず叫んでしまった、あたしでした。
(了)