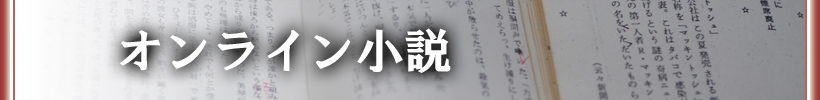オンライン小説
今夜、君の夢を見る
その日は、朝から景色を乳白色に染める、醒めきった心の中にまで滲みこんでくるような、細かい雨が降り続けていた。
ただSFを書く作家だというだけで、大学祭のシンポジウムで、コンピュータ教育をディスカッションするなど、気恥ずかしいというより、コメディに近い。駅を下り、キャンパスの門へ吸い込まれていく色とりどりの傘の中にまぎれながら、ふとそう思う。やたらくだらないトリックで人を殺しまくり、嬉々としているミステリー作家が、警察の現場に顔をだすようなものではないか。嘲笑が聞こえるようだ。――ねえ、ワトソン君。虚構と現実は違うのだよ。君の夢物語につきあっている時間はないのだ。
夢が現実と掛け離れていることぐらい、今の僕は十分過ぎるほど承知している。少なくとも、今自分が身を置いている世界が、昔、夢見ていたそれと全く同じかと言われれば、首を縦に振ることはあるまい。夢は見るためにあるのであって、叶えるためにあるのではないのだ。夢にも五月病というものがあるのなら、僕は確かにその病に冒されていた。
キャンパスの中は、生憎の雨ということもあって、お世辞にも活況とは言えなかった。模擬店の呼び声がいくぶん自棄気味にも聞こえる。もっともそう感じるのは、大学を辞めまっとうな道から外れた者が、前途洋々たる大学生に持つ妬ましさからかもしれない。彼らの笑い声は雨に湿気てはいないのだから。今の若者は夢を見ないとオトナは言う。そんなことがあるものか。それとも今のオトナは彼ら以上に夢を見ているというのか。今の僕には彼らが眩し過ぎる。
ふと、君のことを想う。昔、僕も君のことを夢みた季節があった。今、君はどうしているのだろう。共に過ごした短い時間の中で、夢を見るなんて虚しいだけ、と囁いた君。それから醒めたとき悲しいだけ、と呟いた君。僕はそんな君に、夢を見させてあげたいと願っていた。今、彼らを見る僕の目は、あのときの君の瞳と同じ色をしているのかもしれない。
校内の廊下はじっとりと湿っていた。案内された控え室のパイプ椅子に座り、所在なく傘の雫で床にいたずら書きをする。僕の書いた物を高校の頃から読んでくれていた、このシンポジウムに僕をひっぱりだした張本人である女子学生が、お茶を淹れてくれた。彼女は否定するが、あいかわらず雨女であるらしい。
パネル・ディスカッションのテーマは、コンピュータ教育――CAI――に関しての、コンピュータ導入の利点と危険性というものであった。まばらに人が入った文学部の教室に案内され、壇上の席に腰を下ろす。僕の他には、この大学の工学部で教鞭を取っているK教授と、県の教育センターで実際にCAIを研究しているというY氏が顔を揃えており、現実を知りに知り抜いている二人は、実に快調に意見を飛ばし始めた。
「僕はCAIには希望を抱いてはいませんが――」
「コンピュータはあくまでも教育の効果を高める道具のひとつで――」
「先生よりコンピュータの方がいいと言われるようでは教育者として失格ですし――」
さまざまな言葉が僕の回りで交錯し、通り過ぎていく。それらはあまりに現実的であるが故に僕にとっては非現実そのものでしかなく、ただ、言葉としての意味しか持たないディスカッションではあった。SF作家が口を挟めるほどCAIは非現実ではないし、同時にトリックスターとなれるほど現実的ではない。なにより教育に失望して教育学部を中退した人間が、教育を云々するのは居心地が悪過ぎる。
大部分の“教育者”が考えている“教育”などは、彼らが考えているほど重要でもないし、本質的なものでもない。僕はそう思っている。教育とは何が正しいのかを見極める力を授ける術であって、“正しいこと”を擦り込む手段ではない。果たして今の教師たちは答えられるのか。なぜ生徒がバイクに乗ってはいけないのか、なぜパーマをかけてはいけないのか、なぜ修学旅行にドライヤーを持っていってはいけないのか。それが“正しくないこと”だからなどと答える教師は全員死んでしまうがいい。あなたたちが生徒に“正しいこと”を見極める力を授け、同時にそれが真に“正しくないこと”であるとすれば、あなたの生徒たちがあなたを裏切るものか。
願わくば、これから教職を目指し子供たちを育まんと意欲に燃える者たちよ。このことを忘れないでほしい。戦争はいけないと教える教師は、戦争はいいものだと教える教師と、なんら変わるところがないのだということを。子供の心は教師の黒板ではないのだ。
その点において、僕は現在の教育に失望していたし、負け犬でもあった。コンピュータ教育が将来、どのようなものになって、どのように使われていくのか、僕の知るところではないが、それは所詮、“学習”の分野に属することであり、“教育”を変える力になるとは考え難い。だとすれば、負け犬がせめてもの捨て台詞を吐き捨てられる範疇でもなさそうだ。
外ではあいかわらずの細雨が降り続いている。他にすることもなく、幾分いいかげんに相槌を打つ僕を蚊帳の外に、Y氏とK教授の意見はそれぞれ微妙な擦れ違いを見せながらも、予定調和のように歩み寄り始めていた。もっとも、この二人は、コンピュータに何の夢も幻想も抱いていないという点では、確かに最初から同志同士ではあったが。そしてこの点においても、僕はやはり埒外であった。
出席者としては実に無責任な言い草だが、明確な結論を導きだすというよりも、ただ提起されるべき問題をまとめあげただけという印象を残して、ディスカッションの幕は引かれた。企画したスタッフには不本意な結果であったかもしれない。三々五々教室を去っていく人々を横目に、我々三人も控え室に戻った。その途中、未だ言葉足りぬといった体のY氏は僕に向かい、作家のあなたがCAIの現場を知らないのは当然だと言い、もし興味があるのならセンターに見学に来ると良いと熱っぽく勧めてくれた。Y氏のCAIに傾ける情熱には感心するばかりだ。
今まで人気の失せていた控え室の中は、湿った空気が淀んでいた。出る前に僕が傘の水滴で書いていた文字が、タイルの上に流れながらも残っている。ここで少し待っていて下さいという女子学生の言葉に従って、僕らは別に決められた訳でもないのに、それぞれ自分が前に座っていた椅子に当然のように腰を下ろした。Y氏はまだCAIの未来について語り続けている。矛先が向けられたK教授は、やや困惑気味だ。
ふと、部屋の中に一瞬の静寂が割り込んできた。どんなに話が弾んでいても、波が引いていくように会話の糸が途切れてしまうときがある。初対面の知らぬ者同士であればなおさらだろう。ちょうど今がそのようなときであった。一度沈黙のフィルターに濾過されてしまった話題は、そう易々と続けられるものではない。僕ら三人は三人とも、脆い結びつきを凍えさせる沈黙に目を伏せて、互いに他の二人を責めるかのように口を堅く閉じ、新しい潮が訪れるのを待った。
このようなとき、何より武器となってくれるのが煙草である。嫌煙権を唱える人々は、沈黙に痛みを感じない鈍い感受性の持ち主か、あるいは被虐症なのであろう。だがその頃僕は一時の気まぐれで煙草をやめていたし、被嗜症でもなかった。
最初に白旗を挙げたのは、他ならぬ僕であった。顔を上げ、小さく咳き込んだ途端、他の二人は命綱でも引き寄せるかのように、視線を僕に絡めてくる。僕は言われのない義務感に襲われ、つまずき枯れた声で喋り始めていた。
「K先生はコンピュータの専門家でいらっしゃる訳ですから、僕は素人としてお訊ねする訳ですけれども――」僕は自分で自分が何を話しているのか、よくわかっていなかった。しかし考えるよりも一歩早く、言葉の一句一句が、まるでシナリオに書かれているかのような正確さで口をついていた。「もちろん現在のコンピュータがそこまで到達していないことは承知していますから、あくまで未来の話になりますが、コンピュータは将来――夢を見るようになれるでしょうか?」
この小さな空間の中に、風が吹いたような気がした。と共に夾雑な音が掻き消されていった。しかしそれは沈黙ではない。名指しされたK教授もY氏も、僕の言ったことが理解できず、きょとんとしているだけだ。僕は後に続ける言葉を探しながら、その昔、確かにこれと同じ光景を見たことがあるという強迫的な既視感に囚われていた。
K教授は目の端で僕を捉えながら、訊ね返してきた。「夢を見る、というのは?」
「つまり――、コンピュータが人間と同じになれるかということなんです」この言葉はあまりに舌足らずであり過ぎるようだ。K教授は眉を寄せている。二、三、補足せねばなるまい。「SFには珍しくない話ですし、SF作家は割と何も考えずそういったことを書いてしまうものなんですが、“意識を持ったコンピュータ”のことをお訊ねしたいんです。実際の話――コンピュータが自我や意識を持つ可能性はあるんですか?」
「ふふん――」K教授は鼻で相槌を打つ僅かな時間だけで、見事な答えを用意していた。「まず、ありませんね」
「……しかし、ですよ。人間の脳もつきつめて言えば、神経細胞などの物質的構造で構成されているものですし、その精神現象が脳内の電気信号や伝達物質の動作によって起こっているというのは、現在の脳科学ではまず一致した見解ですよね?」別に絡むつもりはなかった。ただこのツンと澄ました【教授先生/タイトルホルダー】に、“ちょいと一発”かましてやりたかっただけだ。「ならば、我々の脳がファンタジックな霊的現象で成り立っているのではない以上、そのロジックをコンピュータ上で再現することも可能なのではないですか?」
「確かに、意識が宿るのは脳であって、魂ではありませんが――」哲学に退路を見出さないところは、K教授もさすがであった。どのような分野においても、精神論を持ち出す者はすでに敗残兵である。「しかし脳と現在のコンピュータとでは、根本的な原理が違うのですよ。我々の脳が並列処理を行い【あいまい/ファジー】な作動原理を持ちうるのに対し、今日の人工知能はブール代数の範疇にある対象しか扱えないんです。ありていに言ってしまえば、コンピュータは問題解決の方法をあらかじめ教えておいてやらないと答えを弾きだせない――自分でものを考えるようなことはできないんです」
K教授は僕をズブの素人とみて、こんなナメた返事を返してきたのであろうか。虚構を創造することを因果としている以上、僕は現実がどの程度のものかを知ることにやぶさかではないつもりだ。
「でもそれは、現在大部分を占めるノイマン型コンピュータではの話でしょう。最近脚光を浴びている、人の脳のように素子を並列処理したニューロコンピュータならば、ファジーな制御もできるでしょうし、先生のおっしゃる否定的な要素をクリアできるのではないですか?」
「ふふん――」
まるで、懸命に吠えかけてくる子犬を眺めるような目で僕を見ているK教授の素振りに、僕は一層依怙地になっていった。
「現在のニューロコンピュータは我々の脳に比べれば余りに単純過ぎるでしょうが、根本的な原理としては、我々の脳の雛形に近いそうですね。我々の脳が複雑かつ高度な、しかし所詮は思考する【機械/マシン】である以上、いつかはチューリング・テストをクリアできるコンピュータも造ることができると思うのですが」
Y氏が興味深けに口をはさんできた。「チューリング・テストというのは?」
「チューリング・テストというのは、例えば僕の頭の中にあるのが脳味噌ではなくコンピュータだとして、僕と話しているあなたがそれと気づかない場合は、そのコンピュータには自我があると考えられるというものです」
「その場合でも、自我があるというのはどうだろうね」K教授が今までになく、強い語調で言った。「自我があるかのように振る舞う、ということ、自我がある、というのは別のことだよ」
「それは確かに――その通りです」
「僕はね、どのようなメカニズムだろうとシステムだろうと、それがマシンとしての脳を複製している限りでは、自我も意識も芽生えないだろうと思うね。最初の君の質問に戻れば、そんな存在が夢など見るはずもない。そう――そういう意味では、【人間の脳すらも/傍点】例外ではないんだよ。なぜなら――」
「なぜなら?」
K教授は、悪戯っぽい笑みを浮かべていた。「君の思い出は、君だけのものだろう?」
正直言って、僕はこのとき、K教授の言ったことがわからなかった。理解できなかったわけではない。人間の脳はファジーなことも理解できるのだから、僕のそれも例外ではないはずだ。僕の思い出は、僕だけのもの? それは、確かにその通りだ……
「コンピュータというのはね、田所クン――」僕の名を呼び、覗き込むように、そして諭すように、K教授はゆっくりと言った。「産まれたときから、オトナなんですよ」
その一言で十分であった。すべて劇中のような、重さというものが失せた世界の中に、僕の目の前で優しく微笑むK教授のその一言だけが、僕に割り振られた、しかし舞台の上で忘れてしまっていた台詞のように重く残っていた。コンピュータは産まれたときからオトナ? そうか、オトナだから夢など見ないのか。君が――君がそうだったように?
不意に視界が白く消えた。そこに、僕が失っていたヒロインの淋しげな輪郭があった。長い髪をゆっくりとかきあげると、その余りに大きい瞳に浮かんだ涙を、左目の小さなほくろの脇から落とし、君は、誰にともなく、呟いた。それは、いつか僕が聞いた言葉だ。「ねえ、もっとオトナになってよ、タカシ――」
気がつくと、僕は傘を広げ、帰りの道を歩いていた。幾人もの人々が、大きな傘を持つ僕をうさんくさげに追い抜いていく。石畳の上の水溜まりは、ゆっくりと揺らぎながら空を映し込んでいた。十一月の雨雲は過ぎていったようだ。
そう。あの季節、君は確かにオトナ過ぎたし、僕はコドモ過ぎた。僕は夢の話ばかりしていたし、君はいつも溜息ばかりついていた。だが、誰しもがいつかは、現実に揺さぶられてオトナになる。今の僕がここにいるように。スーツを着た僕の友達が、自嘲と共に灰色の世界に身を投じていったように。それでも――それでも僕は夢を見ていたい。夢を、見ていたい。ねえ、今の僕にはわかるよ。本当は、君の見ていた夢は――
名を呼ばれ、振り返る。白く煙る景色の中に、まるで薄い水彩で描いたような、希薄な君が佇んでいた。病的に痩せた体に、あの日と同じ、男物のシャツにストーンウォシュ。そして唯一お洒落な水玉の傘。
君の唇が動いた。僕は歩み寄る。君は、淡く、淡く、消えていく。ショウ・ウィンドウに映る、過ぎ去っていく人々の影、流れに取り残された黒い傘。それは一人、今来た道を見つめ、ただ立ち尽くす、僕の姿。
いいだろう、美里。君のために、僕は夢を語ろう。
今夜、僕は、君の夢を見る。
(了)