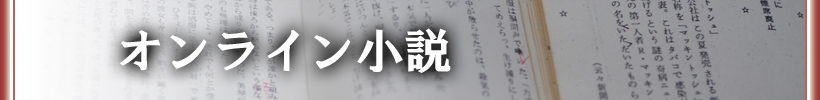オンライン小説
●第1章
絶句した。チボリウムの蓋を開けて、ヨゼ神父は。
シンと静まりかえったお聖堂の中で、火曜日のミサは粛々と進められていた。聖変化も終わり、平和の挨拶もすみ、平和の賛歌が唱えられる直前である。
チボリウムというのは、ご聖体が入った器のことで、聖体拝領直前までは、祭壇中央のご聖櫃の中に納められている。中には前のミサで聖変化させたご聖体が数十枚くらい入っているのが普通だ。
それが今日も一枚。たった一枚しか入っていなかったのである。そう、先週の火曜日に引き続いて、またしても。
ヨゼ神父は、ひょっとしたら自分の視力がどうかしてしまったのではないかと、光を見ることができる唯一の右目を瞬いて、もう一度しっかりとチボリウムの底をのぞきこんでみたが、そこにはやはり、ただ一枚のご聖体があるばかりであった。
「神の小羊――」先唱を務めているなじみの女性信徒が式文を唱え、数人の会衆がそれに応える。「世の罪を除きたもう主よ、われらを憐れみたまえ」
先週に同じことが起こったときは、きっと、自分のミスが招いた結果だろうと思っていた。日曜主日に十分な数のご聖体を作ることができず、四旬節の忙しさの中、病人を見舞う聖体奉仕者などにも分け与えた結果、チボリウムの中に一枚だけ残してご聖櫃に戻し、火曜日に今週分のご聖体をまとめて作ろうと思っていたのを、自分がすっかり忘れていたのだろう、と。
とにかく、一年前のあの事件以来、自分はどうかしてしまっている。左目と左手の小指を失った代償は小さくはなかったが、なにより毎日、頭に霞がかかったようで忘れっぽくなり、日々の教会行事を秘書役の信徒に手伝ってもらいつつこなしていくので精いっぱいだ。週日ミサに必要なご聖体の数を心にとどめておくような細かい気配りができなかったくらいで驚いたりはしない。
しかし今週は違った。おとといの主日ミサでは十分な数のホスチアを聖変化させたし、チボリウムに納めて、ご聖櫃に入れて鍵を掛けた記憶がきちんと残っている。先週、失敗した分、それは意識して自分が行っていたことをわかっている。
いや、そのようなことは今はいい。問題はこのミサの聖体拝領をどうするか。信徒たちの祈りの声を耳にしながら、ヨゼ神父は混乱した頭の中で、先週、どうしたかを思い出そうとした。確か、ミサ中に聖変化させたばかりの大ホスチアと、チボリウムに残っていた一枚を四つに割って、全部で八枚のご聖体に分けて配ったはずだ。先週は五人程度の信徒だったからそれでも足りた。しかし今日、お聖堂にいる信徒は――七人。自分がいただく分も入れて八枚。なんとかしのげるだろうか? ああ、駄目だ。どうあっても一片はチボリウムに残して聖櫃に戻さねばならない。
「世の罪を除きたもう主よ、われらに平安を与えたまえ――」
平和の賛歌が終わってしまい、またお聖堂に静寂が訪れる。信徒の目が自分に注がれていることを感じ、ヨゼ神父は心を決めた。大ホスチアをいつものミサのように二枚に割り、半分をチボリウムに入れた。
「神の小羊の食卓に招かれた者は幸いです」
呼応して、信徒が唱える。「主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて、誰のところに行きましょう」
ヨゼ神父は、大ホスチア半分のご聖体をいただき、カリスに入ったご聖血を飲み干した。信徒たちは三々五々、中央に集まり列を作っている。
いつもならば、聖体のたくさん入ったチボリウムを持って立つ祭壇の前、内陣の中央に、ヨゼ神父は親指を組み合わせたカトリックの合掌姿で立ち、頭を下げた。
「ごめんなさい。わたしのミスで、今日のご聖体、少なかったです。割ってみなさんにあげられるほどもなくて。今回は、祝福で許してください」
先頭に並んでいた、先唱を務めていた信徒はキョトンとしていたが、すぐに頭を下げて祝福を待った。
ヨゼ神父は右手を彼女の頭に掲げ「あなたに神様の祝福がありますように」
「アーメン」
並ぶ信徒たちに祝福を与えながら、ヨゼ神父は祈った。
主よ、もう十分です。もう、十分です。わたしは耐えられそうにありません、と――。
* *
「すると、先週の火曜日も、神父さまのポカではなく、実はご聖体が盗まれていたというわけですか――」いかつい顔をした壮年の男は、口を富士山のように曲げて言った。「まるで洋画のいちシーンのようですな。〝いいニュースと悪いニュースがある〟という」
「悪いニュースはわかりますが――」こちらは痩せたネクタイ姿、薄いレンズのメガネを掛けた中年の男。「寺内さん、いいニュースの方はなんですか?」
「そりゃ決まってるじゃないですか」寺内はねじ曲げた唇はそのまま、片方の眉を上げて「われらの敬愛するヨゼ神父さまは、ボケちゃあいなかったってことですよ」
司祭館の応接間に座っている信徒それぞれが笑いをこぼした。
四旬節の半ば、平日午前中の勉強会に顔を出すような面々は、すでに信徒歴も長い、互いに知った顔が五名ばかり。
いつもならば、翌週主日――日曜日――に朗読される聖書の読み解きと感想の分かちあいの時間だが、ヨゼ神父は思い切って、ことの次第をすべてこの面々に話して相談してしまおうと決めたのである。
ヨゼ神父の様子を見て、今日の勉強会は信徒会館の会議室ではなく、司祭館の応接間にしようと勧めたのは正解だった、と、笑い声が残る部屋の隅で、コーヒーメーカーからカップに良い香りの液体を注ぎつつ、妻木京子は思った。
教会委員で総務を務めている寺内長太郎は、いつも不機嫌そうな顔をしているが、その心根は表情とは裏腹に気遣いができるタイプであることは承知している。しかしいつも喧々囂々の教会委員会会議を開いている会議室だと、寺内がセンシティブな情感よりも、問題解決の討論を優先しかねない、と、ミサ閉祭から勉強会までの短い時間に、勉強会の世話役を務めている彼女は、そう、計算したのだった。
実際、コーヒーの良い香りが、ヨゼ神父を含めた六人の表情を和らげているようである。
「まとめてみましょう」痩体にネクタイの男は、メガネをクイと指で上げてから、メモを取っていたシステム手帳の最後に、万年筆で読点を打ち「まず先週の火曜日――」
「その前に、みなさん、ちょっと一息入れましょう。多田井さん、どうぞ」
「ありがとうございます」多田井は万年筆のキャップを閉め、妻木からコーヒーカップを受け取った。
彼はプロテスタントからの〝帰正者〟である。元プロテスタントにありがちな理論派。冷静で、なにかコトを解決するときは頼りになる男だが、今はまず、ヨゼ神父の心情を分かちあうことが第一だ、と妻木は思っていた。
それでなくても、男性というのはストレートに物事を解決に導きたがる。ここは教会で、われわれはキリスト信者、ただでさえ不合理な〝復活〟や〝奇跡〟を信じる者の集まりなのである。男性的な論理優先は少し遠慮してもらわなければ。
妻木が心配しているのは、ヨゼ神父の心の傷が、決して癒えていないことを承知していたからだった。あの事件で、神父さまは自らの左目と左手の小指を犠牲にして、信者ひとりの命を守ることができた。しかし――これは結果論で、誰もヨゼ神父のせいではないと承知しているが――その信者は数ヶ月後、自ら命を絶ってしまったのである。
ヨゼ神父にとって、失った左目や指のことなどは些細なことで、信者ひとりの命を本当の意味で守りきれなかったという心の傷の方こそがまだ塞がっておらず、未だジクジクと血が膿み滲んでいることを、勉強会の世話役で毎週顔を合わす妻木はわかっていた。
この応接間にいる残りの信徒は。去年洗礼を受けたばかりの、いかにも〝若奥様〟な溌剌としたムードメーカーの安村と、もうひとりは信徒歴の長い、足の悪い年輩の女性、小橋である。この二人は安心だ。ヨゼ神父を心ならずも傷つけるようなタイプではない。
多田井は、誰が見ても「それは入れすぎ」と思うほど大量の砂糖をコーヒーに混ぜ、かき混ぜて、一口。
「良かったらお菓子もどうぞ。多田井さん」
と、ヨゼ神父がテーブル真ん中に置かれたチョコレート菓子を勧めると、彼は大真面目な顔で「神父さま、誘惑は勘弁してください。四旬節なので、大好きな甘いものを断っているんです」
「え、でも」と、安村。「さっきお砂糖いっぱい入れてたじゃないですか」
一同の間に、また笑いが巻き起こった。あの仏頂面の寺内も、クックと顔がゆがむのを抑えている。
ヨゼ神父の眉間から皺が数本消えたのを見て、妻木は神と多田井に感謝した。多田井は堅物だが、同時にここぞというときにはユーモアを発揮することを厭わないことを知っていた。きっと、自分が道化になって、場を和ませてくれたのだ。
「では多田井さん」と、ヨゼ神父。「さっきの話、まとめてください」
「承知しました」多田井はシステム手帳のページをめくり、端正に万年筆で書かれた文字を、適度に要約しながら読み始めた。「まず、先々週の主日ですが、ヨゼ神父さまは聖変化でいつものように、一週間分に十分な量のご聖体を作り、チボリウムに入れて聖櫃にお入れになったと考えていらっしゃいました。ところが月曜日の休日を挟んで、火曜日の週日ミサで、聖櫃から取り出したチボリウムには、小ホスチア一枚しか入っていなかった、と」
「正確にはホスチアではなくご聖体だよ。聖変化後だからね」と、寺内。
「もちろんです」と多田井は小さくうなずき「話をわかりやすくするために大小ホスチアという言い方で許してください。大聖体、小聖体と呼ぶ方がおかしいでしょう?」
「まあ、そりゃそうだな。先週みたいのじゃ〝聖体のかけら〟と呼ばにゃならん」
カトリック教会のミサでは、ホスチアと呼ばれる、丸いウエハースのような〝種なしパン〟を、ミサ中に〝聖変化〟させる。その結果、ただの種なしパンであったホスチアは本物の〝キリストの体〟になる。キリストを象徴したものや、宗教的なシンボルではなく、本当に本物の〝キリストの体〟になる、というのがカトリックの信仰である。
信徒は列を作って、司祭や整体奉仕者からそれを手にいただくと、食べる。カトリック教会の〝ご本尊〟は、食べて信者が自らの血肉とすることで完成するのである。
「聖体の大小と尊さが比例するわけではありません。わたしはプロテスタントからの帰正者ですからね。そのあたり、寺内さんより実はこだわりがあるかもしれませんよ」
「あんたがよく勉強してることはわかってるよ」と、寺内は大きな肩をすくめ「さっきのは茶化したわけじゃないんだ」
「でも、ごミサで、神父さまがお持ちになられてた大ホスチアのかけらをいただくと、正直、嬉しいですよね」と、安村。
「それもわからなくはないですね」多田井はあくまで真面目に応える。「【聖餐/コミュニオン】の意味は、主の食卓を皆で囲みその血と体を分け与えられるということですから。わたしも大ホスチアのかけらをいただくと嬉しいですよ」
「問題は――」寺内はまた唇をねじ曲げて、仏頂面を作り「その大切な主のお体が盗まれてたかもしれないってことだろう?」
「先を急ぎすぎです。まとめを続けさせてください」多田井は甘いコーヒーを一口。「先週の火曜日、チボリウムに一枚しかご聖体が残っていなかったことを、ヨゼ神父さまは、ご自分がなにかミスをしたのだろうと思って、特に問題にはしませんでした。聖体拝領は大ホスチアと小ホスチアを割って五人で分け、チボリウムには一片のご聖体を戻し、水曜日の週日ミサで土曜日までの十分なご聖体を作ることで、ことは終わったかに見えました」
コーヒーポットを片付けた妻木も席につき、多田井のまとめに聞き入る。
「そしておとといの主日」〝主日〟とは日曜日のことである。「先週のこともあったので、神父さまはチボリウムに十分な量のご聖体が入っていることを確認した上で、ご聖櫃に入れました。みなさんご存じのように、芝浦教会は月曜日、週日ミサをお休みしています。明けて今日の火曜日、神父さまが大ホスチアの聖変化を終えたあとに、ご聖櫃からチボリウムを出してみると、中には小ホスチアが一枚しか入っていませんでした」
「涙を流すマリア像ってのはあるけど、ご聖体をいただいちまう聖櫃ってのは聞いたことがねえなぁ」と寺内。が、誰も笑わないので、頭をかき「いや、すまん。茶化しちまうのは俺の悪いくせだ」
「もしそうなら――」と安村。のんびりとした口調で「秋田のマリアさまみたいに、奇跡認定されますかねぇ」
「されませんね。ああいうのとは違います」と、多田井は言葉を選び「それに、秋田のあれは教区司教の奇跡認定であって、バチカンが正式に認めた奇跡じゃないんです」
「そうなんだ。残念ですねぇ」
「今日も、小さく分ければ、ご聖体拝領、できました」
ヨゼ神父は申しわけなさげに言う。
スペインに本部を置くマルキエル宣教会の神学生として日本を訪れたとき、〝ヨゼ神学生〟はもう四十を越えていた。それまでは父の事業を継ぎ、貿易商として第一線で活躍していたが、その父が急逝したのが契機だった。
子どもの頃からの夢だった神学の道、それも日本で司祭になりたいという突拍子もない告白を、母と弟妹にしたとき、彼らは顔を見合わせて「ずっと結婚を拒んできたあなたは、同性愛者かもしれないと心配していたの」と言ったものだった。まだ世界は、そういう時代であった。
マルキエル会の神学校へと入学した遅咲きの神の【僕/しもべ】は、いろいろと問題も起こしたが、総長の理解もあり、夢だった日本へと、マルキエル会としては初の神学生として派遣された。司祭ではなく神学生を日本に送るのは、マルキエル会としては初めてのケースだった。それだけ、ヨゼ神学生の日本に掛ける情熱が大きかったのである。
来日してからは、いろいろな教派の宣教師がともに学ぶ日本語学校で苦労して日本語を習得し、さらに日本の大神学校で神学を履修。同時にいくつかの教区教会を神学生として周りながら勉強の日々。そして東京大司教区で助祭叙階。一年後、本国で司祭叙階後、正式に宣教師として再び日本の地を踏み、カトリック東京大司教区から芝浦教会の助任司祭として任命されたのが六年前のことである。経験を積み、前主任司祭のスペイン帰国を受けて主任司祭となったのが二年前。かれこれ十年は日本語を勉強し、日常会話はほぼ問題なくできるレベルではあるが、まだまだ流暢とは言いがたい。
マルキエル会は歴史こそあるものの、とても規模の小さい宣教会である。それでも戦後のキリスト教ブームのとき、この地方都市の外れの芝浦に唯一の教会を建てた。それがこの〝カトリック芝浦教会〟である。
外国の宣教会が建てた教会であっても、日本においてはその地域の教区に組み込まれ、司祭人事もその教区の司教によって配置される。しかしもちろん、そのバックグラウンドは強く反映されるので、日本に一名しかいないマルキエル会司祭のヨゼ神父が芝浦教会の主任司祭となるのは、教区にとっても、所属信徒にとっても自然なことであった。
カトリック司祭としては生え抜きではないが、社会人としての生活も長かった分、ヨゼ神父はバランスの取れた暖かい司牧をむねとしていた。それが気に食わず、他の小教区へと移る信徒もいなかったわけではないが、それが許されるのもカトリックである。
「ご聖体を割っていくと――」ヨゼ神父は、指先で小さなかけらを持つ格好をして見せ「こんなに小さなものになってしまいます。あまり、よくありませんね。それは」
「まとめは以上です。わたしも神父さまの今回のご判断を支持します」と、多田井。「大小でご聖体の尊さが変わるわけではありませんが、同時にご聖体は〝食べ物〟である必要があります。いろいろな説がありますが、わたしは〝噛む〟ことが食べ物であることを表現していると思うんです」
「飲み込める程度の大きさじゃ駄目ってことだな」寺内はうんうんとうなずき「昔はそれこそ、尊いものだから噛んだりせず、丸のみしろなんていう親父もいたな」
「それはナンセンスでしょう。カトリック協議会も、例えば病人に聖体拝領をするとき、砕いてなにかに溶かして飲ませるようなことは意味がない、と言っていたような記憶があります」
「あの小さなご聖体のサイズにも、いろいろ意味があるんですねぇ」安村が言うと、場がのんびりとしてくる。「厚いのや薄いの、しけってるのもありますよね。パリッとしてると、あ、今日のはおいしい、とか」
あっ、言っちゃった。というふうに、彼女は手を口に当てた。
苦笑が満ちる。この応接間に、ヨゼ神父を気遣う空気が流れていることを、妻木は嬉しく思った。
が、強面の寺内は、また口をへの字に曲げて腕組みをし「しかしこれは問題だよ。要するに、泥棒が入ったってことだろう? 犯人が誰だかはわからんが、われわれにとって大切なご聖体を、煎餅みたいにバリバリ食っちまった不逞のやからがお聖堂に侵入してたってことだ」
「まぁ、泥棒はねぇ……」と、小橋。「教会にはつきものですよね」
「そうなんですかぁ?」
「前に夜、香部屋に泥棒が入っちゃって――」と妻木は口を挟んだ。「冷蔵庫に入ってたミサワインを全部飲まれちゃったことがあるのよ」
「わたしが以前いたプロテスタント教会も、何度か被害にあってますよ。まあ大したものは盗まれませんでしたが。銀の燭台もありませんでしたし」
「世の中には頭のいい悪いやつがいるもんでさ」寺内は眉間に皺まで寄せ始めた。「各教会のミサの時間を調べて、その時間に司祭館に盗みに入ってたって泥棒もいたぐらいだ。ミサ中の司祭館には誰もいないことが多いからな」
「教会なら盗んでも許されると思ってるんですかねぇ」
実際、この芝浦教会だけでも、妻木の知る限り、数回の空き巣、盗難被害に遭っているのだった。一回は司祭館のヨゼ神父のデスクから、十万円ほどが盗まれていたことも知っている。〝知っている〟というのは、ヨゼ神父はそれを警察に届けず、ほとんどの信徒が事件そのものすら気づかなかったからだ。内部犯行なのか、外から忍び込まれたのか、それすらもヨゼ神父は「まあ、こういうこともありますね」と笑って済ましてしまったのである。
「とにかく、これは警察に連絡だよ」フンッ、と寺内は鼻息を荒くして「ミサワイン事件のとき、警察に言われたろう。お聖堂や香部屋に施錠してなかったから、事件として扱うのは難しいってさ。あれを教訓に教会委員で、夕方から朝まで、香部屋とお聖堂自体の鍵を掛けると決めたんだ。自由なご聖体訪問ができなくなるという反対意見を言う連中を宥めたのは俺なんだぜ。今回は警察だって取り合ってくれるだろうさ」
指を組んで、長いため息をついたヨゼ神父の様子を、妻木は痛々しい気持ちで目の端に入れていた。カトリック教会の小教区の意思決定は、すべて主任司祭の一存である。ヨゼ神父が大事にしたくないという気持ちを持っていることは明らかだ。
「警察に通報するにしても、どう説明したものかっていうところもありますよね……」妻木は語尾を小さくごまかしつつ「そもそも、ご聖体がどれだけわたしたちにとって大切なものかってのをわかってもらえるかどうか。金銭的な価値としてはほぼゼロ円なんですから」
「だからって、犯罪行為を見逃していいってことにゃならんだろう?」寺内は今にも拳でテーブルを叩きそうな勢いだ。「しかも二回目となったら、こりゃ舐められてるよ、犯人に」
「――しかしわれわれの置かれている事態は、週の初めの日に、マグダラのマリアがイエス様の墓に行ったときよりも、まだ、ましではないですか?」
多田井の言葉に、皆、キョトンとした。プロテスタントと比べて、カトリックは聖書を読むことを励行しない。それを承知の上の多田井の謎かけである。
さすがにヨゼ神父はすぐに意味を解した。「ヨハネの二十章ですね。せっかくですから、少し勉強会らしいことをしましょう。妻木さん、読んでください」
「はい。ヨハネ福音書の二十章ですね――」彼女は手元の自分の聖書を広げ、該当箇所を朗読した。「『週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た。そこで、シモン・ペトロのところへ、また、イエスが愛しておられたもうひとりの弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちにはわかりません』」
妻木が一息入れたところで、多田井が切った。「どうですか?」
「意味がわかんねぇな。どうして俺らの方がこれよりましなんだい?」んっ? と、寺内は言葉を飲み込んだ。がらっぱちではあるが、頭の回転が遅いわけではない男である。「なるほど。俺らの場合、チボリウムに最後の一枚は必ず残ってたってことか」
「そうです。そして、聖体ランプもつきっぱなしだった」多田井は深くうなずき「これは、忍び込んで酔っ払うためにミサワインを飲んだような、ただの泥棒じゃない。ちゃんと、ご聖体がキリストの体だと承知した上での行いです」
「うむ……。ただの泥棒がおつまみにするなら、一枚だけ残していく理由はねぇわな」
一同は沈黙した。多田井の指摘はもっともだった。
寺内は腕を組み、上体を大きくそらして、呻いた。「内部犯行、か……」
「え、え?」と、空気を読まない安村が「どういうことですか?」
「聖櫃の鍵が香部屋の吊り戸棚、それも特定の位置に置いてあることは、ある程度、典礼奉仕をしているものならば誰でも知っています」多田井は丁寧に説明した。「むしろ、小銭やミサワインを目的に忍び込むような泥棒が、聖櫃の鍵を見つけても、それがどこに使われる鍵かすらわからないでしょう。よしんば聖櫃を開けたとしても、一枚だけ残して食べる方が不自然です。つまり犯人は、この教会の所属信徒で――」
「かつ、そこそこ典礼奉仕の現場を知っている者、だな」むぅ、と寺内は鼻息をひとつ。「内部犯行となると、警察ってわけにはいかないか――」
一番、強硬姿勢を貫きそうな寺内が折れたことに、妻木はホッとした。ヨゼ神父のためにも、ここは穏便に――
「いやしかし、逆に、なかったことにはできねぇなぁ。むしろ犯人は確実に捕まえて、とっちめてやらねぇと」
気づかれないよう、ため息をひとつ落とす妻木である。ヨゼ神父は困ったような表情を浮かべたまま、なにも言わないでいる。彼は、信徒からの意見が出尽くすのを待って、結論を出すタイプの司祭だった。
妻木はかぶりを振り「それにしても、たくさんのご聖体を盗んだりして、はんに……その人はなにをしたかったんでしょうね?」
松村、寺内、小橋、それに言った妻木自身も、お互い顔を見合わせている様子を眺めて、多田井は、緩やかな苦笑を浮かべて、言った。
「みなさんは、カトリック一筋だから、わからないというところもあるかもしれませんね」
「元プロテスタントのあんたならわかるんかい?」
「わたしはいくつかの教会を渡り歩きましたからね。褒められたことではないですが――中にはね、本気でオカルティックなことを信じている教会もあるんですよ。例えば〝サタン〟ですよね」〝サタン〟とは、聖書中にも書かれている言葉だが、一般人がとらえている「悪魔」というイメージよりも〝誹謗中傷する者〟という方が本来の意味に近い。最近のカトリック教会では〝サタン〟という言葉自体を使うことがほとんどなくなっている。「なにか悪いことがあると〝サタン〟の仕業、あなたは〝サタン〟にとりつかれている、とかね。それで、そういう教会だと、この世界には〝反キリスト〟もいると信じられているんです」
「反キリスト!?」と、松村が大きな目を見開いて「なんだか、きな臭くなってきましたね」
「というより、うさんくさいな」
「その昔、まだプロテスタントがなかった頃の中世ヨーロッパには、〝サタン〟を信奉する反キリスト者による〝黒ミサ〟が開かれていました」寺内の茶化しを軽くスルーして、多田井は続けた。「〝黒ミサ〟の目的は神への冒涜ですが、特に、盗んできたご聖体への汚辱はありとあらゆる形で行われた、と聞いています。ご聖体を踏みつけ、つばを吐きつけ、赤子の血を浸し、粉々に砕いて汚物に混ぜる」
「おおいやだ」小橋が肩をすぼめて震わせた。
「みなさんは毎週のごミサでご聖体をいただいて食べられる、ということが、普通になってしまっていますからね。逆にご聖体がどれだけ尊いものか、忘れてしまっている、というところもあるのではありませんか?」
妻木はうなずいた。「確かに、現代のカトリック信者にとって、そういうところがないとは言えませんよね。ご聖体をいただけることが当然のようになっているし」
「昔は、ごミサの前の晩から断食し、日曜日は朝からつばも飲まずにご聖体をいただいた、という信者もいたそうですよ」
「えぇー、そこまでするんですか」と、またのんびりと松村。「まあ中には、手じゃなくて直接口へいただく信徒もいらっしゃいますし、そういうの、すごいなあって思いますけど」
「耳に痛い話だが、それはひとまず置いておいて」寺内は、ずい、と身を乗り出した「つまり多田井さんはこう言いたいわけだ。この教会から、汚聖、涜聖のために、ご聖体を盗んだ〝反キリスト〟なやつがいると。そいつの目的は、なんだか知らんが不届きな〝黒ミサ〟のためである、と」
司祭館の窓から、三月の木漏れ日の光が揺れている。鳥が一羽、鳴きながら飛んでいった。こんなありふれた日常の中に、〝反キリスト〟や〝黒ミサ〟という言葉は、コーヒーの中に落ちた小バエのように不釣り合いだ。
ヨゼ神父は小刻みにうなずきながら、全員を見渡した。
「それで、みなさん、どうするのがいいと思いますか? 警察に届けますか?」
「それは――」寺内も全員をぐるりと見て「なしにしましょう。どうですか?」
応接間に、ホッとした空気が流れる。皆の様子を確認してから、寺内は多田井に訊ねた。「汚聖が行われているとして、われわれはどうするのが一番いいだろう? 多田井さん。あんたが一番、知識がありそうだ」
だが多田井は長くため息をついた。「中世ヨーロッパとは違いますからね。魔女狩りができるわけでもないし、現実的には、犯人をつきとめて、事情を聞くしかないでしょう。その結果どうするかは、司牧上の問題で、われわれがどうこういうことではないのかもしれません」
「結局は、犯人を捕まえねぇことには話が進まねぇなぁ。監視カメラでもつけて録画するかね?」
「そこまで大仰にしなくても、手はありますよ。ご聖体がなくなったのは、二週とも、火曜の朝のミサですよね。この芝浦教会では、日曜主日、午後二時からの英語ミサが終わったあと、午後六時頃、お聖堂の鍵を掛けます。そのときに香部屋の鍵も掛けますよね。そして、月曜日はお休みで、聖堂は閉めたままです。ということは」
「そうか」寺内は、右の拳を左の手でパンと受け止めて「犯行時間は日曜の英語ミサが終わってから、聖堂を閉める午後六時までに限られるってことか」
「そうです。その間だけ、どこかに隠れて、監視していればいい」そして、多田井は難しい顔をして「二度あることが三度ある。来週も犯行が行われるならば、ですが」
「いや、こうなったら意地だよ。どうしたって犯人を捕まえてやらにゃ気がすまん。来週だろうが、再来週だろうが、さ」
「寺内さんがそうおっしゃってくださって良かった」多田井にしては、珍しくニヤリ。「問題は、誰がその役目に立候補してくれるか、でしたから」
「え?」寺内は、右を見て、左を見て、合点がいかない顔で、もう一度、全員を見た。そして自分以外の六人の視線が注がれているのに気づき「俺かい?」
ヨゼ神父はにっこりと笑った。「寺内さん。お願いできますか?」
「俺も暇じゃねぇんだけどなぁ」寺内は大仰に嘆息した。「けど仕方ないか。言い出しっぺだ。わかった。やりますよ」
そして、ギロリとにらみをきかせて、一言。「わたしたちの主、イエス・キリストを盗んだやつに、一泡吹かせてやりましょう」
(第2章へ続く)