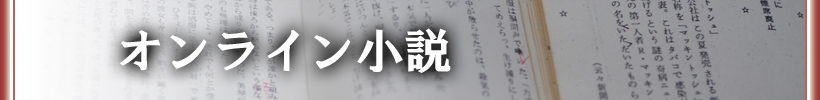オンライン小説
●第2章
師走の陽光に、真っ白い裂け目が一閃する。庇った左手には、痛みより熱さがほとばしっていた。ガン、と左の頭をなにかにぶつけたような衝撃。最初は、頬が裂けたのだと思った。飛び散り流れる鮮血が、顔を覆った両腕の肘から伝って落ちるのがわかる。
最後に左目に写った、真っ白い裂け目が、白刃のそれだったとわかったのは、ヨゼ神父が膝をつき、それでも、相手の腰から下にしがみついてからだった。
「神父さま!」背後から飛ぶ、女性の金切り声さえ、今は背に千の針のマントを掛けられたかのようだ。
「逃げなさい。逃げて。すぐに」
「お、おまえが悪いんだ」ナイフから手を離し、ヨゼ神父を蹴ってどかし、後ずさった男は、顎をわななかせて、震える声で言っていた。「おまえが俺から逃げなければ、こんなことには……」
そして一気に逃げ出したのは、女性の方ではなく、この男の方だった。
何事か、と、教会事務室の窓を開けて、庭を見た妻木は息を飲んだ。が、悲鳴を食いしばる胆力と、事態を理解できる聡明さ、今、するべきことを行える実行力が彼女にはあった。すぐにデスクの電話から受話器を取り上げ、一一九を回す。
「神父さま、ごめんなさい、わたしのせいで、ごめんなさい」ヨゼ神父の背後から駆け寄った女性は、おろおろとするばかりであった。「ごめんなさい、わたしのせいで、ごめんなさい……」
「だ、大丈夫、です」薄れていく意識の中で、ヨゼ神父は思った。そういえば、この言葉は、〝ありがとう〟の次に覚えた日本語だったな、と。「大丈夫です。あなたのせいでない。だいじょう……」
* *
「大丈夫ですか?」
看護婦に肩を触れられ、ヨゼ神父は、ハッと目を覚ました。額にびっしょりと汗をかいていた。
それをぬぐった右手で、左右の目を交互に覆って、左目の視界がまったくないことを確認し、残った右目で、欠けた左手の小指を見る。
すべてが現実だ。
あのとき、頬から左目にかけてえぐられた刃の傷跡は、信徒の伝手でかかった手練れの整形外科医のおかげで、ほとんどわからなくなっているが、失われた左目の視力と、第一関節からちぎれた左手の小指の先は、どうしようもなかった。
どれだけ時間をかけても、治らない傷というものはある。ましてや、心の深い傷跡はなおさらだ。
看護婦に付き添われ、ヨゼ神父は診察室に入った。デスクではなじみの初老の医師が微笑んで待っている。ヨゼ神父もにっこりと相好を崩し、丸椅子に腰を掛けた。
「お待たせしてしまってすみません、神父さま。だいぶお待ちになったのではないですか?」
壁の時計の針は、もう十二時半を回っている。が、ヨゼ神父は首を横に振った。
「最後に回してくれと言ったのはわたしですね。大丈夫。立石病院。商売繁盛よいですね。あ、よくないですか。この日本語は」
医師は笑った。「医者を必要とするのは、健康な人ではなく病人だとおっしゃったのは神父さまではないですか」
「おぅ、違います。それはイエス様」
「教会に来てみないと、人は自分が罪びとであることがわからないとおっしゃったのは神父さまでしたね。病院も同じですよ。だから繁盛するのは良いことです。さて――」立石医師はカルテと、印字されたいくつかの書類を確認して、言った。「内科の方から報告をいただきました。結論から申しあげますと、ヨゼ神父さま。お体に問題は見つかりません。訴えられている倦怠感や頭痛、不眠、食欲不振、記銘減弱――失礼、いわゆる物忘れですね。それに集中力の減退感などは、脳や血管の詰まり、そういった身体的なものが原因ではないと思われます」
ヨゼ神父は首をかしげ「健康? わたし」
「ええ、身体的には」立石は両の指を組み合わせて、少し目を閉じて顔を上げたあと、ヨゼ神父の方を向いて、言った。「ですが神父さま、そういった体の症状は、こころの状態に左右されることがあります。ありていに言えば、そう――昔はノイローゼと言われました」
「ノイロゼ?」
「neurosis――スペイン語はわかりません。すみません」
ヨゼ神父は小刻みに首を縦に振った。「なら大丈夫。大丈夫。わたし、繊細からほど遠いですね」
「神父さま――」立石医師は、ヨゼ神父に向かって、前のめりに身を乗り出した。「本当のところをふたつ、申しあげます。ひとつ目は、ひとりの信徒として、ヨゼ神父さまに、このまま芝浦教会の主任司祭として司牧を続けてほしいと願っています。ですがもうひとつは、医師として、ヨゼ神父さま、あなたには休息が必要です。そう、スペインにしばらくお戻りになって、精気を養われた方がいいほどに」
ヨゼ神父はため息をついたが、立石は真剣な表情で続けた。
「日本のマルキエル宣教会に、〝代えの神父〟がいないことは承知しています。ですが、一時的に教区司祭を主任とすることもできないわけではないでしょう。教区の司祭人事についてはわたしのわかるところではないですが、第二次司祭異動の前に希望を出せば、いや、それ以前に、スペインのマルキエル宣教会本部に事情を話せば、今年の復活祭後に、帰国なさることも不可能ではないのではないですか?」
「……すべては」ヨゼ神父はかぶりを振り「神様の御心におまかせです」
診察室に沈黙が流れた。
ヨゼ神父は、あの事件の、正確に言えば、あの事件のあとに起こった女性の死をあがなうために、この異国で孤独に十字架を背負い続けるつもりなのだろうか――立石は唇をかんだ。誰がそんな過酷な運命を、ひとりの人間に強いることができるだろう。
精神科医として、あの事件以来、ヨゼ神父が気丈を装っていても、どこか、情動が薄くなっていることに、彼は気づいていた。最近はSSRIと呼ばれる良い薬も出ている。それとなく勧めてみたが、ヨゼ神父は向精神薬の服薬はのらりくらりと拒否するのだった。おそらくそれは、自分を罰するために。
「――せめて、不眠については睡眠導入剤を試してみませんか?」
「大丈夫です。これがあります」ヨゼ神父は、ジャケットのポケットから、裸のロザリオを取り出して見せた。「眠れないときは、三環、四環、五環……。マリアさまにお取り次ぎを願っていれば、朝まで眠れなくても大丈夫です」
なんの取り次ぎを願って? と、訊ね返したくなる衝動を立石医師は押さえた。あの事件も、あの女性の死も、誰もヨゼ神父のせいではないとわかっているというのに。そう、おそらく、神でさえも。
「取りあえず、医者らしいことはさせてくださいよ。ビタミン剤を出しておきますので、毎朝、飲んでください」
「ありがとうございます。大丈夫です」
立ち上がり、一礼して診察室から出て行くヨゼ神父の後ろ姿は、年齢よりも相当に老けて見え、立石医師は処方箋に気休めを書きながら、眉に皺を寄せるのだった。
* *
片目を失ったあの日から、ヨゼ神父はクルマの運転をやめた。法規的にはなんら問題ない視力だったのだが、万が一にでも事故に遭いにでもしたら「あの片目の神父が」と言われてしまうと思ったからだ。
ヨゼ神父の足は、自然と、あの市営公園へ向かっていた。そこはかつて畜産試験場があった場所で、広く、古墳の跡なども残る、おだやかな場所だ。今の時期は草木も丸裸だが、復活祭を過ぎる頃は、並んだ桜並木が見事な花道を作ることだろう。
その公園の丘からちょっと入った奥。柵があり、立ち入り禁止になっている場所の大きな木で、彼女は首を吊っていたのであった。まだ年が明け、松が取れる前のことだ。あの事件の一週間後。ヨゼ神父がやっと、自分に起こったことを病院のベッドで理解できるようになった頃だった。
公園のベンチに腰を掛け、四旬節の、寒いが青い空を眺める。コートの下のジャケットからロザリオを出して、その十字架を指でなでる。
小教区の主任司祭として、彼女の顔も名前も、もちろん知ってはいた。もともとあまり〝熱心な信徒〟ではなく、最後の数ヶ月、教会へこなくなっていたことを気にかけてはいたが、彼女が悩んでいたこと、苦しんでいたことは、まったく気づいていなかった。なにしろその頃、自分は芝浦教会の主任司祭として一年間、つつがなく過ごせたことに多少自信を持つことができ、自分が神の御心にそってこの共同体を司牧しているという実感を、やっと得られたと思っていたのだ。
彼女が遺した遺書を、ヨゼ神父は、ほぼ違わず思い出すことができた。それほど、長いものではなかった。
* *
神父さま。ごめんなさい。
本当にごめんなさい。
こんなことになってしまって、ほんとうにごめんなさい。
わたしは悪い男にだまされた馬鹿な女です。
堕胎しました。
教会に来られる身ではありません。
なのに、教会に逃げれば、あの男は追ってこないと思ったんです。
しばらく身を隠したら、この街を出るつもりでした。
まさか、あの男に見つかるなんて。
神父さまが守ってくださらなかったら、あのとき、わたしは殺されていました。
そうなればよかったんです。
わたしが、神父さまの目と指を奪ってしまいました。
わたしの命で償えるものではないけれど。
許してください。
天国へ行かないことで、わたしを許してください。
* *
右の目から、大粒の涙がこぼれ落ちるのをそのままに、ヨゼ神父はうつむいていた。
堕胎をしたという彼女の苦悩を、それでも最後は教会に逃げてきた彼女の信仰を、自分の命を投げ出して、赦しを乞う彼女を、いったい、誰が責められるというのか。
彼女は確実に自殺であったが、現場に復帰したヨゼ神父は、それを知っている一部信徒の反対を押し切り、葬儀ミサを挙げた。
本来、カトリックでは自殺者のために葬儀ミサを挙げることはない。しかし、精神科医としての著作もあり、教会で信頼されている立石医師が、「彼女はこころの病が原因で病死したと考えられませんか?」と反対者の前で言ってくれたことが大きかった。また、教会委員総務の寺内が、裏でいろいろ骨を折ってくれていたこと、秘書役の妻木が大司教区の方にまで根回しをしてくれていたことを、あとで知った。
自分ひとりで、この小教区の司牧を切り盛りしているなどという自信……それが、なんという思い上がりだったのかと打ちのめされた。
ヨゼ神父の目と指を奪った犯人の男は、数ヶ月後、別の県で刃傷沙汰を起こし逮捕された。灰の水曜日のことであった。不思議な因縁に事情を知る信徒はなにか感じるところもあったが、ヨゼ神父は不思議と、犯人の男には憎しみも恨みも、驚いたことに、聖職者らしい憐れみも感じなかった。そう、なにも感じなかったのだ。
検察側の証人として裁判に出ることを求められたが、ヨゼ神父はそれを固辞した。彼は今、刑務所にいるはずだ。
わたしの左目と左の小指を奪ったのは、彼ではないという思いがあった。それは他でもない、神ご自身だと。自分は聖職者に向いていないと、神ご自身がお教えくださったのだ、と。
立石医師が提案してくれた選択肢の優しさを反芻したヨゼ神父は、スペインの乾いた風と街並み、下町の匂いを思い出した。
「アヴェ・マリア。グラツィア・プレナ。ドミヌス・テクム……」
ラテン語で十回、アヴェ・マリアを心の中で唱えると、霞がかかっていた頭が、少しだけ、はっきりしてきたような気がした。
今、考えなければいけないのは、聖櫃から盗まれたキリストの体のことだ。
もし、汚聖が行われていたのだとしたら、それらもすべて、自分のいたらなさのせいだと、それを自覚できない自分への神の怒りだと、ヨゼ神父は確信した。
そのときは――日本語が思い出せない。日本の大神学校で同級生だった、サムライの子孫だと言っていた友人の口癖だ。そうだ〝潔く〟。
潔く進路を決めよう。ヨゼ神父は立ち上がり、ロザリオをコート内側のジャケットのポケットに落とすと、教会への道を歩き出した。
(第3章へ続く)