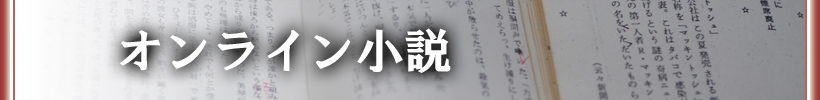オンライン小説
●第3章
翌週主日――日曜日のこと――午後二時からの英語ミサもつつがなく閉祭し、芝浦教会からは三々五々、人が去って行った。
ミサのときはあれほど人が入っていたお聖堂も、時計の針が午後三時半を回り誰もいなくなれば、壁かけ時計の秒針の音が聞こえるほどシンと静まりかえる。
ときたま、聖体訪問やマリア像に祈りをささげ、キャンドルに火をともしに外国人信徒がやってくるが、それも十分くらいでお聖堂をあとにする。
聖堂には「香部屋」と呼ばれる、司祭や侍者たちの準備室がある。芝浦教会のお聖堂では、入り口のすぐ横にその部屋が設えてあった。衣装ダンスには司祭や侍者の服が並んでおり、戸棚にはミサで使われるロウソクやミサ典礼書、主日ごとに信徒に配られる「聖書と典礼」のパンフレットなども整理され置かれている。
壁には、東京大司教区の司教と教皇の写真が並んで飾られ、またミサの予定表が貼られている。
「香部屋」はいわば、舞台でいう「楽屋」なのである。
そして対面壁面につけられた吊り戸棚の一番右に、小袋に入れて置かれているのが、聖櫃の鍵。これは、香部屋に出入りしたことがある侍者や、ミサの準備をしたことがある者なら誰でも知っている、周知の事実であった
もっとも、鍵といっても、それほど精密なものではない。手練れの泥棒ならば、この鍵などなくとも、針金一本を使い数分で聖櫃を開けてしまうだろう。この平和な時代に、聖櫃からご聖体を盗む者がいる、などということは、想像外のことではあるのだった。
また、聖堂の奥から階段を上ると、二重のガラス張りで防音された、聖堂内を見下ろせる小さな部屋がある。この部屋は、小さな赤ん坊などがぐずり始めたらそこに入り、ミサに与れる場所として用意されている。通称「泣き部屋」だ。
その隅で、モゾモゾと塊が動いた。頭からすっぽりと毛布をかぶり、目だけぎょろつかせて、お聖堂を見下ろしている――寺内であった。
三月とはいえ、暖房を切られたお聖堂の中の空気からは暖気が消えている。ましてや、泣き部屋においておや。
寺内は、鼻をズッとすすりあげると、確かめるように聖堂の入り口を、手に持ったコンパクトカメラのファインダーからのぞき、再び毛布に潜り込んだ。
そして、身震いをひとつ。これから現れるかもしれない、謎の「キリスト泥棒」を思っての武者震いか、単なる寒さからくるものか。
緊張と弛緩の連続で、さしもの寺内も、いつもの肝の太さは続かないようである。背後から音もなく近づいてくる影に気づかなかったのは無理もない。
この二階にある泣き部屋は、防火条例の関係で外へと続く階段がつけられている。普段は内側のノブで鍵が掛けられており、外側から開けられる鍵のありかを知っているのは、ごく限られた教会関係者だけだ。
影はそのノブを外側から開けて、悠々と寺内の背後へと回り込んだのであった。
そして手に持った、金属の丸く太い棒のようなものを――そっと寺内のかぶった毛布の頬の部分に当てた。
「わっ、わっ、うわわわ」
「おぅ、寺内さん、ごめんなさい。驚かせた?」
「お、驚きますよそりゃぁ」寺内は毛布をバッと体からはがして、荒らげはしないが小さい声で「せめて声くらい掛けてください」
影の主は、ヨゼ神父であった。手に、温かい缶コーヒーを持っている。
「ここ寒いですからね。差し入れです」
「そりゃ、ありがたい。遠慮なく」缶を振るとプルトップを開け、寺内は一口。「こりゃあ甘口だなぁ。多田井さん向けだ。いやでも、ありがたい。体が温まる」
と、ヨゼ神父の心遣いに感謝したあと、寺内は手でヨゼ神父に、〝身を伏せて〟と合図した。ここではヨゼ神父の大きな体は目立ちすぎる。もし聖堂に入ってきた者が泣き部屋を見上げたら、そのガラス窓を通して、人の影があることに気づくかもしれない。
ヨゼ神父もうなずいてしゃがみこみ、再び毛布をかぶった寺内に話しかけた。
「で、怪しい人は来ましたか?」
「いやあ、今のところ、全然」
「そうですか――」
ヨゼ神父の顔に、自然と、ホッとしたような表情が浮かぶのを、寺内は苦笑で受けた。ヨゼ神父はこういう人だ。ひょっとしたら、自分のやっていることが徒労に終わるのが一番なのかもしれない。
「寺内さん。もしも、ですよ。怪しい人が現れたとしても」ヨゼ神父は小さくかぶりを横に振り「手荒なこと、いけません。もし、相手にでも、寺内さんにでも、ケガがあったら、わたし、神様に顔向けできません」
「わかってますって。だからこうやって」と寺内はコンパクトカメラを見せ「今日はとにかく、証拠固めと思ってこれを持ってきた――」
途中で、寺内は言葉を飲み込んだ。聖堂の入り口に、冬の低い夕日に照らされて伸びた長い影が揺れたのが見えたからだ。
その長身、痩躯の影は、しばらく聖堂の入り口でたたずみ、中をうかがっているようだった。
毛布をかぶった寺内も、身を屈めたヨゼ神父も、その様子を二階の泣き部屋の二枚ガラス越しからうかがう。長身、痩躯の影の主は、二人の存在に気づいていないようだ。
長身、痩躯の影は、ゆっくりと聖堂の中に入ってきた。いや、それは長身ではない。そう見えたのは、冬の低い夕日のせいだ。そこにいたのは――ひとりの少年であった。
「こど……子どもだ」と、目を丸くして寺内。「なんだ。びっくりした……。あの子は、教会学校で知っている子ですよ。忘れ物でもしたかな?」
ヨゼ神父は、視力が残っている右目をすがめて、少年の様子を見ようとしたが、どうにもよく、網膜にその姿が映らないのであった。
「寺内さん、わたしはここからではよく見えないんですが、ご存じの子?」
「ええ。ここのところ、教会学校に母親とたまに来ている子で、去年の子どもクリスマス会にも来てましたよ。小学五年生くらいだったかな。お母さんもまだ未洗礼で、名前は確か、佐々木さんだ、うん」
「ああ、佐々木さんの坊や」
ヨゼ神父も思い出した。佐々木母子は、去年の秋あたりから、この芝浦教会に通うようになった二人である。ヨゼ神父は、主日ミサの聖体拝領列で、彼ら二人に連続して祝福を与えたことを覚えていた。いつもなにか、思い詰めた様子で祝福を受けていた母親の様子と神妙な子どもの顔が、ヨゼ神父の脳裏によみがえる。今日の拝領列にいたかどうかは、記憶が定かではないが……。
「こりゃあ白ですね。あんな子が犯人のわけは……」寺内の眉がクッと寄った。「ああ、やめてくれよ、そんなことは」
泣き部屋から見下ろせる聖堂で、佐々木少年は、聖堂に誰もいないことを恐る恐る確かめると、ゆっくりと、香部屋の方へと向かって行ったのである。そしてノブをつかみ、鍵が掛かっていないことを確かめると、ゆっくりとそれを回して扉を開け、中へと消えていった。
「なんてこった。どうしてあんな子どもが。なんのために? こりゃあ、なにかの間違いだ」寺内は、うーん、とうなったあと、フン、と鼻息をひとつ。「いやしかし、駄目なもんは駄目だ。もしあの子が聖櫃の鍵を開けたら、即座に怒鳴りつけて――」
「ねえ寺内さん」ヨゼ神父は、静かに、頭を横に振った。「ここは、わたしにまかせてくれませんか? 聖堂で、わたしと坊やの二人きりでお話をさせてください」
「いや、そりゃ……。いやしかし最近の子どもは見かけに寄らず――」
一年前の事件のこともあり、寺内が自分を心配してくれていることはよくわかる。たとえ相手が少年ひとりとはいえ、こういう状況で、二人きりにさせたくはない、ということも。
しかしヨゼ神父の唇は、なにかを考えるよりも早く、また落ち着いて、言葉を発していた。
「大丈夫です。あの子は悪い子じゃない。わたしにはわかります」
「神父さまが今まで、誰かのことを悪く言ったことなんか、一度もないじゃないですか」寺内は息をついた。同時に、ヨゼ神父がこうと言い出したら聞かないことも。「わかりました。ただし、聖堂には降りませんが、わたしはここから見ていますからね。なにかあったら、即、警察を呼びに行きますよ」
* *
聖柩の鍵の袋をそっと持って、少年は香部屋から聖堂へと、うかがうように出てきた。冬の陽が落ちるのは早く、窓から入る日差しは長い影を延ばし、聖堂の中はすでに薄暗い。
その聖堂の真ん中、内陣を登った中央に、磔刑されたイエスの十字架があり、その下に小型金庫くらいの大きさの聖櫃がある。脇には点灯している赤い聖体ランプ。これが灯いているということは、聖櫃の中にご聖体が入っている、という証しである。
本来この聖体ランプは、ロウソクでなければいけないことになっているが、日本でだけはバチカンから許され、商用電源から引いた電球を光らせればいいことになっている。
少年は、聖櫃の鍵をそっと袋から出すと、できるだけ腕を延ばして聖櫃の鍵穴に差し入れ、両開きの聖柩の扉を開けた。
中には、大人の両手で押しいただける程の大きさのチボリウム。しかし、彼の背丈では中をのぞくことはできない。
少年は精いっぱい背伸びをして、両手で聖櫃の中を何度かまさぐったあと、確かにチボリウムの両側を手でつかみ、丁寧に、そっと、外に出すことに成功した。
少年の顔つきに、明らかにホッとしたような表情が浮かぶ。彼はチボリウムを、胸の前で、両手で大事に押しいただいて体を返し、祭壇の上に置いた。
「――そこまでにしておきましょう」
突如、掛けられたヨゼ神父の声に、少年は飛び上がった。まさか、聖堂の陰の中に、自分を見守っていた人影がいるとは思ってもみなかったのだ。
「神父さま――」しかし、少年は逃げることも、後ずさることもなかった。むしろ、きりっと視線を上げてヨゼ神父の顔を見つめ、濁りのない、澄んだ瞳で言ったのだった。「ぼくが悪いことをしていることはわかっています。地獄に落ちたってかまいません。けど、信じてください。ぼくは一枚もこれを食べていません。今、これを必要としている人がいて、その人のために――」
ヨゼ神父は右手を挙げて、続ける少年の言葉を制し、そして左手を挙げて――少年の体を引き寄せ、抱きしめた。
「わかりました。わかりました」少年が嗚咽こそしていないものの、涙をいっぱいに浮かべ、頬にそれを流していることを、夕日の射す影が長い、暗い聖堂の中でも、ヨゼ神父は悟ることができた。
「先週も、先々週も?」
「はい。ぼくがやりました。ごめんなさい」
「君の大事な人は、ご家族?」
「お兄ちゃんです。ぼくよりふたつ年上で」
「お兄ちゃんはどこの病院に?」
「いいえ、もう助からないだろうから、最後は家でって。でも、先々週にご聖体を食べさせたら、元気になったんです。だから、やったと思ってたら、先週、また発作を起こして――」ついに少年は、声を上げて泣き出したのだった。「神父さま、お兄ちゃんを助けてください。もう、今朝から、息がつらそうで、今にも……。だからお兄ちゃんには、今、これが必要なんです」
「わかりました。今すぐ、君の家に行きましょう」少年の両肩を握って、少し彼の体を離すと、ヨゼ神父は、優しく、真剣な表情でうなずいた。そしてチボリウムを視線で指し「君がそれを持ってくれますか?」
「ぼくでいいんですか?」
「ええ、ぜひとも」
チボリウムを両手で大事に持った少年の肩を抱いて、お聖堂の扉を開け、外に出ると、階段の下には、一台のクルマが転回してくるところだった。運転席にいるのは、寺内だ。
彼は運転席の窓を開けて、ヨゼ神父に「事情はだいたい把握しましたよ。さあ乗って乗って」
「おう、さすが寺内さん」
「さあ早く。坊やは前だ。案内してもらわなきゃいけないからな」寺内は手で少年を呼び、そのごつい顔に似合わない真剣な表情で、言った。「俺たちゃイエス様と違って、そのときがきちまったら、ラザロを起こすことはできないんだから」
* *
街灯がポツポツとつき始めている。この季節、太陽が落ちるのは早い。すでにあたりは薄暗く、クルマもヘッドライトなしでは走れない。
ここは路駐禁止区域だから、自分は車内に残っていますよ、という寺内をクルマに置いて、少年とヨゼ神父は、玄関灯がついている一軒の前にいた。
「今、鍵を開けます」
ヨゼ神父は、多少の違和感を覚えた。今、臨終の床にある家族がいるというのに、この家は人気がなさすぎる。少年が開けた玄関の中も真っ暗だ。
「ご家族のみなさんは?」
「ぼく、もうずっと、お母さんと二人暮らしなんです。お父さんは別の家に住んでいて」
「お母さんは?」
「ほんとは一緒にいたいんだけど、仕事がどうしても抜けられなくて、って――」
この子の兄が、今、今際の際にいるというのに、仕事が抜けられない!? ヨゼ神父の違和感はいっそう強くなったが、少年がなにかたくらんでいるとも思えない。
その証拠に、奥の部屋から、なにか定期的に空気を圧縮する音と、シューッという連続した擦過音のようなものが聞こえてきているのだ。これは自分も病院で聞き慣れた、圧縮酸素を送る機械の音だ。
ヨゼ神父は、疑惑を振り払うように言った。「お兄ちゃんはどこに?」
「こっちです」
少年は居間にヨゼ神父を案内した。壁のスイッチを入れて電灯をつける。
「これ、は?」
フローリングの居間の床に、衣装箱ほどの大きさのガラスケースが置かれていた。その横に、確かに酸素圧縮装置がつながれ、ガラスケースの中に酸素を送り込んでいる。中にいたのは――一匹の猫だった。
「これが君のお兄ちゃん?」
少年はうなずいた。
ヨゼ神父は、ガラスケースの中をのぞきこんだ。中の猫は呼吸を荒くし、身を横たえている。しかし、キッとヨゼ神父を見たその瞳は、弱々しくはなかった。むしろ、「おまえは何者だ?」とでも言わんばかりの力強ささえたたえていた。
ヨゼ神父は、自分でも気づかず、こう、つぶやいていた。「おぉ、主よ――」
「良かった。まだ大丈夫だ――」ヨゼ神父の横から頭をぶつけるように中を見た少年が言った。「今朝は血を吐いちゃって、もう、特別なご飯も食べられないんです」
「お兄ちゃんの病気は?」
「心臓が悪くて、大きくなっちゃうんだそうです。それで〝ハイスイシュ〟になって、呼吸ができなくなっちゃうので、この酸素室に――」
ヨゼ神父は、何度も、小さくうなずいた。この少年が、猫を〝お兄ちゃん〟と呼ぶことを、誰が責められようか。きっと彼は、赤ちゃんの頃からずっと、この猫と一緒に成長してきたのだ。少年にとっては、唯一無二の〝お兄ちゃん〟であることに間違いはない。
「ねえ神父さま、お兄ちゃんに、これをあげてもいいでしょう?」少年は、大事に抱えていたチボリウムを、そっとヨゼ神父の前に出し「悪いことだってのはわかってたんです。でも先々週、ご聖体を持ってきて、すりつぶして、お兄ちゃんにあげたら、本当に元気になったんです。この酸素室から出て、普通のご飯を食べて、ちょっと走ることができるくらい。だけど、また発作を起こして――だからぼく、先週もご聖体をいただいてきて、お兄ちゃんにあげたんです」
少年は、ポロポロとこぼれてくる涙をぬぐうこともせず、懇願するように、ヨゼ神父に続けたのだった。
「ご聖体を盗むのが、悪いことだってのは、もちろんわかっています。ぼくは地獄に落ちたっていいんです。お兄ちゃんが助かれば、ぼくなんてどうなったって――」そして、顔を上げ「ねえ神父さま、これ、本当のイエス様のお体なんでしょう? 病気の人を治し、死んだ人を生き返らせた、イエス様のお体でしょう? ぼくのお兄ちゃんだって、治せますよね。ね」
ヨゼ神父は、チボリウムを抱えたままの少年を、真正面から、大きく抱きしめた。いったい誰が、この少年のしたことを〝涜聖〟だと指弾することができるというのか。汚らしい盗みだとののしることができるのか。少年の瞳から流れる涙が、ヨゼ神父のカラーシャツに染みる。この少年は、物理的には酵母の入っていないこのウエハースを、心の底から、イエス・キリストの体だと信じて疑っていないのだ。
これ以上の信仰が、これを越える敬虔さが、この世の中でいったい誰にあると言えるというのか。
しかし、チボリウムの蓋を開けようとした少年の手を、ヨゼ神父は、そっと、押さえたのだった。
「ごめんなさい。君のお兄ちゃんには、ご聖体、あげられません」
「どうして? お兄ちゃんが猫だから? そんなの、おかしいです。ぼく、勉強したんです。難しかったけど、聖書にも、犬でもテーブルから落ちるパンをいただくって書いてあったんです。だから――」
「そうだね。確かに、そうだね」
ヨゼ神父は、ほんのわずかの間、迷った。この場で、〝お兄ちゃん〟にご聖体をあげることなどたやすいことだ。しかしそれが、この少年の信仰に、純粋な敬虔さに報いることになるのか。そうではないはずだ。この少年に真正面から向き合って、本当のことを、精いっぱい、真摯に伝えようとすることこそが、自分にできる、一番誠実なことだ、と。
「やっぱり、ぼくのお兄ちゃんが猫だからなの? 神父さまも言うの? たかが猫だからって――」
「そうじゃない、そうじゃないですね」ヨゼ神父は、残った右目で、しっかりと、しかし優しく、少年の目を見つめた。「君のお兄ちゃんには、もともと罪がないから。だからご聖体を食べても、効果、ないんです。
「罪? 悪いこと?」
「君のお兄ちゃんが猫だから、というのは、確かにそうです。人間は動物とは違います。わたしや君は人間で、原罪を負っています」
「ゲンザイ?」
「そう――なんていったらいいかな。わたしたち人間、生きていて、いつも神様のこと、どこかで忘れています。お友だちをいじめたり、それを見て見ぬふりをしたり、誰かを憎んだり、乱暴な言葉を使ったりしますね」
「それが、ゲンザイ?」
「そう、原罪がかたちになったもののいくつかです。神様のことを忘れて、生きているのがつらいとか、もう死んでしまおうかな? とか、神様のことを忘れてしまおうかな? とか思うこと。これが原罪ですね」ヨゼ神父は少年をうながして、チボリウムを受け取り、横にそっと置くと、酸素室の中の〝お兄ちゃん〟の様子を見せた。中の猫は、息を荒くして、今にも命の火を吹き消されそうになっていても、その瞳だけはカッと開き、二人の様子を見つめているのだった。「君のお兄ちゃんは、これっぽっちも原罪を犯していません。原罪を犯すのは人間だけです。だから、毎週、ごミサでご聖体をいただきます。告解もします。でも、君のお兄ちゃんは、そういう罪がないですね」
「よくわからない……」
「ご聖体は、そう、魂の病気を治す薬みたいなものですね。君のお兄ちゃんは、体は病気だけれど、魂、病気じゃないですね」
「でもこんなに苦しんでるのに……。ぼくが、ぼくがご聖体を盗んだから、神様が罰をあてたの?」
「違う。そんなことは、絶対ありません」
「じゃあ」少年はヨゼ神父の胸に、両手の拳を叩きつけた。「神様なんていないんだ」
「いますよ」ヨゼ神父は、酸素室の中でうずくまっている猫を目で指した。「今、ここに」
「お兄ちゃんが神様なの?」
「君のお兄ちゃんの中に、確かに、イエス様、いらっしゃいます。そして今、苦しんでるのは、わたしたちを救うため」ヨゼ神父は、少年がまた口を開こうとする前に、彼の手を強く握った。「いつか、それがわかる日が必ずきます。だから今は、一緒にいてあげる。それが、一番」
「神父さまも一緒にいてくれる?」
大きく、ヨゼ神父はうなずいた。
そして、自分の修道名がペトロであることを思い出し、今、死を前にした主の【御前/みまえ】から逃げ出さずにいられることを、神に感謝した。
* *
路上に停めたクルマの中で、寺内は車内灯をつけ、聖書をめくっては、目を落とし、また閉じてはめくり、一文を読んでは、閉じるのだった。
すでにあたりは暗くなり、佐々木家の玄関灯だけが、このあたりの路面をホッと照らしている。
小一時間前に入っていったヨゼ神父と少年はまだ出てこない。
顔はいかつく、声を出せばべらんめぇの寺内ではあるが、決して勘の悪い男ではない。少年の兄が臨終の床にあるにしては、この家は静かすぎる。普通ならばもっと人の出入りがあるだろうし、第一、誰かが路上にクルマを停めた寺内に挨拶にくるだろう。
これらのことから、中でどのようなやりとりがなされているか、寺内はだいたい、想像ができていた。
聖書をめくるのにも飽きて、寺内は、カーオーディオにカセットをガチャンと差し込んだ。
「『何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある』という言葉があります。〝コヘレトの言葉〟の一節です」
流れてきたのは、この四旬節に行われた黙想会での、司教の話の録音である。「続けてみましょう。『生まれる時。死ぬ時』――」
と、家の中から、あの少年の泣き声が聞こえてきた。それは、何度も、何度も続き、やがて、小さくなっていった。
カセットの音声は続く。「わたしはこの部分も好きですね。『人間に臨むことは動物にも臨み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊をもっているにすぎず、人間は動物に何らまさるところはない』いかがですか? みなさん、ちょっと黙想してみましょう」
カセットをガチャンと引き出すと、寺内はまた聖書をめくり、車内灯の中でパラリと開く。「『すべては塵から成った。すべては塵に返る』、か――」
家の扉が開いて、ヨゼ神父が出てきた。寺内のクルマへ寄ると、窓を開けて? とレギュレーターハンドルをくるくる回すジェスチャー。
先に質問をしたのは寺内だった。「ワンちゃんですか? 猫ちゃん?」
ヨゼ神父はびっくりした表情を作って見せた。「どうしてわかったんですか?」
「あの年頃の坊やより長命で、闘病中なのに、だけど家は静まってる。お母さんの佐々木さんの気配もない。お兄ちゃんが誰なのかくらい、少し考えればわかりますよ」
「おぅ、寺内総務委員。探偵さんでもやっていけますね」
「ごめんこうむります。で、これからどうするんです?」
「彼のお父さん、事情があって、どうやら家にはもう戻らないらしい。今夜はお母さんがくるまで、一緒にいてあげますね。お母さん、何度か教会で会ったことがあります。顔知ってる。だから、大丈夫」
「わたしもここで待ちますよ。乗りかかった船だ。いくら神父さんだからって、家に男が知らぬ間に入ってたとなったら騒ぎになりかねんでしょう。母親が帰ってきたタイミングで、事情を話してから入ってもらいますよ」
「感謝します。それとですね、寺内さん」
「なんですか?」
ヨゼ神父のおねだり上手を知っている寺内は、もうすべて引き受ける苦笑で受けた。
「お葬式、挙げてあげたいです。もちろん、ミサには、ならないけど。なにか、寺内さん、知恵ありますか?」
「――わかりました。なんとかします。場所は教会でってわけにはいきませんが、神父さまが出張してくださるなら心当たりはあります」
「ありがとうございます」
寺内は軽く首を縦に揺らし「今、あの子は?」
「お兄ちゃんを抱いて泣いてますね、でも、賢い子です。きっとわかってくれます」
「あとのことはまかせて、今はあの子についていてあげてください」
ヨゼ神父が再び佐々木家に入るのを横目で見ながら、寺内はバックミラーに写る、こちらへ向かってくる小さな人影に気づいていた。さて、少年の母親に、なんと声を掛けなにをどう言うべきか、そして、なにを言わずにおくべきかを考え、彼は小さく、ため息をついたのだった。