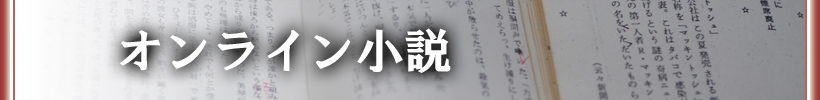オンライン小説
●第4章
その年の春分の日だった。柔らかい陽光がペット用の小綺麗な火葬場を照らしている。
ヨゼ神父と佐々木少年は、煙突から空に上っていく煙を見上げていた。
「お母さんも一緒にこられなくてごめんなさい。今日もお仕事だからって」
ヨゼ神父は優しくうなずいた。
「お母さんから、神父さまにくれぐれもよろしくって」
あの晩、佐々木少年の母親は、家に入る前に寺内に呼び止められ、ことの次第をすべて聞いた――ただ、ご聖体泥棒のことだけは抜きにして――のだった。母親は、むしろ恐縮するほど恐縮していた。それまでもたびたび教会へ佐々木少年と顔を出していたので、神父さまを頼ったのはよくわかる、と――。父親はもう家に戻らない。そういう事情があるのだった。
猫は佐々木少年が生まれる前から飼っていた雄猫で、心臓病だった。母親も可愛がっており、レンタル酸素室で治療していたのだった。
「それでは、お葬式を始めましょう。この前も話したけど、君のお兄ちゃんには原罪がありません。だから、人間と違って、お葬式のミサはできません。けれど、少しミサに似せて、お葬式の儀式、やりましょう」
きちんと葬儀用の白いストラを掛けているヨゼ神父は、手書きの式次第をコピーしたものを少年にわたした。「このマーカーの部分を一緒に読んでくださいね」
「はい」
それは、少年のために、ヨゼ神父と寺内が頭をつきあわせて作った式次第だった。
日本のカトリックには、未信者のためにミサのない「結婚の祝福式」はあるが、未信者のための、ましてや動物相手の「お葬式」などはない。
それでも、佐々木少年には、それっぽく儀式を挙げてあげることが大切だ、と、二人の意見は一致したのであった。
「父と子と聖霊の御名によって」
「アーメン」
「天におられる父よ、今、あなたのところに、罪のない無垢な魂を送ります。どうか、この無垢な魂が、あなたの腕の中に抱かれ、永遠の憩いを得られますように。わたしたちの主、イエス・キリストによって」
「アーメン」
「じゃあ、聖書のここのところを読んでください。ちょっと難しい漢字もあるけど読めるかな?」
「ふりがなが振ってあるから大丈夫です」
少年はヨゼ神父からわたされた聖書の、マーカーが引いてある部分を読んだ。コヘレトの言葉、三章十九節――。
「『人間に臨むことは動物にも臨み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊をもっているにすぎず、人間は動物に何らまさるところはない』――これは神のみことばです」
「神に感謝」よくできました、と、ヨゼ神父はうなずき、聖書を少年から受け取った。
「アレルヤ、アレルヤ。キリストに賛美。アレルヤ、アレルヤ、神に感謝」
アレルヤ唱を唱えたあと、今度は新約聖書の部分を広げる。
「『わたしは良い羊飼いである。わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っている』。キリストに賛美」
「キリストに賛美」
ヨハネによる福音書、十章十四節――。
「では一緒に、主の祈りを唱えましょう。これは一番大切なお祈りですよ」
「知っています」
二人は一緒に「主の祈り」を唱えた。
〝お兄ちゃん〟の遺体を焼いた煙が、三月の空へと上っていく――
「恵み豊かな神がわたしたちを憐れみ、罪を許し、今あなたのところにお送りした無垢な魂が、あなたの腕に抱かれ、憩うことができますように」
「アーメン」
「行きましょう、主の平和のうちに」
「神に感謝」
以上が、ヨゼ神父が、佐々木少年のために、特別に用意してくれた「お葬式」だった。
三月の空は気まぐれで、少し風が強くなってきた。少年は乱された髪をかきあげると、ヨゼ神父に、涙を浮かべた目を上げて、聞いた。
「神父さま。ご聖体のこと、本当に謝ります。ぼく、これからはいい子にします。そうしたら、天国でまた、お兄ちゃんに会えるかな?」
ヨゼ神父は優しく微笑み「とんでもない」
「えっ?」
「たとえ君が悪い子だったとしても、神様は君のことをとても大切に思ってるんですよ。だから、必ず、また会わせてくれます。必ずです」
「神父さま」少年はわっと泣き出して、ヨゼ神父に抱きついてきたのだった。
ヨゼ神父は少年をかたく抱きしめると、自らも涙がこぼれてきそうな目を上げた。視力の残る右目の網膜に、流れる大きな雲と、上っていく煙。そして、ヨゼ神父は、この湿った日本の風の匂いを心地よく思っている自分に気づいたのだった。
* *
ザクリ、と、樫の木の根元にスコップの先が入る。復活祭も過ぎ、教会に射す陽光もだいぶ暖かだ。寺内の額にも、薄く汗が浮いている。
「このくらいでいいだろう」
ある程度の穴が開いたところで、寺内は少年をうながした。佐々木少年は神妙に、猫の絵の描かれた骨壺をそこに慎重に置き、それから、そっと右手で涙をぬぐった。
「よし、じゃあ土を掛けるぞ」寺内はうなずいて、そっと土を掛け始めた「言っておくが、誰にも内緒だぞ。坊やと、ヨゼ神父さまと、俺だけの内緒だ。いろいろうるさく言うやつもいるんでな」
「ありがとうございます」
寺内は困ったような顔をした。あまり、真正面から礼を言われることに慣れていないのだ。
「まあ、いつでも来いよ。教会ってのはそういうところだ。その、なんだ……」語尾をごまかしながら、寺内は穴を埋め終わり、スコップでならすと、そっと、横に用意しておいた、一輪の百合を置いた。「教会ってのは、神様の家だからよ。誰だって、いつだって、ただいまって帰れる場所なんだ」
二人の様子を、ヨゼ神父は司祭館の窓から見つめていた。そっと、閉じたままの左目に手を当ててみる。その眼球を失ったとき、自分は光をなくしたと思っていたのだ。
陽光が新緑に揺れる。こんな素晴らしい情景を見られる右目が、まだ残っているではないか。
復活節は、まだ始まったばかりだ。
* *
青年はしゃがみこんで祈っていたが、やがて、立ち上がり、樫の木を見上げた。今年の灰の水曜日は遅かった。その分、復活祭も遅くなる。今はまだ四旬節だというのに、太陽の光がだいぶ暖かい。樫の木を通って射すそれは、二十五年の時を経ても、なにも変わっていないように感じる。
隣接した駐車場に、一台のクルマが停まった。助手席から、片目の外人が降りて、伸びをする。
「いやあ、いいですねえ。新車にカーナビ、エンジンも静かですね」
運転席側に回った彼に向けて、壮年のしかめ面の男が、パワーウィンドウを開けて声を掛けた。
「だからエンジンだけじゃないんですって。ハイブリッドって言って、エンジンとモーターを使った――」
「よくわかりませんが、まずは新車の祝福を――」
と、二人は樫の木のもとにいる青年に気づいた。
まず反応したのは、運転席の男だった。「おかえりなさい、蘇我野神父さま」
「寺内さん、お久しぶりです。助祭叙階式以来ですね」
「まさかここに配置されるとは夢にも思わなかったけれどね」寺内にしては珍しく、崩れるような笑顔が浮かんだ。「言ったでしょう? ここはただいまって帰れる場所だって」
片目のヨゼ神父は、二人を交互に見て「お知り合い?」
「神父さま、歳でもボケるのはまだ早いでしょう。春からあなたと一緒に頑張ってくれる、うちの助任司祭ですよ」
「蘇我野文章です。ヨゼ神父さま」
「あぁ、ソガノ神父さま。君が」ヨゼ神父はにっこりと笑った。「お会いできる日を楽しみにしていましたよ。ここまでは電車で?」
「いえ、バイクで――」と、駐車場の横に停めた、大型のスクーターを目で指し「実はこのあたり、わたしけっこう詳しいんですよ」
二人の様子をニヤニヤと見ながら、クルマの運転席から寺内は声を掛けた。「神父さま、クルマの祝福はまたにしましょう。神父さまはそう思ってないかもしれませんが、わたしも忙しいんです」
寺内は、駐車場の中でくるりとクルマを転回させると、教会の門から出て行った。
「ごめんなさいねぇ。ソガノ神父さま。今のがここの教会の今の教会委員長です。本人、忙しいとか言ってるけど、けっこう暇人。暇人。わたしは。ヨゼです。この教会の主任司祭」
「ええ、存じてます。またこうして、ここでお会いできるとは思っていませんでした」
二人の間に、春の風が吹き抜けた。それは、いつか感じた、あの日の匂いとともに――。
「え? また? 以前にも会った?」
「はい。覚えていらっしゃらないかもしれませんが――」青年神父は、人懐こい笑顔を浮かべた。「わたしは二十五年前、この教会でキリストを盗んだ少年です」
「二十五年前?」
ヨゼ神父の脳裏に、まるで古いアルバムからパラパラと写真が落ちるように、さまざまな情景が巡っていき、やがて、ひとつの少年の像が浮かびあがった。神父は残った右目を見開いた。
「あのときの、君か!」
「はい。あのとき、猫のお葬式を挙げていただいた子どもです。当時は、佐々木という名字でした」
「そうか、君、神父になったのか。覚えている、覚えているよ」それどころか、忘れるはずがなかった。「いや、どうして。今まで全然気づかなかった」
同じ教区にいれば、神学生や助祭の動向は、聞くともなく耳に入ってくるものだ。しかし今までヨゼ神父は、彼が司祭への道を進んでいたことを知ることもなかった。
「あのあと、わたしの両親は離婚して、わたしは母に引き取られて、実家の方へ引っ越したんです。蘇我野は母方の名字です。教区も名字も違ってしまったので、神父さまは今まで、お気づきにならなかったのだと思います。寺内さんだけは、なにかと気に掛けてくださって、助祭叙階式にもいらしてくださいました」青年神父は、きらきらとした瞳で続けた。「寺内さんには、わたしから内緒をお願いしていたんです。もしヨゼ神父さまにもう一度お会いできる日がくるなら、司祭としてお会いしたいから、って。だからヨゼ神父さまのお噂は、いつも聞いていました」
「うん、うん。相変わらず、この教会にいるよ」
二十五年、ひとつのカトリック教会に同じ司祭が勤め続けることは稀なのだ。特段の事情がなければ。そして、ヨゼ神父と、マルキエル宣教会が設立したこの教会には、その特段の理由があったのである。今となっては、マルキエル会で唯一、日本語を話せる司祭、という。また、それ以上に、過去の事件でヨゼ神父が信徒たちに愛されているというつながりもあった。
しかし、ヨゼ神父も高齢になり、教区の大司教も、そろそろ教区司祭をひとり、助任司祭としてつける決定をしたのである。
別の教区で司祭叙階を受けた教区司祭が、他の教区へ移ることはそうないが、ちょうど、病気の教区司祭が故郷の教区へ移るのと交換のかたちで、この若い司祭は、生まれ故郷のこの教区へと送り込まれたのである。
「この教会へ母が来ていたのは、父とのことを悩んでいたからだと思います。あのとき、洗礼こそ受けませんでしたが、母はよくロザリオで祈っていました。でも――」青年は少しため息をつき「奇跡なんて、そう起こらないものですねえ。父と別れて、引っ越してから、母はめっきり教会へ行かなくなってしまいました。それでも、わたしが神学校へ行くと言ったときは喜んでくれて」
奇跡が起こらないだって!?
ヨゼ神父は、目の前の、背の高い、素直な表情をした、どこかあどけなさの残る青年の顔をまじまじと見つめた。
あのとき、猫のためにご聖体を盗み、一緒にお葬式を挙げた少年が、今、こうして、ひとりの司祭として自分の前に立っているのだ。
「今になってわかります。あのとき、神父さまがどれほど自分を救ってくださったか。わたしが司祭職を選んだのも、あのときヨゼ神父さまがいらっしゃったからこそです。本当にあのときはありがとう……神父さま?」
ヨゼ神父は、涙を流していた。光を失った左目から、唯一残った右目から。そして、それをぬぐうことができなかった。
もし、あのとき、あの少年がいなかったら、自分はきっと、宣教の道を捨て、母国へ帰っていただろう。
自分がこの青年を救ったのではない。自分こそが、あのとき、あの少年に救われていたのだ。
老神父は、この若い青年の手を取って、握りしめたいという衝動に耐えた。ヨハネによる福音書で聖トマスが漏らした一節が、強く、たくましく、老神父の心に浮かびあがっていた。『わたしの主、わたしの神よ』と。
「どうかしましたか?」
「あ、いや――」手を握る代わりに、ヨゼ神父は蘇我野神父の肩に手を置いた。「蘇我野神父さまに、お願いがあります。復活祭前です。わたしにゆるしの秘蹟をお願いできますか」
青年神父は、目を丸くして、そして、小刻みにうなずいた。
「ええ、ええ、もちろん。もちろんです」それから、照れくさそうに「実は、告解を聞くのは初めてなんです。司祭叙階のあと、人事配置を知らされてから、すぐにここへ飛んできたので――」
「それでは、告解室へ行きましょう。場所は――」
「もちろん知っています。この教会のことは、子どもの頃から」
「そうだったね。それでは、改めて」ハンカチで涙をぬぐうと、老神父は、若い、溌剌とした青年神父を、優しい右目で見上げて、言った「芝浦教会へおかえりなさい。蘇我野神父さま」
「はい。ただいま帰りました」青年は、少しはにかんで、言った。「キリストを盗んだ、放蕩息子の帰還です」
( 了 )