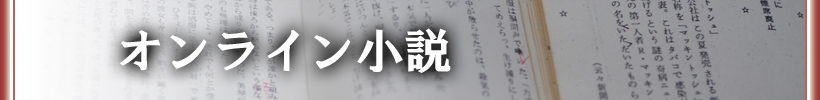オンライン小説
●第1章
望みさえすれば、誰でも地球周回軌道上のカモメになれる時代に、今の彼ら以上に切ない思いで、この青い惑星を眺めている者がいるのかしらと、ふと思ってしまうと、涙を浮かべればより一層悲しくなってしまうのがわかっているのに、それでも少し、泣いてしまった。
ステーションの中は肌寒く、それが色彩乏しいメインフロアからうける五感の錯覚だとわかっていても、思わず背を丸め、震える胸を抱きこんでしまう。マスコミが祭りあげる、地球と【来訪者たち/ビジターズ】の絆とは、いったい誰のこと? 一人になってしまえば、ただの女でしかない。今の主人とではなく、彼とあの懐かしいアパートで暮らしていれば、こんな気持ちになることはなかったのに。それを言っても、もう遅い。それはわかっているけれど、でも、やはり……。よそう。しかたがなかったのだ。
流れる曲が、好きなパッヘルベルのカノンに変わる。【あの人たち/ビジターズ】の科学は、我々の全てを変えてしまったけれど、芸術だけは、消し去ることはできなかった。そう、信じたい。しかしこの真空の宇宙で、空気をつめた現代科学最先端の金属の【泡/バブル】に似合う音楽が、地球がまだケーキの形をしていた時代のそれだとは。でもなぜ、この曲を好きになったのだろう。思いだせない。あるいは、思いださない方がいいのかもしれない。
気づけば、横の扉は開いていて、世話役のまだ若いドクターと看護婦が、子供たちをつれてきていた。そうとうむずかったらしいペリジーは、さっそく乾いた涙が光る顔をくしゃくしゃにして、看護婦の手を振りきり、わたしの胸に飛びこんでくる。
「お手数をおかけしたみたいですね」
「いいえ」黒人のドクターは白い歯を見せて笑った。「二人とも、いい子にしてましたよ」
微笑み、わたしはペリジーの頭をなでた。「ほんとにこの子は、人見知りが激しくって。誰に似たのかしら?」
「アポジーちゃんの方は、目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうほど、活発なんですがねえ」
「あは」苦笑するしかない。「やっぱりお手間かけちゃって」
「あいや、これは失言」
屈託なく笑う黒い顔。縮れた髪、厚い唇、出身はアフリカというところだろうか。憎めない人だ。
やはり黒人の看護婦は、一礼すると去っていった。
「これで全部終わりかしら?」
「ええ。検疫関係に関しては。今回のご滞在は?」
「二ヶ月というところかしら。彼らを見送って――」ステーションの軸の部分につながれた彼らの船を見やり「あとは主人しだい」
「ついにここまできましたねえ」ドクターはうなずいた。「あいつらにしても、嬉しいでしょう。新世界を探して、宇宙を旅するなんて、ちょっと羨ましい気もしますよ」
「ええ、あ……、うん」わたしは返事をごまかし、咳こむふりをした。
「あいつらはどこを目指すんですか?」
「まずは【木星/ジュピター】。そこの恒星船で“【協力者/コーペレータ】”全員の到着を待って、バーナード星系へと」
「どのぐらいあるんです?」
「六光年の距離ね」
「と、言うと、光の速度で六年か」彼は心外そうな口調で、ふーん、と鼻を鳴らした。「わりと近いんだなあ……」
彼には六光年という距離がどういうものかわかっていないらしい。いや、そんなことはあるまい。若くしてステーションの検疫官になるほどの頭脳の持ち主なのだから。わかって行っているのだ。彼らの船がそこに到着するまでに、千年以上の月日が必要だということを。
もっとも、わたしは彼らの船が、そこへ行き着くことがないことも知っている。わたしは口をつぐみ、話題を変えた。
「食事はできるかしら?」
「ではご一緒しましょう」白衣の腹を叩き「実ははらぺこなんですよ。地球採光室がいいな。ご案内します」
眠り始めたペリジーを抱き立ち上がる。ドクターがアポジーの手を引いてくれた。
通路を出て通り過ぎる人々はみな有色人種で、【わたしの主人とその同胞/ビジターズ】の徹底した政策を思いしらされる。望みさえすれば、人は誰でも地球周回軌道上のカモメになれる。しかし非有色人種は人ではないのだ。
「ここも相当変わりましたよ。先月は日本の学生ツアーに荒らされましてね。連中ときたら、ニュートン物理学さえわかってないんだから」
「時代も変わったわ。少なくとも、物理を知らない人間が、地球をその目で眺められる程度には、ね」
白衣姿の若い日本人が三人、笑い声をたてながら通り過ぎていく。わたしはふと振り返った。線の細い小柄な若者と、不精ひげに汚れた裾の二人が、まだ笑顔の幼い女性をはさんで――まるで昔のわたしたちのよう。わたしと、わたしが愛した優しい人と、いつも怒られてばかりいて少し恐かったけれど、磊落で頼りになった先輩に。
「奥様?」
呼びかけられて、我に返る。わたしはかぶりを振って、ため息をついた。
「ごめんなさい。ちょっと昔を思いだしていたの」
「昔、ですか?」
「ええ」
それ以上喋りたくなる衝動を、速めた足で押さえる。黙ってしまったわたしに気をつかってか、ドクターは頭をかいて、自分のことを話しだした。
「僕も、昔の夢を時々見るんですよ。ビジターズが来る前の頃の夢を」少しためらったあと「南アフリカの、ソエトにいました」
「ああ――」
「ひどいものでしたよ。すぐ近くに発電所があるというのに電気さえ引けない家で、土間に寝て、父親は失業して酒びたり。そういえば、金曜日の晩に強盗の真似ごとをしたこともあったっけ」
「まあ、あなたが? 信じられない。他にご家族は?」
「弟が一人、結核で早く他界しました。母は――」つばを飲んでから「バーで、【売春/フルージイ】を……」
わたしは目を閉じた。「――ごめんなさい」
「いえ、いいんです」大袈裟に手を振り、笑顔をつくってみせる。「もう七年も前のことです。今なら笑って話せる時代の話ですよ。でも、今でもあの頃のことを夢に見て、うなされるんです。そして朝起きて、自分が暖かなベッドの中にいることを確認して――いまさらながらにビジターズに感謝するんですよ。彼らが地球を訪れなかったら、僕はまともな教育も受けられず、のたれ死んでいたろうって。それが今や、ステーションの医者ときた。あの頃からすれば、今の方が夢のようだ」
おどけてみせた彼に、わたしも微笑んだ。「ビジターズの力だけじゃないわ。あなたの努力があったから――」
わたしは最後まで言えなかった。横の通路からブロンドの白人女性が、息を切らしながら転がりでてきたのだ。目は落ちくぼみ、乾いた唇はめくれあがっている。肉のそげた腕は骨格と腱が浮いていた。彼女はわたしたちを見上げると体を硬直させ、つぶやいた。
「【お願いです/プリーズ】。【見逃して/カナイブ】――」
「どこに逃げた!」
奥から飛んだ声に、ドクターは間髪を入れず怒鳴った。「ここにいるぞ!」
「いたぞ!」
駆けてくる足音に、彼女はよろめきながら立ちあがろうとしたが、ボロボロに破れた自分の作業衣に足をとられ、その場に前のめりに倒れてしまった。
「こいつ!」追いかけてきた、まだティーンエイジャらしい黒人兵は、彼女の背を踏みつけると、髪を無造作につかみ、ぐいと引きあげて、顔面を勢いよく壁に叩きつけた。「このブタ野郎が」
「ぐっふ……」血に濡れた歯が落ちる。彼女の手から何かがこぼれた。干からびた、リンゴの芯だった。「――許し、許して下さい。子供が、子供がいるん――」
「これが欲しいのか。あーん?」後ろからのっそりと現れたもう一人の兵は、ニヤニヤしながらそれをつまみあげ、血が溜まっている彼女の口をこじあけると、それをねじこんだ。「遠慮すんなよ。おら、食えよ」
「う、が、ぐ……」
「食えってんだよ!」リンゴの芯をくわえさせられたまま、何かを言おうとしているその白人女性の口をめがけ、彼は思いきり蹴りをいれた。
「あびしいっ! あぐあ、あぐが……」彼女の顎が不自然に横に広がった。
「やめなさ――」
止めに入ろうとしたわたしの腕を、誰かが強くつかむ。ぎょっとしてその主を振り返る。ドクターだった。彼の目を見て、わたしは息を呑み立ちすくんだ。それはさっきまでの、暖かい穏やかな好青年の目ではなかった。行為を直接下していない彼の黒い瞳には、兵士二人のそれに勝るとも劣らない攻撃心、憎悪――殺意がたぎっていた。
顎を押さえ、金髪を自分の血で朱に染めながらのたうち回る彼女を、兵士二人はなお執拗に蹴り続けている。
「お前ら、お前ら【非有色人種/ノンカラー】はな、生きて、生きていられるだけで贅沢なんだよ! ああ、何とか言ってみろよ!」
たまらず、わたしは叫んでいた。「もうやめて!」
「そうだな、もうやめろ」ドクターが冷たい声で言う。「床が血で汚れる」
「けっ!」忌々しげに若い兵が最後の一蹴りを脇腹に加えると、彼女は口と鼻からばっと茶色い液を吹き出して、それきり動かなくなってしまった。兵は彼女の頭を足で転がすと、髪をつかみ、もときた通路へとひきずっていった。
「どういうことだい。ここにあんなのが出るなんて」
「いやあ、先生、どうもね――」残った兵は方をすくめ、舌打ちをする。「飯ほしさに、ダストシュートを伝って入ってきたらしいんですよ」
「監督がなってないな」
「まったく、すいません」
一礼すると、彼は壁の受話器を取りあげてどこかと何事か相談し始め、ドクターに促され、わたしたちはまた歩きだした。
「いやなものをお見せしてしまって」
「ええ、本当」
「驚かれたでしょう。【有色人種専用/カラードオンリー】が鉄則のステーションに【非有色人種/ノンカラー】がいるなんて。ここでは公然の秘密なんですよ。あれは作業夫なんです」
「ああ、噂では聞いたことがあるわ」
「僕なんかはあんな連中、入れなきゃいいと思ってるんですけど、なにぶん安い労働力だそうで、機械の維持費よりも安くつくそうですよ。水さえやっとけば、死ぬまで働きますからね、あいつらは。危険な船外作業や、原子炉なんかは連中に――」
わたしはうつむき、寝息をたてているペリジーを抱き直した。耳をふさぎたい思いにかられた。わたしが受けた嫌悪感は、喋り続けるこの青年の共感を呼ぶようなものではなかった。
これで、良かったのだろうか――。
過去は、後悔するためにあるのではない。しかし、現在に対しその責任を負っている。
なぜ、こんなことになったのか――。
わたしは、一週間前の、あの日のことを思いだしていた。
(第2章へ続く)