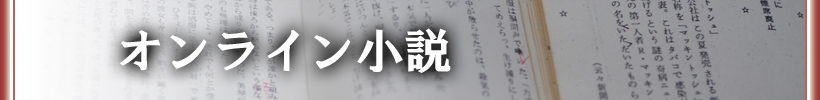オンライン小説
●第3章
叫ぼうとしたわたしの口は、そのときはもう暴漢の手によって塞がれていた。
「貴様!」
残った護衛が、脇のホルスターから銃を抜く。その腹を男は蹴りあげた。
つばきを吹きだし、彼は道に倒れ、落ちた拳銃がくるくると回る。その間に男はわたしを後方にひきずっていった。
「“助けて”と叫べ」
「え!?」とっさに、わたしはささやいた彼の意を解し、叫んだ。「助けて、助けて!」
腹を押さえながらも銃を拾い、追いかけてきた護衛が、近くの車の後部座席から狙われているのを見て、演技抜きにわたしが悲鳴をあげたときには、護衛は腹に弾丸を撃ちこまれていた。
もがき、身をよじるわたしを、男は有無を言わせずその車へ叩きこむ。ヒールの片一方が転げ落ちた。待っていたドライバーがスロットルを開けたのと同時に、彼も飛びこみ、素早く窓にカーテンをかける。運転席側も仕切られていて、通行人の反応を見ることはできなかった。
中で待っていた援護役の男――金髪に青い目、高い鼻、典型的な白人だった――が、ライフルを座席の下に置くと、わたしの名を確認した。「間違いないな?」
「ええ。来ないのかと思っていたわ。非道いことをするのね、彼らには罪はないのに」
「はっはあ!」わたしを“誘拐”した男が、豪快な笑い声をたてる。「死なねえよ、あのぐれえじゃあ。これを見な」
汗臭いTシャツをめくり上げると、その黒い肌の腹には、いくつかの手術創が残っていた。
「どうだい。俺あ腹に三発、胸に一発くらったことがあるが、まだこうして生きているぜ。【連中/ビジターズ】が教授した、進んだ医学ってやつでな」
「あなた――本物の【有色人種/カラード】ね?」
「おうよ。この肌は硝酸銀で焼いたんじゃないぜ。PCI、ICC共に陽性の、生まれつきの【黒人/傍点】さ」ふん、と鼻を鳴らし「すべての黒人が、連中のやり方に賛同している訳じゃない」
有色人種、と言わずに、自らを黒人と言った彼の口調には、誇りが感じられた。
「そう――」多少なりとも、救われた気分だった。「ゴトーに会わせてくれるのね」
「罠じゃないとわかったら」
「どうやって確かめる気?」踵から血がにじみ、わたしは顔をしかめた。
白人がドライバーに訊ねる。「追手は?」
「いない。今のところ」
「なるほど」
「やはりな」わたしをはさんで、二人はニヤリと笑い合う。「じゃ、やるか」
左に座っていた白人の男が、わたしの喉に手をあててきた。その手はすぐ下におり、ブラウスのボタンを外すと、胸もとに滑りこんでくる。異様に冷たい感触に、わたしはぞっとした。
「なにを――」
「動かないで」
そのまま手を沈めていく。下着越しに伝わる硬い感覚に、わたしは目を閉じた。
小さな電子音が鳴る。彼はそこで手を止め、息をついた。
「あったぞ。やっぱりな」
「どこだ?」
「胃だろう」引き抜いた彼の手には、小さな機械が握られている。鳴っているのはそれだった。
「胃か、そいつあ助かった」
「どういうこと?」
訝かるわたしに、黒人は錠剤とドリンクをつかませた。「飲んで、時間がない」
黙ってそれを喉に流しこむと、とたん、猛烈な嘔吐感が襲ってきた。
「ほらきた」
渡された袋の中に、逆流してくる酸っぱいものを吐きだす。独特の刺激臭が鼻をついた。出がけに何もとってきていなかったので、固形物はほとんど出てこない。
息をついたわたしに、どちらかがタオルを握らせてくれる。それを口にあて、呼吸を整えているわたしをよそに、男二人は汚物を入れた袋に例の機械を触れさせていた。何度か角度をかえると、さっきと同じ音が鳴り、二人は低く笑声をたてた。
「どういうこと――」
「はっは。教えてやろうか。RRBの局長夫人が白昼堂々誘拐されて、なぜ追手がまったくこないと思う」
「あなたたちが考えているほど、わたしは重要人物じゃないだけよ」
「違うな。今この車は、大勢の目に見つめられてるんだぜ。静止軌道上のスパイ衛星を経由して。あんた、今朝は何を食った?」
「何も――」
「ピルは?」袋の口をしばりながら、青い目の男が無表情に訊く。わたしはうなずいた。「それだよ。錠剤の中に超微型の発信器が仕込んであった」
「まさか……」
「今までに何度も痛い目にあってる。とっ捕まった仲間が、警備の手が薄くなった隙に逃げだしてくる。近くのシンパと連絡をとって、アジトへ戻る。そこで十分もしないうちにRRBが乗りこんでくるという寸法さね」
「今だって胃でよかった。俺たちゃ、ここであんたに【おまる/傍点】を使ってもらうことも覚悟してたんだ」
「……衛星からでも捉えられる【信号/シグナル】なら、服の上からやってほしかったわ」
「それを言うなら、ボディスーツなんぞ着ないでほしかったね、こっちは」
眉をしかめたわたしに、やりとりを聞いていた黒人が陽気な声をたてた。
「こいつを誤解しないでやってくれよ。エンジニアあがりでね。ゴトーと並んでお堅い奴なんだぜ」
「俺の機械では薄手の布一枚越しに信号を捉えるのがやっとなんだ。旧式のチップしか使えないからな。ビジターズのレベルとは違うよ」
「そう――ごめんなさい」
「いや」真面目な顔で、彼はこう応じた。「残念だったな。日本人の肌は【きめ/傍点】が細かいってんで、期待してたのに」
「まあ」
二人は目配せし合った。
「あんたを信用しよう。別の車に乗ってもらう。一応目隠しをしてくれ。その方が後で言い訳に困らないし、【恐くないだろう/傍点】」
「何をするの?」
「こっちは止まる訳にはいかない。だから――放りだす」目隠しをわたしの頭に回し、きつく縛る。「一分もかからない。かかったらまずいんだが」
周囲が暗くなるのを肌で感じた。音がこもって聞こえる。彼らはわたしの体を抱き上げ、外に放りだした。全身をふわりと何かが包みこんでくれる。確かに目隠しのおかげで何が何だかわからず、それほどの恐怖心は湧いてこなかった。走り去る車のエンジン音が反響して聞こえる。トンネルだろうか。何者かに腕をつかまれ、緊張していたわたしは、思わず悲鳴をあげた。
「大丈夫、大丈夫。彼らの仲間よ、連絡は受けてるわ。心配しないで。こっちへ」女の声。誘導されて、二、三歩進む。「乗って」
別の車らしかった。シートの感触が柔らかい。外でさっきの女性が何事か誰かに指示している。
「マットを片づけておいて。あたしは先に行くわ」そして乗りこみ、前に声をかけた。「出してちょうだい」
車はどうやら今までとは逆方向に走りだした。目隠しが細い指で外される。やがて視界が戻ってくると、そこに映ったのは、ブルネットの白人女性であった。
「大丈夫?」
「ええ。でも見事なお手並。一分どころか、三秒もかからなかったんじゃない?」
「もう少しね」それから、手振りで、“吐いたか”と訊いてきて、うなずくとハンバーガーの包みを見せた。
「ごめんなさい。食欲はないわ。何か飲む物はないかしら」
「そうくると思った」にっこりと微笑むと、ドリンクを手渡してくれる。それを乾いた喉に流すと、やっと人心地つき、わたしはシートに背をもたせかけた。
「手荒なことをされなかった? 一人、気が荒いのがいたでしょ」
「いいえ、久しぶりに、本当の紳士に出会えた気分よ」
「あっは。あいつに聞かせてやりたいわ。そうすればもう少し、大人しくなるかもね。もっとも大人しくなかったから、生きのびられてきたんだけど」
煙草を取りだし勧めた彼女に、わたしは手をあげて辞退した。
「あたしが【連中/ビジターズ】に感謝するとすれば、ガンの特効薬を持ってきてくれたことだけね。それだけはほんと、表彰状を送りつけてやりたいぐらい」
「さっきの人たちは、これからどうするの?」
「発信器のこと、聞いたでしょ。これから逆に【連中/ビジターズ】をぎゃふんと言わせてやるんだ、っても――」笑いながら溜息をつき「この程度のことじゃ、痛くもかゆくもないだろうけどね」
それきり、話すこともなく、わたしたちはお互いに口をつぐんでしまった。この車もルートをわたしに知られないよう、窓に目隠しがしてあるので、景色を眺めていることもできない。手もちぶさたに、わたしは一人爪をいじっていた。
「靴はどうしたの?」
「靴!? ああ、さっき落としてしまったらしいの」
「そう。じゃ、シートの下にサンダルがあるから、それ使って」
「ありがと……」
シートの下を探っていると、また彼女が話しかけてきた。彼女にしても、間が持てないのだろう。「何か話そうか。ここからまだ遠いから。あなたが嫌でなかったら」
「ええ」わたしはうなずいた。
「――そうね。あなたの現在は問わないわ」
「訊かなくても、ご存知でしょう?」
「まあね。双子のお子さんはお元気?」
「ええ。おかげさまで」
「あなたは昔、ゴトーの何だったの? ステディ?」
首を振ってみせる。「友人だった。それだけ。一緒になろうと思っていた人は、別にいたわ。わたしたち三人は同じ研究室にいて、ゴトーはいい先輩だった――」
「そう」
「あなた、ゴトーの?」
「あはっは」彼女は噴いた。「まさか、あんな堅物。でも――。彼はみんなから好かれているわ。でなけりゃ、あたしたちがついていく訳」
「そうね。彼らしいわ」
「ゴトーは昔、どんな人だった?」
「うん……。あんまり外見こだわる人じゃあ、なかったわね」
「不精ひげに曇ったメガネ。ヘビースモーカーだけど酒は一滴も駄目。汚れた一張羅のポケットにそのまま現金を入れて、すり減ったサンダルの踵をすって猫背で歩くと、小銭がちゃらちゃら音をたてる――」
「驚いた。ぴったりよ」
「驚いた。あたし、今の彼を言ったのよ」
二人して、顔を見合わせ、くすくす。変わっていない。昔のことを思い出しかけ、わたしはうつむいた。
「……悪い話題だったかな。ごめん。そうね――映画は好き?」
「この頃は全然。劇場からは足が遠のいちゃって」
「それは同じよ。と言っても、立場が全然違うけど。こっちは劇場なんて入れない、【貴族階級/傍点】ですものね。先週ディスクで見たんだけど、なんだっけ、古いSF映画で、知ってる? うーん――題名をど忘れしちゃった。へんな宇宙人が地球に来る話」
「そういう話は、腐るほどあるでしょう? 数えたことはないけれど」
「そりゃそうね。でも感動的な話なのよ。白人の少年がね、その宇宙人を追っかけ回す科学者連中の手からかばって、宇宙に返してやるっていう」
「――ロマンティックなお話」
「でしょお。たまらないわ。あたし、思わず泣いちゃったわよ。あの映画製作者たちに見せてやりたかったわね。地球に降り立った最初の異星人の姿を。鼻は高くて彫りは深くて、すらりと伸びた長身と長い足に、ぴしっとキメた黒髪の、とってもハンサムな【黒人青年/傍点】の姿をね。それとロマンティストのカール・セーガンに。彼が今の地球を知ったら、【地球外生命探査/セテイ】なんてやると思う?」
わたしは笑った。「返答に困るわ」
「結局どんな科学者も、SF作家も見抜けなかった訳よ。訪れた異星人が、見かけはおろか遺伝子構造まで地球人と同じなのに、肌だけ黒かったなんて。それも全員が全員。しかも肌のなまっ白い人間がいることを知らなくって、嫌悪感を覚えるだなんて――。連中のショックって、あたしたちが緑色した人間を見たようなものなのかしら。当たってたのは、彼らが発達した科学力を持ってるってことぐらい」
饒舌な彼女に、どう応じたものか、わたしは力なく合槌を打った。
「子供の頃、歴史の教師がね、ことあるごとに言うのよ。“歴史は繰り返す”ってさ。ほんと、連中のやってることって、新大陸で白人がインディアンにしたことと、おんなし」
「同じなんてもんじゃないわ」
「――そうね。連中って、なんてまあ、ものすごいヒューマニストじゃない? 今じゃ戦争の恐怖も、飢餓の心配も、エネルギー危機も、疫病の流行も、なんにもありゃしない。味気ない世の中にしてくれちゃって。あはっはは」
「うふふ」
おかしくもないのに、笑い合う。ふと、彼女は目を伏せ、かぶりを横に振った。
「……笑って話してるけど、ほんとはとってもつらいのよ。旦那と子供が、殺されてるの。七年前にね。南アフリカにいたわ……」
ビジターズは、アパルトヘイト政策を緩和することを拒んだ南アフリカで、まず最初の革命を起こさせた。黒人たちに未来を約束し、武器を与え、白人政権を潰滅させたのだ。そして彼らは、世界に向けてこう宣言した。我々は有色人種の味方である、と。
連鎖して闘争に目覚めた黒人たちに武器を与える一方でまた、議会において三分の二以上の有色人種議員を有するか、あるいは最高指揮官を有色人種にしなければ、一切の経済、科学技術、医療技術、そして軍事力の援助はしないとし、二年後ビジターズが裏で手を回して、アメリカ合衆国に初の黒人大統領が誕生してから、人種隔離法案――白人はいわゆる先天性メラニン欠乏症、つまり白子という人類の奇形なのだから、人間たる有色人種の遺伝子プールを守るため、隔離せねばならない――が議決されるまで、そう時間はかからなかった。
「……連中が来てから、たった、たったの七年よ。どうしてこんなことになってしまったの?」膝にぽとりと涙を落とした彼女の横で、小さくベルがなった。「……ごめん。取り乱しちゃって。もう着くわ」
「――そう」
車が止まる。彼女が自分の側の扉を開け、サンダルをはいたわたしを誘導した。そこは暗く、オイルの臭いが漂っている。どこかの車庫らしかった。
彼女に案内され、薄暗い通路を渡る。二人とも無言のままに。彼女にどう声をかけても、それは慰めにはなるまい。
いくつかの符牒を白人の男たちと合わせ、彼女はつきあたりの扉の前で立ち止まった。カードをパネルに挿入し、暗証をなぞる。そして振り返った。
「ここにゴトーがいるわ。あたしはここで返るから。そのうち、あなたとゆっくり話したいわね」
「ええ。わたしも」
「戦争におびえ、飢餓に苦しみ、エネルギーは渇し、疫病が大流行してる時代になったらね」
わたしは微笑み、うなずいた。
「じゃあ」
彼女の後ろ姿を見送り、そしてわたしは扉を開けた。そこに、ゴトー、後藤がいた。
(第4章へ続く)