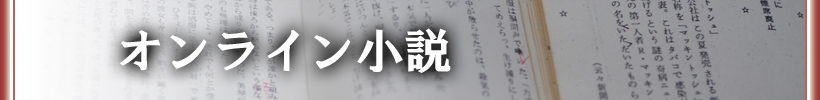オンライン小説
●第4章
彼はおぼつかない手つきで、コンピュータの端末を操作していた。訝かってわたしは目をこらした。わたしの知っている後藤は、一分間に六十ワーズを打てる、タイプライタの名手だったから。そしてわたしは胸がつまった。彼の左腕は、肩から消えていた。
「何をぼさっとつっ立ってるんだ。ドアを閉めろよ」
「……その腕は?」
「いろいろあったのさ。お前さんなんかには想像もつかない」
「今の医学なら、継ぐことも可能でしょう?」
「神経までズタズタでね。最初の処置もまずかった。座れよ。お前さんは変わらんな。人に言われなきゃ、なんにもできんのか」
「あなたも変わらないわ。その言い方」
天井から音がこぼれてくる。彼がインターフォンを操作すると、その曲が大きく漏れてきた。
Now, woke up this morning,
couldn't hardly see
Snow on the ground fell 8 feet deep
「コーヒーを一つ。そう。ブラック。それと――」わたしを見、訊く。「何がいい?」
「頼めれば、アイスティを」
「アイスティを」
フォンを切ると、天井を顎でしゃくる。「【秘密酒場/スピーク・イージィ】になってる」
「“今朝 目が醒めたら――”か。ブルースを聞いたのは、久しぶり」
「いい声をしてるだろ。それに情がこもってる。あれを歌ってるのは、白人だぜ」
彼のデスクの横で、小さな窓が開き、そこから盆に乗ったカップとグラスが、誰かの手によって押されて出てきた。後藤は右手でグラスを取ると、わたしの前に運んだ。
「何年ぶりだ」
「そうね。三年。あなたの名をリストで見た時には、目を疑ったわ。あなたがこんな運動をしているなんて」
デスクに戻り、カップを取り上げると、視線をよこす。ぼさぼさの不精ひげ、毛髪は色が抜けている。口調は乱暴だが、誰にでも好かれる人だった。それは今も同じよう。しかし昔その奥で、優しさをひそませていた瞳は、今は険しく変わっていた。
「その三年の間に、立場は変わったがね。昔お前さんは、俺にからかわれていつもピィピィ泣いてた癖に。今や俺の方が苦しめられてるときた」
「……わたしを憎んでる?」
「誰も、お前さんを憎んだりしちゃいない。奴だって、もうお前さんを覚えちゃいないさ」
「お願い。あの人のことを教えて」
彼は目をそらし、ほっと溜息をついた。「東京にいる。結婚して、子供もいるそうだ。一回手紙がきたよ。とても幸せそうだった」
「そう」わたしはまぶたを落とした。瞳が熱かった。「それは良かった――」
「良かったさ。最高に。お前みたいな、連中に体を売るような女と、一緒にならずに済んだんだ」
「――わたしが、どんな思いで、あんな黒ン坊に抱かれたか、あなたにわかる?」
* *
その晩は、どしゃ降りの雨だった。黒いしずくに打たれ、あの人のアパートにたどり着いた頃には、わたしは全身濡れねずみになっていた。
彼は驚いて、どうしたんだ、と訊いた。彼の顔を見たときから、わたしは声をあげて泣きだしていた。
「あなたと後藤さんが帰ったあとに、あの黒ン坊が入ってきて、あいつ、あいつ――あたしあいつに――」
その後は、言葉にならなかった。言う必要もなかった。彼は泥だらけのわたしを抱きしめた。
「僕が悪かった。僕が、僕が君を残して帰ったりしなければ……」
雨の音がうるさい、湿った夜だった――。
* *
その数週間後、わたしはまた彼の部屋を訪れていた。
「プロポーズされたわ」
「……あの黒ン坊に?」
わたしはうなずいた。
「それで?」
「受けるつもりよ」
「そう……」
「怒らないの? 殴ってもいいのよ」彼は悲しい目をして、黙っていた。わたしは彼に、にじり寄った。「怒ってよ、ねえ、殴ってよ。あたしを殴って。それであなたの気が済むのなら」
彼は急にわたしの両肩をつかみ、そして――平手のかわりに、そっとキスをした。
「僕が、君を殴れると思うかい」目を閉じると、うつむき、背を向けた。「今になって、やっとあの黒ン坊が派遣されてきた意味がわかるんだ。政治的な意図が。研究施設の視察なんて、名目だ。先月はニグロの女と婚約発表した奴がいた。そして今回は――」
「そういう意図がないとは、あたしも言わないわ。でも――あたしにどうしろと言うの? まだ非公式だけど、断る訳にはいかないわ。圧力がかかってきてるのよ。今のあたしには、死ぬ権利さえないのよ。ここに来るのでさえやっと……」
「わかってるよ……」
わたしは唇を噛み、できるだけ、明るく言ってみた。「それに、あの人も決して悪い人じゃないと思うの。一緒に暮らしていれば、いつかは愛せると思うの」
しばらくしてから、彼は一言だが、きっぱりと言った。「――信じないよ」
部屋から出るとき、わたしはドアを閉めながら小声で、愛しているわと、つぶやいた。彼の返事は聞けなかった。
道に出て二階の彼の部屋を見上げると、彼は窓から、そっとわたしのことを見ていた。悲しい目だった。わたしは無理をして微笑むと、手を振った。バイバイ、と。
* *
後藤は目を下げた。
「――言い過ぎた。謝る。わかっているんだ。本当はわかっているんだ。連中の求婚を断れるような時代ではなかった」
「今もそうよ。その時代は続いていくわ」
「――今日は何のために来た?」
「彼らと話し合ってほしいの。わたしが仲介してあげてもいいわ。いいえ、そのつもりで来たのよ」
「話し合え!? 正気か? はん、莫迦を言え」
「彼らだって、このまま永久に白人を閉じこめて、うまくやっていけるとは、思ってやしないわ。最近はKKKや“兄弟同盟”の活動も活発になってきているし、GT計画だって、完遂の見込みはないのよ。木星の恒星船だって未完成だし――」
「GT計画? は。あれは何の略だい。【いんちき/ジップ】トリックかい? 【偽善の罠/グッディトラップ】だったか?」彼はわたしの顔色を伺った。「知らんらしいな。さすがにこれは【寝物語/ピロートーク】でもでなかったか」
「からかわないで、なんだって言うの?」
「二週間後、GT計画の最初の“移民団”はステーション202を離れるはずだ。木星へ向けて。だが、そううまくはいかない」
「どういうこと?」
「青写真を教えてやろう。彼らの乗せられた船は、もっと近い人間の住める惑星へ降りる。わかるか」デスクを指で硬く叩き「ここ、地球だよ。場所は【南/サウス】オーストラリアのウーメラ、ナランガー基地。パイロット、移民団共々、造反を起こすんだ。彼らはそこを占拠するのさ。ナランガーには核がある。そして彼らは汎用周波数を使ってビジターズに通告する。非有色人種自治区の白人たちすべてを解放しないと、核の無差別攻撃を行う――とな」
「まさか――本気でそんなにうまくいくと思っているの?」
「俺に訊いてもらっても困る。これは【ビジターズが企てた/傍点】シナリオなんだからな。続きを教えてやろう。汎用周波数で流れた脅迫は、十分もしないうちに全世界のマスコミに伝わる。ところがその十分のうちに、ビジターズの連合軍はナランガー基地に降下、反乱軍を全員射殺する。家庭のテレビにはこんなテロップが流れるのさ。“移民船の【協力者/コーペレータ】がオーストラリア、ナランガー基地を占拠、詳細は不明”その数分後にはビジターズの力によって、それが解決したことがね」
わたしには言葉もない。後藤は続けた。
「その翌日からマスコミに乗る情報は、ちょっとしたもんだぜ。造りもののホラー映画なんぞ相手にならん。カメラに映るのは、腹を裂かれ、内臓をはみださせたまま死んでいる黒人兵、目をえぐりだされ、手足が異様にねじまがったまま転がっている士官、口から尻まで鉄パイプを突き刺され、吊るされているオペレータ――。善良な市民は目をそむける。そして怒る。やったのは誰だ。移民船の白人の連中だ。白人ってのは、なんて奴らだ。人間じゃない。人間の皮をかぶった獣だ。ってな。そしてその白い獣を自分たちから隔離してくれたビジターズのお株はまた上がるという訳だ」
「まさか!」わたしは叫んでいた。「そんな恐ろしい計画が成功する訳がないわ!」
「甘いな。連中には実績があるんだぜ。二年前のチリ大地震を覚えているか? そのときのことを。第二十三非有色人種自治区の白人たちが、崩壊した壁を乗り越えて市街に脱走し、暴動を起こした。一時間後にビジターズによって全員射殺されたあの事件を」
「あれもビジターズが仕組んだというの」
「地震を起こしたのまでがそうだとは言わん。だが連中は知っていたはずだ。かなり大規模な地殻変動が起こることを。その数時間前、自治区の白人たちは向精神ガスを吸わさせられていた。このガスの効果はすごいぜ。視床下部に刺激を与えて、猛烈な“怒り”を起こさせる。飢えた野獣になるのさ。崩れた壁から溢れでた白人たちは、数名の煽動に乗って、市民を殺して回った。ただこのガスの難点は、効果があまり持続せず、神経がやられちまうところだ。そこをビジターズは狙い撃ちした。簡単な話だ。もっともこのときは、計算以上にガスの効果がありすぎて、市民が死にすぎた。その分リアルだったがね。今回はもっと安全だよ。ガスは使わない。舞台はみな揃ってる。核の凍結を宣言したビジターズが、なぜ所々それを残しておいたと思う? 猿芝居の大道具にするためさ。移民船には実際にはパイロットはいない。【航法/ナビ】コンピュータの【自動操縦/オートクルーズ】だ。乗せられた“協力者”たちは、訳もわからないままにナランガー基地に着陸する。そこにはビジターズの兵がいて、彼らを下ろさせる。あたりには血にまみれた黒人兵が転がっているときた。ビジターズが前もって殺してさしあげておいたのさ。あとはハンティングだ。無線は【やらせ/傍点】だよ。これがGT計画の全貌だ。【大したもんだぜ/ジンジャーピーチィ】」
「まさか、嘘よ、嘘よ。なぜそんな恐ろしいことをしなければならないの」
「理由は明快だ。“共通の敵”をつくるためさ。連中が地球人と同化するために」彼は立ち上がり、サンダルを床にすりながら歩き始めた。「二次大戦が終わったとき、進駐軍はまず何をした。戦犯をつくることさ。戦犯を連合軍と日本の一般市民の“共通の敵”につるしあげて、我々は君たちの敵ではなかったのだ、味方だったのだ、我々が闘っていた相手は実は戦犯たちに他ならなかったのだとアッピールした。ビジターズが何の手も打たずに、地球に訪れたらどうなっていたと思う? それこそ大国間の“共通の敵”にされてしまうか、あるいは片一方とうまくいったとしても、決して【うまみ/傍点】はない。連中の目的は、テクタイトの壁に囲まれた空間に住むことではなく、この自然に溢れた地球に移住することなんだからな。これこそ連中が十世紀の時間を宇宙で過ごしてきて、望んできたことだ。たとえ片一方とうまくいったとしても、そのせいで地球の生態系を破壊してしまう可能性を持つ緊張を、この世界に張り巡らしてはいかん――しかし連中は頭が良かったよ。“共通の敵”を造るのに、イデオロギーではなく、肌の色を選んだ。連中の顔つきを見てみろ。鼻は狭く高く、唇は薄く、彫が深い。毛髪は直毛か波状。色を別にして見れば、連中の風貌はアングロ・サクソンに近い。白い肌が人類の奇形だ何だというのは、方便に過ぎんのさ。連中は地球の【片一方/傍点】ではなく、【内部/傍点】に敵を造る必要があった。しかも日頃抑圧されている者たちの方が味方につけやすい。そこで自分らと共通している、一目でわかる黒い肌を選んだ。もし中国という、膨大な人口をを抱えた黄色人種国がなかったら、連中は黄色人種をも狩ったかもしれんのだぜ」
立ち止まり、咳こむと、続ける。
「連中のもくろみはまんまと成功しただろうが。小惑星から採掘した【希少金属/レアメタル】を市場に放出し、南アフリカを経済的に孤立させ、世界中の世論に乗ってそこの黒人たちに革命を起こさせた。祝辞の言葉がふるってたぜ。“我々は資本主義の味方ではないし、社会共産主義に迎合する気も更ない。しかし、有色人種を差別することだけは【許さない/傍点】”とな。この許さないってのがミソさ。人は集団になってこそ、その持っている偏見を乗算していくんだ。一人一人は決して差別をいいことだとは思っていない。ビジターズにまっこうから反論してきた世論があったか? 有色人種を差別することを許そうじゃないかという意見が出たか? 肌に色がついていたことでコンプレックスを抱いていた者たちは、一斉にビジターズを歓迎したろうが。彼らは白人を除外して集団となり、その白人への偏見と狂気を増幅させ、そして――」
言葉を切る。上からさっきの曲が、ぱらりぱらりとこぼれてきた。
Lord I'm lost,
baby what gonna come of me
You know I feel just like
easin' back down into Tennessee...
「今朝、目が醒めてみたらどうだ。今や世界は黒一色だ。子供に訊いてみろ。白人はどういう人種か。二つの世界大戦を始めたのは? 白人だ。新大陸でインディアンを殺したのは? 白人だ。原爆を造り、日本の有色人種を殺したのは? 白人だ。すべての悪の元凶は? 白人だ。では我々の敵は誰だ? 白人だよ。その証拠に白人を隔離したらどうだ。今や世界に戦争の恐怖はなくなり、飢える者はおらず、平均寿命は伸び、週に三日働けば、人並みの生活ができる。みな口々に言ってるだろうが。ビジターズはキリストの再来だと。弥勒だったと。決して連中が敵だとは言わん」
わたしは全身から力が抜け、椅子に背を丸めていた。
「話し合え、と言ったな。ビジターズと【話しあって/傍点】、うまくやっている白人たちがいるのを知ってるか? お前さんがさっき言った、活動のお盛んなKKKと“兄弟同盟”だよ。連中はビジターズと契約し、たまに白人の騒乱劇を演じてみせる。チリの自治区で、黒人を殺せとアジテーションしたのもあいつらだ。白人が、いかに危険な存在か、またビジターズがいかに市民のために白人と闘っているかを市民に印象つけるために――」
「もうやめて――」
後藤は、わたしの前に腰を下ろし、静かに言った。「……わかったかい。お前さんの考えてることなんぞ、どだい無理なことなのさ」
その口調は、わたしへの侮蔑ではなく、彼自身へのあきらめの言葉のようだった。
「――そんな恐ろしい計画を、あなたたちが指をくわえて見ているとは思えないわ」
「もしなにか考えているとしても、お前さんに言えると思うかい?」
「わたしだって知っていたわ。自分の言っていることが甘いことだって――」わたしはポケットから、一枚のメモリカードを出し、彼に渡した。「これを……」
「む――」受け取り、デスクにつくと、即座にそれを端末に入れる。左手の雨だれ打ちでキィボードを操作し、ファイルを開くと、彼の口も開いた。「ほーう、ほほう。なるほど――」
「役に立つと思うわ」
「どうやってこんなものを手に入れた。極秘事項だろう」わたしを見て「罠かもしれんな」
「RRBは、局長婦人を使ってまで、あなたたちみたいな弱小の解放組織に罠を張るほど、情けなくはなくてよ」
「それはそうだな」
「それに――、わたしもあなたたちと行動を共にしようと思っているわ」
「それは駄目だ」
「どうして!? わたしが一緒なら――」
「俺たちだって、RRBの局長婦人に頼らなければなにもできないほど、おちぶれちゃいない」
「プライドが高いのね。変わらないわね。罠ではないという保証がなくなるわよ」
「お前を信用する」
その一言が、今のわたしには何よりも嬉しかった。
「あと二週間ある。同志を募って、久しぶりに旅行といくか」
「ステーションからの地球の眺めは最高よ」
「ハネムーンには向かないぜ」
「期待しているわ」
後藤は笑ってみせた。ここにきて、初めて見た、本当に優しい笑顔だった。
「お前さんはもう帰れ。送らせる。なんて言い訳する気だ?」
わたしも笑ってみせた。「泣いて泣いて泣きまくって、ごまかしてみせるわよ。結婚してからこのかた、得意になっちゃってね。実績があるのよ。ほら、もう……」
「そうか――」体を部屋から出しかけたわたしを、彼は呼び止めた。「……ありがとう」
扉を閉め、わたしはそれに寄りかかった。迎えの男たちが歩いてきていた。わたしは涙ぐんでいるのを悟られないように、うつむいて従った。