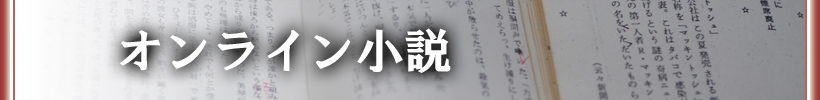オンライン小説
●最終章
地球採光室で食事をとり、そこで眠ってしまった子供二人をドクターに連れてきてもらい、私はあてがわれた個室に戻った。この部屋から見える地球も、ステーションが重力をつくるために回転しているので、重心のずれた円板が飛ぶようにゆっくりと回っている。
二人をベッドに寝かしつけ、わたしは地球を眺めた。地球は青かった。これは過去形ではない。今も青い。そして未来も。
ステーションの回転に、地球からの定期便のオービターがシンクロしているのが、頭上の方――ステーションの中心部に伺える。あの人が住んでいる日本を、青い地球に探したが、それは、わからなかった。
“協力者”の移民船がここを離れるまで、あと一週間しかない。彼らはもうすでに乗り込み、船内に閉じこめられている。後藤たちはどう出るつもりなのだろう。ここに来るまでに捕らえられてしまうことも、大いにありうるのだ。もしかしたら……。
わたしは彼らのことを思うのをやめようと、オーディオのパネルを開けた。用意されたディスクの中に、パッヘルベルのカノンがあるのを、指が無意識に探りだし、気づいたときには、それをトレイに乗せていた。
それ一曲をエンドレスにして、わたしはベッドに腰を下ろし、ペリジーの髪を撫でた。双子の兄妹の肌は、黒くはない。モンゴロイドの特徴を、二人は現し始めている。ビジターズと地球人との混血として、二人は産まれたときに厳重な検査を受け、遺伝的にも完全に、夫のものだと証明された。――検査そのものは、それが目的ではないことは、言うまでもない。地球人と彼らの混血が可能であるか、奇形になる可能性はないかといったことが重要だったのであり、その結果、わたしが密かに持っていた希望が、科学的に打ち砕かれたというだけのことなのだから。
わたしが切なさにペリジーを抱きあげようとしたその刹那、淡い【地球光/アースライト】に染められた背後の扉が開いた。振りむく間もなく、男の声が飛んだ。
「両手を上げろ! そのままゆっくりとこっちを向け!」
わたしは従った。「来ていたのね。あなた、後藤の仲間ね。わたしはあなたたちの敵じゃないわ」
そこにいたのは、スペーススーツを着、小銃を構えた一人のゲリラだった。彼はわたしの顔を見ると、首を横にゆっくりと振り、後ずさった。扉が連動して、再び開いてしまう。「君は……」
「何をやっているの。扉が開いてしまうわ」
彼はわたしの言葉を聞いていなかった。ヘルメットのフェイスプレイトを上げると、わたしに目を向けた。
「あなた――」
「まさかこんなところで、君と会えるとは――」
「あなた――」
言葉にならなかった。言葉にならない想いが、胸をかき乱し、そのときはもう、彼に抱きついていた。彼はわたしを受け止めて、抱いてくれた。昔泥だらけのわたしを抱いてくれた、その腕で。
厚いスーツ越しに、忘れることはなかった、彼の匂いを感じることができた。わたしの背を抱く彼のグラブを通して、彼の暖かさをつかむことができた。それは、廊下にせわしい足音が響いてくるまで、ずっと。
「いけない。ドアを閉めないと」
扉を閉め、鍵をかける。間一髪で、警備兵がインターフォンから警告してきた。
「奥様、白人解放組織のゲリラが、今の便で侵入してきてるんです。気をつけて! 鍵をおろしておいてください!」
「わかったわ。わたしは大丈夫。あなたたちも気をつけて――」
声が震えている。しかしそれが感じとれるほど、彼らも落ち着いてはいまい。ふたことみこと仲間と叫び合うと、彼らは駆けて行った。
彼はベッドの脇で、銃をぶらさげたまま、立っていた。わたしは言葉を探しながら、彼を座らせた。
「……東京にいるとばかりおもっていたわ。奥さんと子供もいるって、後藤さんはそう――」
「僕がそう言ってくれと、頼んだんだ」
「どうして?」
「……君に、死ぬほど逢いたかったから。死ぬほど、逢いたかったから。君に逢ってしまうと、闘うことができなくなると、思っていたから」
「ああ、あなた……」
彼の胸に飛び込み、わたしは泣いていた。泣きながら、彼にしがみついていた。彼は小銃を持ったまま、わたしの髪に手をあてている。わたしは顔を上げ、懸命に微笑んでみせた。
「……それを離したらどう?」
「あ、ああ。指が強張って、離れないんだ。もう弾丸もないのに」
彼の指を、両手で包み温め、一本一本を、引金からはがす。昔の彼は、虫も殺せない人だった。優しくて、優しすぎて、それが恐い人だった。今もきっとそうなのだ。その彼に武器を取らせたのは、わたしなのだ。
彼に不似合いな鋼鉄細工を取り上げ、それを彼の足下に置くと、金属音が立った。触れている彼の足が、震えていたのだった。わたしはそれを抱きしめた。
「計画は――、失敗したのね」
「……移民船に乗っている“協力者”を解放して、ステーションを乗っ取るつもりだったんだ。ところが――僕たちが突入したときにはもう、みな殺されていた。僕たちが侵入したのに気づいて、みんな殺してしまったんだ」
「……非道いことを。なんて、なんてことを――。後藤さんは?」
「死んだ」わたしの頬に、水滴が落ちた。「移民船の【航法/ナビ】コンピュータの、【定電圧定電流装置/CVCS】を破壊しようとしてて――」
「あそこは駄目! あそこは――」
「わかっているよ。僕が行ったときには、【凍結/フリーズ】されていた。先輩は感謝していたよ。侵入経路とガードシステムの資料を教えてくれたのは、君だそうだね。僕も、嬉しかった」彼は、ふと、顔を上げた。「この曲は?」
「パッヘルベルの――」
「うん。僕が好きだった曲だ。久しぶりだ」
「……そうね、そうだったわね」
わたしは彼に寄り添い、肩にもたれた。何度目かのリピートを繰り返したその曲が、また始まろうとしていた。
「こうしていると、三年間のことが嘘みたい。嘘みたい。本当に、ほんとに嘘だったらいいのに。嘘だったら、嘘だったらいいのに。そうしたら、そうしたら、ここはあなたの部屋で、いつものようにわたしがご飯をつくって」
「僕はいっつもサラダを残して、怒られたっけ」
「それで喧嘩して」
「謝るのは、いつも僕の方」
「そう。いつも、いつも、いつまでも、ああやって過ごしていければ良かったのに。あの人たちが来なければ、あの人たちが来なければ、ずっとああして暮らしてゆけたのに」
「――彼らは方法論だったんだよ」
わたしを見ず、彼はどこか遠い所を、その目で探りながら、つぶやいていた。
「――ビジターズの超越した科学でも、乗り越えることができなかったことが、一つある。何だかわかるかい? 因果律さ。原因は結果に先行し、過去は現在にその負債を負っている。過去は現在に裁かれるのを待っているんだ。僕たちの現在は、過去を裁いているんだよ。十九世紀のアメリカを、二十世紀の南アフリカを。彼らは黒い来訪者だった。僕は予言できる。今度来るのは、赤い来訪者か、緑の来訪者か、それとも黄色か? そのとき、過去に生きていた僕たちは、朝、目が醒めると被告席に座っているんだ。刑の宣告を待つために――」
「ああ、あなた――」
わたしは、傷ついた彼にかける言葉の一つもないまま、ただ彼に向かって、小さくうなずくばかりだった。
彼は、後ろで寝息をたてていた子供たちに気づくと、ペリジーを抱き上げた。「可愛いな。ペリジーちゃんだっけ」
「ええ」彼の乾いた瞳に、昔の面影が戻ってくるような気がした。「そうやっていると、似合うわ」
「口許なんか、君に似てるんじゃないか?」
「目は、あなたにそっくり」
「――確かめられたんだろう。遺伝学的に完全に」
わたしは首を振り、きっぱりと言った。「――信じないわ」
彼はうなずいてくれた。そしてペリジーを下ろすと、弾丸の入っていない銃を取り、腰を上げた。
「もう、ここにいる訳にはいかない。君に迷惑がかかる」
「わたしも一緒に行くわ」
「それは駄目だ」
「どうして?」
「子供がいる」
「父親は残るわ」
「母親は必要だ」彼は、わたしの肩に手をかけた。「この子たちに、見せてやってほしいんだ。未来を。現在が裁かれる日を。いいね」
わたしは黙って、彼を見上げていた。【地球光/アースライト】に照らされた、彼の微笑みを。
「僕は間違っていた。最後に君に逢えてよかった」
「――これからどうする気なの?」
「この部屋に君と子供たちのスーツは?」
「あるわ」
「じゃあ、僕が出ていってからすぐ、それを着るんだ。いいね」
彼は離れ、扉を開けた。閉じる扉越しに、なにか短い言葉を言ったが、それは聞きとれなかった。
わたしはスーツを着ることなど忘れて、ずっと立ちつくしていた。しばらくすると、ステーション全体に振動が伝わって、隔壁の落ちるのが感じてとれ、部屋から出ると、ドクターが駆けつけてくるところだった。彼は訊ねもしないわたしに、説明してくれた。
「ゲリラの最後の一人が、外壁を爆破して、ステーションの空気を抜こうとしたんです。隔壁がすぐ閉まりましたから、この区画は大丈夫。そいつも空気と一緒に宇宙に排出されましたから」
「そう――」
部屋に戻ろうとするわたしの背に、ドクターは走り去りながら声をかけていった。「部屋にお戻りになられるのでしたら、窓にブラインドを下ろしておいた方がいいですよ。そっちの方に死体が流れていったみたいだから」
ベッドの上では、ペリジーがむずがっていた。わたしは抱き上げると、窓の外を眺めた。またあの曲が最初から流れだし、破れたスーツが流れていくのが見えた。そしてその手は揺れていた。まるでわたしに振られているように。バイバイ、と。
( 了 )
作中の歌詞はスリーピー・ジョン・エスティス、“イージン・バック・トゥ・テネシー”より。