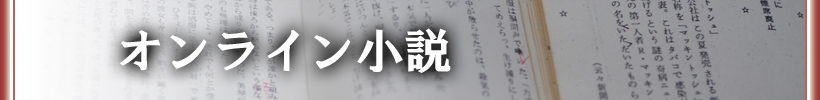オンライン小説
●第1章
まだ入道雲が大きい九月の空を、バリバリバリバリ……と、数台のヘリコプターのプロペラ音が裂いていく。それらは芝浦教会の上を、互いに安全距離を取りながら、旋回しているのであった。
「いやあ、あれがすべて、取材のヘリなんですかね」右の手のひらで傘を作って上空を見上げ、蘇我野神父は驚いたような声で「大したもんだなあ」
ヘリだけではない。路上には、屋根にパラボラをつけた取材車が並び、さらにはお聖堂前の屋外ピロティには、あふれんばかりの報道陣が押し寄せている。アナウンサーにカメラマン、折りたたみばしごを持ったアシスタントにディレクター。まるで祭りのような様相だ。
お聖堂入り口の前で、〝教会広報〟という札を首から提げた多田井が、ハンディメガホンを使って声を張りあげている。
「みなさん、暑い中お疲れさまです。ここはカトリック教会です。みなさんの自由な取材を阻むものではありませんが、節度は忘れないでください。葬儀ミサ前の聖堂内の取材は、お渡しした各社二名ずつの報道者証をつけた者だけです。中でカメラを回すことは基本的には構いませんが、小山内さんのご遺体の入っている棺にはお手を触れぬよう。それと、祭壇がある内陣、ええと、一段上になっている部分ですね。そこには乗らないでください。信徒へのインタビューも止めることはありませんが、祈っている信徒の邪魔はしないように。繰り返しますが、ここは教会です。節度を持ってお願いいたします。誰も見ていないと思っていても、神様が一番見ていらっしゃいますよ」
取材陣の間から、少し笑いが漏れた。
その様子を、聖堂から少し離れた場所、司祭館の入り口前にあるマリア像の前で眺めながら、蘇我野神父は隣の教会事務で司祭の秘書役の妻木にうなずきかけた。
「さっそうとしてますねぇ、多田井さん。しかも手際がいい」
「なんでも多田井さん、以前は広告代理店にお勤めだったそうですから、マスコミ相手の取り回しは慣れたものなんでしょうね」
「へええー」
ハンディメガホンに、多田井は続けている。「葬儀ミサは十六時から始まります。ごミサが始まったら、カメラもリポーターの方も、聖堂からは出てください。入り口の風除室からの撮影はオーケーです。ええと、この中に、カトリックの洗礼を受けた方はいらっしゃいますか?」大勢の取材陣やカメラマンは顔を見合わせたが、誰も手を挙げる者はいなかった。多田井はニヤリと笑い「残念です。信徒の方がいらっしゃったら、ぜひごミサにあずかられていかられたらと思ったのですが」
「一時はどうなることかと思いましたが――」と、蘇我野神父。「多田井さんがこの教会にいらしてくださって良かった。取材陣関係はお任せしてしまって大丈夫そうですね」
「神父さま――」やってきた信徒が声を掛けてきた。「ゆるしの秘蹟を受けたいという方が、告解室でお待ちに――」
「ああ、わかりました」
「おっと、神父さま、横をお邪魔しますよ」と、蘇我野神父と妻木の横を寺内教会委員長が、看板を抱えて通って行く。「どうです。達筆でしょう。うちの右筆が書いたんだ」
看板には、流れるような美しい筆遣いで〝ペトロ・クリストフォロス・小山内秀樹 葬儀ミサ〟と記されている。
「いやあ、確かに見事だ。うちの右筆って?」
という蘇我野神父の質問に、寺内と妻木の二人は、視線でその相手を指した。風除室前でマスコミの質問に答えている多田井である。
「これも多田井さんが!?」
「なんでも雅号を持ってるくらいの書家でもあるらしいですよ」
「元プロテスタントで以前は広告代理店勤務。今はデザイン会社の社長で、勉強会でも驚嘆するくらいの知識をお持ちの上、英語とスペイン後もペラペラ。しかも雅号まで持つ書家でもあるって――」蘇我野神父は嘆息し「多田井さんて、不思議な人ですねぇ」
妻木もクスリ。「ですねぇ。とてもいい人ですし」
「さて、大通りと、階段前と、聖堂前の三カ所につけますけれど、いいですよね、神父さま」寺内の問いに蘇我野はうなずいた。「いい場所に飾ってやらないとなぁ。あまり小山内さんと話したことはなかったけれど、うちの教会のかがみですよ」
看板を両腕で抱えて去って行く寺内を見送りながら、蘇我野神父は少し息をついた。「実を言うと、僕も小山内さんとは、一、二回しかお話ししたことがないんですよ。奥さまの方は毎週、ごミサにいらしていらっしゃるけれど、旦那さまの方はそれほど、でしたよね」
「長患いのご病気だったと聞いています。最近は良くなって、外出もできるようになったと喜んでいらっしゃったのですが、わたしも詳しくは知らなくて」
「妻木さんでもそうですか」
この教会の人事ならほぼ表から裏まで把握している、辣腕教会事務の妻木である。その言葉に間違いはないだろう。
実際、今日これから葬儀ミサが開かれる〝ペトロ・クリストフォロス・小山内秀樹〟氏は、この芝浦教会にとって、教会籍はあったものの、今までは影が薄い信徒ではあったのだ。妻の小山内潤子の方は、毎週ミサにあずかる熱心な信徒ではあったが、夫の方は、数ヶ月に一回、その姿を見るか見ないかくらいの存在感であった。
芝浦教会の聖堂入り口は二カ所あり、もう一カ所の方にはマスコミの山はない。蘇我野神父と妻木はその入り口から聖堂に入った。
祭壇の上には十字架と聖柩の両側に、山ほどの花輪の列ができている。そして祭壇前に男性の写真。六十過ぎくらいであろうか。あまり生気のない瞳、特徴のない、薄い表情で写っている。急いでなにかの証明写真から拡大コピーしたものだろうか、と、蘇我野神父は思った。このあたりは、信徒が伝手のある葬儀会社の仕事である。
「立派な花輪ですね」と、蘇我野神父は小さなため息。「ヨゼ神父さまがいらっしゃってくだされば――」
「葬儀ミサはともかく、この立派な花輪の列は喜ばれたかもしれませんね。なんだかんだ言って、派手好きですから。ヨゼ神父さま」
ヨゼ神父は、現在、マルキエル会の黙想会で二十年ぶりにスペインへ帰国中である。黙想会という名目とは言え、事実上のサバティカル――司祭の休暇であった。
「あとでお見せできるよう、写真を撮っておきましょう」蘇我野神父は神妙な顔つきになった。「少し緊張してきました。一年生の助任司祭に、こんな立派な葬儀ミサが務まるでしょうか? 応援を頼んだ方が良かったかな」
「大丈夫ですよ。落ち着いて司式なされば蘇我野神父さまは失敗しません」妻木はクスリと笑った。「ヨゼ神父さまも、葬儀ミサで〝平和の挨拶〟をやらかしちゃったことがあるんですよ」
「ほんとですか!?」
告解室の赤いランプが点灯している。誰かが入っていて、ひざまずいて待っているという印である。
葬儀会社の係に呼ばれ、妻木は忙しく身を翻してそちらの方へと。蘇我野神父も香部屋へと足を運び、そこで白のストラを掛けて、告解室の司祭側へと入った。
告解室は、世間ではよく〝懺悔室〟と呼ばれる部屋である。
カトリック教会の告解室には多種多様な様式があるが、ここ芝浦教会のそれは一般的なものだ。司祭と信徒が入る部屋に分けられており、信徒側は畳一畳分くらい、司祭側がもう少し広いのは、暖房機や扇風機を置くためである。
信徒側の部屋には〝ひざまずき台〟があり、そこに膝をついて座るとスイッチが入り、外の赤いランプが点灯するという仕組みである。
逆に司祭が司祭側の部屋に入ったときは、スイッチを自分で操作して、〝司祭が告解室にいる〟という赤ランプをつける。
世間で勘違いされている、カトリック教会についての誤解のいくつかが、この〝告解〟絡みである。
まず、一般に流通している〝懺悔〟という言い方は、現代のカトリック教会ではしない。〝ゆるしの秘蹟〟か〝告解〟である。
また、教会に縁のない人は、誰でも教会へ行けばこの〝懺悔〟が受けられると思っているきらいがあるが、〝告解〟を受けることができるのは、カトリックの洗礼を受けた信徒だけである。未洗礼の信徒を〝告解室〟に招き入れて、司祭が人生相談に乗る――ようなドラマのようなことは絶対にない。
また、大きなカトリック教会ならともかく、地方都市の小さなカトリック教会では、特別な期間でもなければ、司祭が何時から何時まで告解室で待機している、ということもない。今回の蘇我野神父のように、信徒に呼ばれて告解部屋へそろって入るのが普通である。
言うまでもなくプロテスタント教会にはこのような秘蹟はない。
また、マンガチックに、シスターが聴罪するということもありえない。信徒の罪を聞き、神の赦しをつなぐことができるのは、聴罪司祭――神父――のみができることである。
信徒は定期的に罪の告白を行うことを奨励されているが、この現代では、あまりそれを行う信徒がいないことも確かである。せめてクリスマス前の待降節、聖なる過ぎ越しの三日間前の四旬節くらいはということで、その期間、所属教会の司祭と違う司祭が黙想会などで訪れ、そういうときは〝行列のできる告解室〟になったりもする。やはり信徒側としても――いくら守秘義務があるとはいえ――なじみの神父に罪の告白はしにくい、というところがあるものだ。
逆に、告解室がいっぱいのときは、香部屋で神父とマンツーマンで告解を受けることもある。世間の人々が思うよりも固いところもあるし、柔軟なところもある、そして現代の信者にとっては、ちょっと縁遠くなりつつある秘蹟が、この「告解」――ゆるしの秘蹟なのである。
司祭の席に座った蘇我野神父は、フーッと一息つくと、信徒との間を隔てている格子窓をカラリと開けた。
「お待たせしました」
「神父さま――」
年配の女性の声だ。しかし、ただそれだけの情報であるよう、蘇我野神父は努めた。今自分は、神と信徒の間に入っている通訳のようなものだ。自らの感情の波は立ててはならない。いい感じだ。
「父と子と聖霊の御名によって」
「アーメン」
「前回のゆるしの秘蹟はいつでしたか?」
「四旬節でした。とても寒い日に」
これは定番のやりとりである。
「それでは、神の愛に信頼して、あなたの罪を告白してください」
「……」
無言の時間が続く。これもよくあることだ。蘇我野神父は、辛抱強く待った。
「……神父さま、わたしは罪を犯しました」
「はい――」
「神父さま、わたしは罪を犯したんです。わたしは!」女性は声を荒らげて、激しい嗚咽とともに言った。「今日、葬儀ミサを挙げていただく、小山内秀樹の妻、潤子です」
えっ、と蘇我野神父は格子から信徒側の部屋を見た。台に両肘をつき、タオルハンカチで顔を覆い肩を震わせている女性は、確かに小山内秀樹の妻、見覚えのある潤子であった。
「どの――」動揺してはならない。蘇我野は射祈を飛ばす。主よ、わたしをあなたの道具としてください。「どのような罪を犯したのですか?」
「わたしは知っていました。知っているんです。神父さま!」
突如、潤子は体を返して格子に両手の指を掛けた。これには、心に波を立てまいとしていた蘇我野神父もぎくりとせざるを得ない。
「小山内さん、落ち着いて、落ち着い――」
「神父さま。今からでも、この葬儀ミサをやめることはできませんか?」
「えっ、それは、どういう――」
「わたしは知っているんです。主人は、こんな立派な葬儀ミサを挙げてもらえる身分じゃないって。主人が罪を犯し、わたしはそれを見逃したんです。主人は――」
再び長い沈黙が、二人の間に割り込んだ。
* *
「わぁお、見てみて、芝浦教会映ってるよ」目をきらきら輝かせて、テレビをのぞき込む若い女性である。「谷中ちゃん、葬儀ミサ、行く?」
「えっ、うーん」谷中と呼ばれた、こちらも若い女性。ちょうど浴室からシャワーを浴びて出てきたところである。タオル一枚巻いたままの、あられもない姿だ。「正直、パスかな。小山内さんの奥さんは知ってるけど、あんまり深いおつきあいってわけでもないし」
テレビには、芝浦教会の空撮が流れている。ワイドショーの画面だ。下にはテロップがついている。〝女性を助けた小山内さん、今日、通夜〟
「能勢ちん行く気あるん?」
「ほら、テレビ局関係がこうやって押し寄せてくる資料って、あんまないからさ。撮影しとくのもアリかなって」
「逆取材はアリだけど、うーん。このクソ暑い中、出かけたく――」
ブイーン! と、自分が髪に掛けるドライヤーの音で彼女の声はかき消された。
「ちょっと谷中ちゃん、ドライヤーうっさい」
「録画しときなよ」
「もうしてますー」
『現場の踏切には、城ノ内リポーターが行っています。城ノ内さん』
と、ワイドショーの司会者が言うと、テレビの画面がパッと切り替わった。
『こちら現場となった踏切から、城ノ内がお伝えします』
画面には、人が二人並んで通るのがいっぱいの小さな踏切と、その脇に置かれたたくさんの花束、人混みが映し出された。
『小山内さんは、この踏切で立ち往生していたお年寄りの女性を救って、電車に接触して亡くなりました。現場にはたくさんの花束、そしてこれは、聖書、あと、十字架ですね。そういったものが供えられています』
画面を神妙に見入る、谷中と能勢のコンビである。
『城ノ内さん、小山内さんはお年寄りの女性を、どのように』
『先ほど、事故を目撃した方からおうかがいしました』スタジオからの問いかけに、リポーターはクリップボードをチラ見しながら続けた。『助けられたお年寄りの女性ですが、押していたカートですね。足代わりの。それが線路に引っかかって、動けなくなっていたそうです。小山内さんはまずお年寄りを抱きかかえるようにして線路の外へ運び、引っかかっていたカートを取りに行こうとして、電車に接触したとのことでした』
『その踏切には遮断機はついていないんですか?』
『いえ、ご覧の通り、小さな踏切ですが、遮断機も警報器もついています』
『小山内さんは、警報器が鳴っている踏切に飛び込んで女性を救ったわけですね』
画面にスタジオが映し出された。司会者が嘆息して言う。『いやぁ、あの警報音がね、カンカン鳴っている踏切に入って人を救うってのは、なかなかできることじゃありませんよね』
『そういうことができるっていうだけで、すごい、なんて言うんでしょう――』と、司会者の相方の女性アナ。『人間として素晴らしい方ですよね』
『城ノ内さん、助けられた女性は無事なんでしょうか?』
『はい。一度、市内の病院に入院したとのことですが、幸いなことに大きな怪我などもなく、現在、検査入院中とのことです』
司会者は、いかにも自分の手柄のように『先ほどの花束の中に、十字架や聖書があったとのことですが――』
『はい。小山内さんは、敬虔なクリスチャンでいらっしゃったとのことで――』画面が、パッとヘリからの空撮に変わった。『今夜、お通夜が、同じ市内の所属教会で行われるとのことです』
「あ」
「あ!」
能勢と谷中の二人は画面ににじり寄った。そして同時に。「今の!」
「蘇我野神父さま」
司祭館の前で、妻木と話している蘇我野神父の姿が豆粒のように映っていたのだった。
二人の若い女性は、きゃーっと嬌声を上げた。「いいよね、いいよねやっぱり」
「絶対テレビ映えする顔だよ」
「ミサ映るかな?」
「映してほしいねぇ」
と、いきなり能勢は谷中を床に押し倒した。「君に、僕のご聖体を食べてほしい」
突然のことに驚くどころか、谷中はちゃめっ気たっぷりに目をつぶって「アーメン……。って違うって、蘇我野神父さまは絶対〝受け〟だから!」
「ちっがーう、わかってないなぁ。能勢ちんは。あの真面目そうな顔で蘇我野神父さまは〝攻め〟なんだよ」
「それにしても――」
「わたしたちって――」
二人は窓から天を見上げて、同時に言ったのだった。
「罪深いよねー!」
(第2章へ続く)