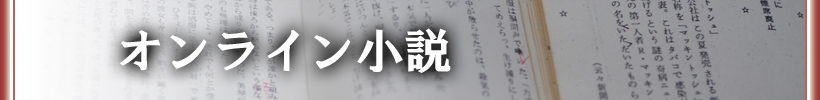オンライン小説
●第4章
中央区重富町――そう電柱に貼られた番地表示が見えてくる。時間はおそらくあれから十五分。
それにしても、カートを使うような足の悪い老女が、現場の踏切まで行くのは大変だったろうと気づき、蘇我野神父は眉を寄せた。ひょっとしたら、多田井のメールを見間違えたのだろうか?
蘇我野神父は、正確な場所を調べるためにバイクを停め、ポケットからスマホを出した。そういえば、番地はマップに入力したが、相手のお名前はもう忘れてしまった。近所に着いた時点で、もう一度、多田井からのメールを確認すればいいだろうと思って――
「あっ!」
それは一瞬の出来事であった。多少、気が焦っていた蘇我野神父の手から滑り落ちたスマホは、弧を描きながら空中に舞い、灼熱のアスファルトの上に、しかも角から、軽い破壊音とともに落下していたのであった。
「えっ? ええ?」蘇我野神父はしばらく固まっていた。「うそ、でしょ……?」
慌ててスマホを拾い上げる。が――その画面はクモの巣のように割れていた。いやしかし、画面は割れていてもまだ見られる。電源さえ入れば。
「主よ!」
小さく射祷を飛ばし、電源スイッチを押してみる。いつもならここで、聖母マリアのロック画面が表示されるはず――しかし、まるでステンドグラスのように割れた画面には、なにも表示されなかった。
呆然とした蘇我野神父は、あまりのことに、くらりと電柱に倒れて寄りかかってしまった。スマホが壊れたことなどどうでもいい。今は一刻も早く、被害者の女性に会って話をしなくてはいけなかったのに――。
と、寄りかかった電柱のすぐ横に、緑色の公衆電話ボックスがあることに蘇我野神父は気づいた。公衆電話! これを以前使ったのは何年前だろう。
熱気がこもる公衆電話ボックスの中に飛び込む。ポケットから財布を出す。が、小銭がない。なんでこんなときに限って。
いやしかし、こういうときのために、手持ちのカトリック手帳にテレホンカードを一枚だけ入れていたことを思い出した。それはミサのとき回される献金袋に入れられていたもので、おそらく現金がない信者が、せめてものという思いで入れたものだった。
福音書の中でも有名な〝やもめの献金〟の一節が頭をよぎる。「信者のどなたか存じませんが、あなたの信仰がわたしを救ってくれまし――」
受話器を取ってテレホンカードを入れ、蘇我野神父の動きは止まってしまった。いったい、どこに電話をしたらいいというのか。多田井の電話番号はスマホに入っているのだ。今や、壊れて起動できないスマホの中に!
自分の教会の電話番号なら、カトリック手帳にも載っている。蘇我野神父は芝浦教会のページを繰って、そこの番号をたたき込んだ。ベルが鳴る。鳴っている。だが――出る者はいない。当たり前だ。鳴っているのは司祭館の電話である。そこのあるじが、今、ここにいるのだから。
蘇我野神父は、蒸し暑い電話ボックスの中で、ついにへたりこんでしまった。
まるでサウナ風呂のようだ。それでなくても、頭がポーッとしてくる。時計の針は午後三時二十分。一度、教会に戻っている時間はないだろう。
ポケットの中をまさぐった蘇我野神父の指先に、なにかが触れた。折った紙だ。取り出してみると、健緑総合病院で、受付の若い娘が、赤い顔で渡してくれたメモだった。
『無理かもしれませんが、電話をください』
もう一度、彼女を説得することはできないだろうか!
蘇我野神父はバッと立ち上がり、受話器を取ってテレホンカードを入れると、メモの番号をたたき込んだ。携帯の番号である。おそらくは、彼女の私的な。
コール二回で相手は出た。
『もしもし?』
可愛らしい女声である。
「もしもし。突然すいません。先ほどそちらの病院におうかがいした、芝浦教会の神父で――」
『あぁ、神父さま――』声のトーンが跳ねあがった。『電話、お待ちしていたんです』
「いや、それが――」多少の罪悪感を覚えながら、蘇我野神父は「先ほどのお願いについてなんですが――」
『それなんです!』受付の女性職員の、あどけない声が受話器から嬉しそうに『相手の方から了解を得ることができたんです』
「えっ?」
『無理かもしれないって思ってたんですけど、今朝退院した患者さまに、こちらから、こういう事情だから、神父さまにご住所をお教えしていいか、って、おうかがいしたんです。そうしたら家族の方から、喜んでお教えしてくださいって、ご了解を得ることができて――』
なんてことだ! 天使は最初からそこにいたのだ。蘇我野神父は自分が少しでもよこしまな考えを持ったことを悔いて親指で胸に十字を切った。
『メモ、いいですか?』
「いつでも」
今度こそはもう大丈夫。蘇我野神父は電話ボックスの壁を下敷きに、カトリック手帳に付属のシャープペンの芯を出して用意した。
『中央区重富町五‐二十三‐九、森村美枝子さんという方です。ご家族とご一緒にお住まいです』
「ありがとうございます。それと、もうひとつ大切なことを」
『え!?』
「あなたの、お名前をぜひ」
『あ、えと――』受話器を通しても、相手が真っ赤になってあたふたしている様子がわかるようだった。『日野です。日野さやか』
「日野さやかさん、ありがとう。あとで必ず、お礼におうかがいします!」
受話器をガチャリと架台に戻し、蘇我野神父は転ぶように電話ボックスから飛び出した。
* *
その家は住宅街の中にまぎれた、ごく普通の一軒家だった。「このたびは本当に、なんと申しあげたらいいか」扇風機がムッとした空気を攪拌している和室の居間に通された蘇我野神父に、小山内秀樹に助けられた女性の娘であるという年配の女性は、恐縮して言った。「亡くなられた方に感謝の言葉もなくて……。今、お茶をいれますので」
「あ、いや、ありがたいのですが、そういうのは本当におかまいなく。なにしろ四時から葬儀ミサが始まる予定で、もう本当にすぐに教会へ帰らないと。それで――お母さまは?」
女性は視線で、縁側を指した。網戸の外で、来客がきているのに、ボーッと座っている老女の姿がそこにあった。
女性は息をついた。「おわかりになりますか? 実はご覧の通り、少し、認知症が入っていまして――」
「そうでしたか――お怪我などはいかがですか?」
「いえ、まったくそういうのもなくて、助けてくださった方に本当に、本当に申しわけなくて……」
女性は右手に持ったハンカチで、そっと涙を拭った。
「あの日は、ちょうどクルマで母を連れて外出して、あの近所のスーパーへ二人で寄って、わたしがちょっと目を離した隙だったんで。以前、あのあたりに住んでいまして、母はそこへ向かおうとしたんじゃないかと」
腕時計の針は、すでに午後三時二十五分を回っている。
「お母さまと直接お話をしても構いませんか?」
「もちろんです」
蘇我野神父は、縁側の老女の横に座った。
「こんにちは。森村さん。わたし、教会の神父で、蘇我野、と申します」
「……帰ってこないねぇ」
「帰って、こない?」
「だからお母さん。そのことはもうあきらめようって」
「なんのことです?」
「いえ……」女性は語尾を濁した。「本当に、なんでもないんです。ごめんなさい」
と、老女の表情にピクンとなにかが走り、赤みがさした。「いる!」
「お母さん!」
と、女性がたしなめようとしたそのとき、森村家の生け垣から、なにか、小さな茶色の毛玉が飛び込んできた。
「トニオ!」
「トニオ!? まさか」
生け垣から庭に入り込み、体をブルンブルンと震わせて葉を落としているその存在は――全身、土と草にまみれて薄汚れたチワワであった。
女性が両手を口を当てる。「トニオ! 生きてたなんて」
チワワは軽く鳴くと、老女の懐に駆け込んでいった。
「おぉ。トニオ、トニオ。やっぱり帰ってきてくれたんだね」
蘇我野神父は、スラックスのポケットから、あの踏切現場から持ってきた、革製のベルトのようなものを取り出した。
「それ――」女性が声を上げる。「この子の首輪です」
「あの踏切に落ちていました」
「本当にごめんなさい。こんなこと。あまりに申しわけなくて、誰にも言い出せなくて、実はあのとき、母のカートには――」
蘇我野神父は、怒濤のようにしゃべりだそうとした女性を、両手を挙げて止め、うなずき、真摯に言った。
「なにも申しわけなく思うことはありません。誰も誰かを責めたりはしません。すべては神の思し召しです。少なくとも――」蘇我野神父は挨拶もそこそこに森村家を出ながら、女性と、老女にうなずきかけた。「これでひとりの女性が救われたんです」
(第5章へ続く)