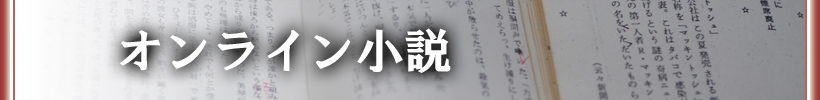オンライン小説
●第2章
「すると小山内さんは――」告解室の中で、蘇我野神父は声を震わせた。「ご主人の事故は、本当は【自殺だった/傍点】と、そうおっしゃるのですね?」
「そうです。間違いありません。主人は、人を救ったと見せかけて、体よく自殺したんです。こんな立派な葬儀ミサを挙げていただけるような、偉いことをしたわけじゃないんです。むしろ――」小山内夫人は言葉を絞った。「地獄に落ちているんです」
カトリック教会において、死は決して忌むべきものではない。キリスト再臨の日まで、今生でのお別れをする寂しいことだが、〝永久の眠り〟ではないからである。死んでもいつの日かまた必ず会える、という保証があるのが、カトリック、プロテスタント問わず、キリスト教の共通認識である。
それでも、カトリックの教義で自殺は禁忌となっている。信者が自殺した場合は、通常、ミサは執り行われない――ことになっているが、現代では〝自ら死を選ぶほどの心の病だった〟と解釈がなされ、まったく葬儀ミサが行われない、ということもない。
ただ、やはり自殺ということは大っぴらにされることはなく、密やかに家族うちうちで、しめやかなミサとなることが多いようだ。ひと昔前は、ミサを挙げるとしても香部屋で、などと、明らかに差別化されたこともあったという。
現代であっても、自殺での葬儀ミサならば、内陣に花輪が並び、華やかな式になることは考えられない。
小山内夫人が、花輪が並びマスコミが押しかけヘリが飛ぶ、この大仰なことになってしまった葬儀ミサを、〝ふさわしくない〟と感じるのは当然であった。
小山内秀樹が自殺ならば、だが――。
「しかし、だとしたら、その――ご主人が自殺だとしたら、理由があるわけでしょう?」
「主人は――うつ病だったんです」小山内夫人はそこでいったん息を継いだ。迸るように話したいことを伝え、少し落ち着いたようである。「一年前に、精神科にかかって、そう診断されました。仕事もそれで休職していたんです」
「そうだったんですか――」
一年前、蘇我野神父はまだ助祭で、この芝浦教会にも来ていなかった。もし、小山内秀樹がこの件で〝病者の塗油〟の秘蹟を受けていたとしても、知らないはずである。
〝病者の塗油〟とは、カトリック教会七つの秘蹟のひとつであり、ひと昔前は臨終を目前にした信徒が受けるものと決まっていたが、今は病気を患った患者がその治癒を願って受ける秘蹟となっている。
もちろん、不治の病で死を覚悟した者が、神の奇跡を求めて受けることもあるわけだが――。
「でも、服薬で、うつ病はだいぶ良くなっていたんです。ただ、うつ病は治り始めが一番怖いって――」
「知っています。病気が良くなって、それまで闘病していた人が、少し動けるようになると。その――」現代の司祭として、蘇我野神父は心の病のシンポジウムなどに参加し、うつ病患者が一番、自殺企図をするのが治り始めなのだということを覚えていた。「ご主人がそうだった、と?」
「いえ、いえ。病気は治ったんです。一度は。服薬も徐々に減らして、今は精神科に通うこともなくなっていて復職も果たしていました」
「小山内さん。小山内さん自身が、もう、納得していらっしゃるじゃないですか」蘇我野神父は、言葉をゆっくりと選び「ご主人は自殺なんかじゃありませんよ」
「いえ、自殺です」
「そんな――」
「主人は、治りかけのとき、自殺未遂していたんです。あの踏切で」
えっ、という言葉を、蘇我野神父は飲み込んだ。こういうときは、こう返す。
「奥さまは、ご主人が、うつ病が治りかけのとき、あの踏切で自殺未遂なさったと、そう考えていらっしゃるんですね」
相手の言葉を肯定も否定もしない。それがコツだとシンポジウムで学んでいた。
「あの病気になったときから、主人は、死ぬならあの踏切で電車に轢かれて死ぬ、と口癖のように言っていたんです。治りかけで動けるようになったとき、夜、家族も就寝してわたしが入浴中、主人はひとりでふらりと、あの踏切に行っていたんです。気づいたわたしが思い出して、慌ててあの踏切まで走って行ってみると――」
告解室に沈黙が流れた。
「――主人は、あの踏切、今回の事故があった下りの線路で仁王立ちしていたんです。電車は来ていませんでしたけれど、わたしは主人にとびついて倒しました。棺に入っている主人のメガネについている傷。あれはそのときついたものなんです。今回のことでついたものではないんです」
「そういうことでしたか。ご主人は、その――」こういう言い方はいけない、と承知していながら、蘇我野神父は言ってしまっていた。「そのとき、本当に自殺企図を? ちょっとした夜の散歩ではなく?」
「そのときははっきりと、自殺したいとは言っていませんでした。けれど、わたしから見れば、あれはもう、自殺未遂そのものです」
「しかしそれは――」蘇我野神父は、いくつも浮かぶ考えを激しく巡らしながら、それでも冷静を装って「過去のことです。今は病気も治って、復職もしていらっしゃる。今回の事故を自殺だというのは、考え過ぎではありませんか?」
「病気が再発したんです。でなければ、どうして日曜の午後に、わざわざあの踏切近くの公園まで散歩したりするんです?」
「――奥さまは、小山内さんが、自殺するためにあの踏切へ行っていたと、そうお考えなのですね」
肯定も否定もしない。これでいい。蘇我野神父は一息整えた。
「警察の方が教えてくれました。目撃者のお話を。主人はおばあさんを抱きかかえて線路からいったん逃げたあと、おばあさんを脇に置いて、線路に引っかかっていたカートを取りに戻ったと。なぜそんなことをする必要があるんです? カートなんて、ただの物ですよ。おばあさんを抱いて安全な場所へ逃げるだけで良かったじゃないですか」
確かにその報道は、この〝美談〟の報道合戦の中で、蘇我野神父も耳にしたことがあった。潤子の言う通り、線路に引っかかったカートを取りに戻らなければ、電車と接触することもなかったはずだ。
潤子の方も少し落ち着いたようだが、その声には、悲しみの中にも、どうしようもない怒り、やりばのない憤りがにじんでいるようだ。
「主人はきっと、こう思ったんです。これはチャンスだと。事故死に見せかけて自殺することができると。主人はわたしたちをだましたんです。でも、人間はだませても、神様をだますことはできないですよね!」
若い神父は、格子を隔てた相手が悟らないよう気を遣いつつ、一回、深呼吸をした。なるほど、潤子の言うことは、それはそれで筋が通っている。しかし、なにか言語化できない違和感、論理のない感情がフッと浮かびあがってくる。蘇我野神父の脳裏に――それは数回しかなかったが――小山内秀樹がご聖体を受けていたときの表情が、本の間から落ちる写真のようにパラリとめくれてよみがえった。
蘇我野神父は考えるよりも早く話していた。根拠のない確証があった。『実は、話すのはあなたがたではなく、聖霊なのだ』というマルコ福音書の言葉に自分が満たされていることを感じた。
「小山内さん。どのような罪をも、神様はお赦しになります。ですが、小山内さんは償いをしなければいけません。おわかりですね」
「ええ、ええ。もちろん。だからこんな葬儀ミサは――」
「ロザリオを四環!」蘇我野神父は小気味よく遮った。「喜びの神秘から、苦しみ、栄え、光の神秘まで、わかりますね。この四環を、丁寧に唱えて祈ってください」
「えっ」
「いいですか、その告解室で今から、です。外に出てはいけません。それが、今回のゆるしの秘蹟の償いです」
「でも――」
司祭はその若さにも関わらず、威厳と、強い口調で言った。
「神様に〝でも〟はありません。やってください。葬儀ミサに関しては、今は忘れてください。神様がすべて、とりはからってくれます」
潤子は言葉を失っているようだったが、やがて、あきらめたように答えた。
「わかりました」
「では、父と子と聖霊の御名によって。アーメン」
十字を切ると、蘇我野神父は音を立てずにゆっくりと扉を開けてお聖堂に出て扉を閉め――走りだした。と、ちょうど香部屋から出てきた妻木とぶつかりそうになる。
「っと。どうしたんですか神父さま、血相を変えて」
「妻木さん、いいところに。いいですか。告解室に入っていらっしゃるのは小山内潤子さんです」
「はい」キョトンとしている妻木京子。
「小山内さんは今、中でロザリオを四環となえています。その間に、わたしはやらなければならないことができました」
「はい?」語尾を上げる京子。
「それで、小山内さんがわたしが帰ってくる前に告解室から出てきてしまったら、お願いがあります。わたしが、罪の償いはまだ足りないと言っていたと伝えてください。今度は続けて、十字架の道行きをやれと命じていたと」
妻木はほんのわずかの間、面食らっていたようだが、すぐに答えた。
「――わかりました」すべてを聞かずとも、聡い妻木はだいたいのところをつかんでくれる。パチリとウインクをして、蘇我野神父のストラを肩からサッと外す。「時間がないんでしょう? あとは任せて、行ってください」
「恩に着ます!」
蘇我野神父はスータン姿のままで、お聖堂の裏口から飛び出して行った。
妻木は苦笑して、親指で小さく、胸の前で十字を切った。若い神父のたくらみはわからないが、神様がともにいてくださいますように、と。
* *
ロザリオというのは、カトリックの〝数珠〟である。珠で作られた円環の部分から伸びたところに十字架がつけられており、一時期、クリスチャンではない人々の間でもネックレスのように多用された。しかし、カトリック信者で首からロザリオを掛ける者はまずいない。普通はロザリオケースに入れ、大事に持ち運ぶ。アクセサリーではないからである。
〝数珠〟と書いたように、信者はこのロザリオを使って祈る。使徒信条、主の祈り、栄唱、それに一番唱える〝アヴェ・マリアの祈り〟を組み合わせて珠を繰る。そう、ロザリオは聖母マリアにイエス・キリストへのとりなしを祈ってささげる信心業なのである。
ロザリオの珠をぐるっと一周繰ることを〝一環〟という。一環ごとにキリストの受難と復活を聖母マリアの目を通して見るテーマがあり、四環で祈りのパターンが終わるようになっている。
蘇我野神父は計算していた。経験則的に、ロザリオ一環を黙祷で唱えるには約二十分の時間が必要である。それが四環だから八十分。小山内潤子が言いつけ通り丁寧に祈っていると数字を甘くみても九十分、一時間三十分がリミットだろう。おそらく、彼女は告解室から出てしまえば、妻木の制止を振り切って、自分の夫が自殺したと、周囲に吐露してしまうに違いない。
大型スクーターでスータンをなびかせ風を切りつつ、教会のある高台からの坂を下りながら、蘇我野神父はまず、自分がどこに行くべきか、激しく思考を巡らせていた。
チラリと腕時計を見る。時計の針は午後二時二十分。タイムリミットの三時五十分までに教会へ戻れたとしても、葬儀ミサの開始は午後四時。どちらにしろ、ギリギリの線だ。
まずは生き証人に会うべきだ。そう、ひらめいた。蘇我野神父の脳裏に、朝、ワイドショーで映った病院がパラリとめくれる。あれは確か、市内の〝健緑総合病院〟だった。小山内秀樹が救ったお年寄りの女性は、そこに入院したとアナウンサーが言っていた。
教会の坂を下りて交差点を右折。〝健緑総合病院〟は県立博物館の並びにあったはず。幸いなことに、教会から飛ばせば十分で着く距離だ。
信号が青になるのももどかしく、車体を斜めにして、大きな交差点を再び右折。その病院は建てられてまだ新しく、綺麗に直立した看板が目印になっている。
門から地下駐車場へとすべり込み、バイクを立ててヘルメットを脱ぐ。熱気で頬がゆであがりそうだ。
しかし、一息入れている時間はない。蘇我野神父は病院入り口への階段を駆け上り、自動扉が開きかけたところで、体を横にして中へまろびこんだ。
汗だくで飛び込んできたローマンカラーにスータン姿の〝神父〟の様子に、受付ブースの中にいた制服姿の女性職員二人が目を白黒させている。
「すみません、お訊ねしたいことがあるのですが、こちらでよろしいですか?」
端正な顔立ちの蘇我野神父が、表情をきりりとさせて真剣な瞳で訊ねてくるものだから、女性二人も少し――どころか若いひとりは頬を染めてうなずいていた。
「ニュースでご存じだと思いますが、この市内の踏切で、お年寄りの女性を庇って男性が亡くなられた事故をご存じでしょう?」
「ええ、もちろん」
「わたしは、その男性が所属していたカトリック教会の神父です。蘇我野と申します」
ああ、と女性職員二人は顔を見合わせた。 蘇我野神父は、自分の容姿が、自然、二人を懐柔していることを知ってか知らずか、両手の指を組み合わせて、ブースの台に置き、身を乗り出した。
「今日の午後四時から、その方、小山内秀樹さんの葬儀ミサを執り行います。その前に、ぜひとも、小山内さんがお救いになった女性にご挨拶をしておきたいんです。こちらに入院なさっているというお話をお聞きしましたので」
「面会のご案内ですね」
「そっ、そ、それでしたら――」
「その患者さまは――」うわずった声を上げた若い同僚を遮って、メガネを掛けた、おそらく先輩の女性職員は首を横に振った。「今朝方、退院していらっしゃいます」
「そうでしたか――」と、髪を無造作にかきむしる蘇我野神父である。その姿すら様になっており、若い女性職員はポーッとしてしまっているくらいだ。
「それでは、ぶしつけなお願いは承知ですが、その方のご住所や電話番号をお訊ねすることはできますか?」
「あっ、はい。ちょっとお待ちくださ――」
受付台の受話器を取りかけた若い女性職員を、先輩とおぼしき同僚が小さく小突いた。
「誠に申しわけありませんが、患者さまのご連絡先は、この病院が守るべき個人情報となっておりますので、お教えするわけにはまいりません」
「それはわかります」蘇我野神父は真摯な瞳でメガネの女性職員を見つめ「しかし小山内さんは、自分の命を掛けて、その女性を救ったんです。ぜひとも、これから葬儀ミサを司式する司祭として、小山内さんが最後に出会った方とお話しておきたいんです」
「そのご事情はわからないでもありませんが」と、先輩職員も退かない。「神父さまもそうでいらっしゃるように、わたしたちにも守秘義務というものがございます。ご理解ください」
蘇我野神父は長く息をついた。「どうしても駄目ですか」
「はい。誠に申しわけございませんが」
唇を噛み、小刻みにうなずいて、蘇我野神父は肩を落とした。
「わかりました。無理なお願いをして申しわけありません」
駄目と決まったら、ここに長居している余裕はない。チラリと時計を見る。その針は午後二時四十分。結局、二十分も無駄に使ってしまった。自動扉を早足に抜けながら、駐車場のバイクへと向かいつつ、蘇我野神父は天を仰いだ。主よ、次の手は――
「あ、あ、あの!」
声を掛けられて、ふりかえる。そこにいたのは、案内ブースにいた、若い女性職員だった。上気した頬で、いかにも、今すぐ恋の告白でもしそうな雰囲気である。
「こ、これを――」彼女は蘇我野神父の右手を取り、その中に、紙切れを無理やり握らせた。「がんばってください」
「は、はい?」
予想外の出来事に面食らっている蘇我野神父を置いて、若い女性職員は病院に駆け戻って行った。
蘇我野神父が右手を開け、そのメモを見ると――
『無理かもしれませんが、電話をください』
というメッセージとともに、携帯番号が記されていたのであった。
うーん、とうなり、蘇我野神父はそのメモを無造作にスラックスのポケットに入れた。一瞬、恋の告白をされた学生時代のことを思い出し、頭を振ってヘルメットをかぶろうとしたが――。
「電話か――」
蘇我野神父はスマホを取り出すと、アドレス帳をめくって、信徒の名を探し出した。〝多田井晃〟。トン、と指先で電話を掛ける。呼び出し音は、たった三回で取られた。
『はい多田井です。神父さま、教会にいらっしゃらないようですが、どうなされました?』
むろん、相手――多田井――はこちらの電話番号で自分だと承知していた。
「多田井さん、実は事情があって、今回の事故で小山内さんに救われたというおばあさんに会いたいと思っているんです」
『はい』多田井の答えはいつも簡潔である。
「それで、おばあさんが入院なさっていたという病院まで来たんですが、今朝方、もう退院されたとのことで、どうしても住所を教えてくれないんですよ」
『退院なさったなら、そうでしょうね』
「それで多田井さん」蘇我野神父は、至って真面目に、はっきりと言った。「そのおばあさんの住所、多田井さんなら、わかりませんかね?」
『……』多田井にしては、沈黙が長かった。が、おそらく時計の秒針は百二十分の一も回らなかったろう。『どうして病院で教えてくれないことを、わたしが知っていると思ったんです?』
「ヨゼ神父さまが帰国なさる前に、わたしにこんなことをおっしゃってたんですよ。寺内さんが芝浦教会のFBIなら、多田井さんはCIAだって。多田井さんに聞けば、わからないことはなにもないって」
『……』
さすがにこれは一秒かかった。しかし反応は蘇我野神父の予想とは違っていた。多田井は困惑していない。受話器の向こうで苦笑していたのだ。その様子が電波越しに伝わってくる。
「わかりました。神父さま。これは一個貸しですよ。三十分ください。神父さまのスマホにメールしておきます」
「三十分――」蘇我野神父は腕時計をチラリと見て「二十分になりませんかね?」
「それは無理です。二十五分で。切りますよ」
電話は一方的に切られたが、それは失礼ゆえではなく、多田井が一刻も早く調査を開始しようとしているからだ。
ここにきて、初めて、蘇我野神父はなにか、わずかな安心感を得ることができた。
が、すぐに首を横に振る。できた気がしているだけだ。多田井は約束を違わない男だ。できないならできないとあらかじめ言うだろう。つまりおそらく、二十五分後に得たい情報を教えてくれるに違いない。しかしまだ、事態はなにも解決していないではないか。
時間を無駄にはしていられない。この開いた時間にもできることはあるはずだ。蘇我野神父はバイクのエンジンに火を入れた。
(第3章へ続く)