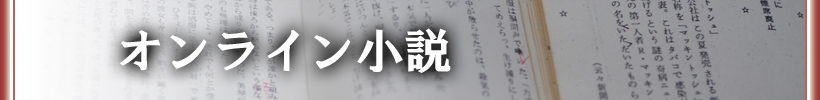オンライン小説
●第5章
聖堂の壁にかけられた掛け時計は、午後三時四十五分を回っている。葬儀ミサ開祭までもう十五分しかない。
告解室の信徒側の扉が、たまに、ガタ、ガタ、と動く。が。開く気配はない。
「ごめんなさいねぇ。小山内さん。なんか、ドアの調子がおかしくって」と、扉の外で妻木。「これだから古い教会はもう――」
「開けて、早く開けてください」中からは小山内潤子の声。「ロザリオはすでに終わりました。わたしは、みなさんに告白しなければいけないことがあるんです」
お聖堂に飛び込んできた蘇我野神父は、告解室の前に立って目を丸くした。なんと、外開け扉のノブに掃除のモップをつっかえ棒にして、折りたたみ椅子と組み合わせ、告解室のドアが外に開かないようにしてあったのだ。
犯人の妻木はちゃめっ気たっぷりに舌をぺろり。そして蘇我野神父を、司祭側の部屋へどうぞ、と手でうながした。
思わず、右の親指を立てて、グッジョブ、とニヤリと笑う蘇我野神父である。
司祭側の部屋に入ると、蘇我野神父は勢いよく、信徒側の部屋とつながる真ん中の格子をカラリと開けた。
「神父さま!」
「小山内さん。すべてわかりましたよ。旦那さまは自殺なんかしていません」
「えっ!?」
「これを見てください」
蘇我野神父は、格子越しに、あの、チワワの首輪を見せた。
「犬の首輪です。あのカートには、チワワが乗っていたんです」
「チワ、ワ?」
「旦那さまは、おばあさんを助けたあと、線路に引っかかっていたカートの中に入っていたチワワを救うために戻ったんです。おそらく、この首輪を外そうと必死だったのだろうと思います」
小山内潤子は、しばらく頭の中で、蘇我野神父が話した事実を反芻しているようだった。口を開き、閉じ、目を開け、まぶたを閉じる。息をつき、深呼吸をして、唇を噛む。
「ご主人が助けたおばあさんは、もうだいぶ認知症が進んでいらっしゃいましたが、最後にご主人が話した言葉は、よくお覚えでいらっしゃいました」
「主人は、主人は最後になんと?」
「――こんなところで、誰も死んではいけない、と」
長い嗚咽のあと、告解室の中に、沈黙が戻ってきた。長い沈黙だった。
「それで――、その犬は?」
「無事です」蘇我野神父は、ただ、事実だけを告げよう、と心に決めて、淡々と話し続けた。「ワンちゃんは、カートが電車にぶつかる直前に、旦那さまに首輪を外してもらって、外に逃げたようです。しばらくは野良生活を続けていたようですが、帰巣本能でしょうね。今しがた、本当についさっき、お宅に戻ったんです」
小山内潤子の返事は、しばらくなかった。
告解室の床に、沈黙が積まれていく。それは淀みでも、澱でもない。澄んだ、清廉な空気であった。
「たかが犬の命のために――。ねぇ、神父さま。たかが犬の命のために」蘇我野神父は、格子越しに、潤子が微笑んでいる様子を感じた。「主人はそれだけ、命というものを、大事にしていたんですねぇ……」
それで十分だった。
蘇我野神父は、生前、小山内秀樹が自分からご聖体を受け取ったときの、満面の笑顔を思い出していた。あれほど嬉しそうにキリストの体を受け取った信者が、自ら死を選ぶようなことはない、と感じた自分の直感、いや、神の啓示、聖霊の導きに感謝しつつ。
「神父さま、葬儀ミサについて、ひとつ、お願いがあります」潤子は静かに言った。「おそらく、主人もそれを望んでいると思いますから――」
* *
「ヨハネによる主イエスキリストの福音――」
「主に栄光」
会衆は、額、口、胸に小さく十字を切った。
「心を騒がせるな。神を信じなさい。そして、わたしをも信じなさい。わたしの父の家には住むところがたくさんある」
マイクを越しでも、蘇我野神父の声はよく通る。福音朗読は〝ヨハネによる福音書〟の十四章一節から。葬儀ミサでは定番の箇所だ。
「もしなければ、あなたがたのために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなたがたのために場所を用意したら、戻って来て、あなたがたをわたしのもとに迎える。こうして、わたしのいる所に、あなたがたもいることになる――」
神妙に起立して聴いている会衆の中にはベールをかぶった谷中と能勢の姿も見える。結局、いろいろな気持ちもあり、この葬儀ミサに出ることにしたらしい。
「はっきり言っておく。わたしを信じる者は、わたしが行う業を行い、また、もっと大きな業を行うようになる。わたしが父のもとへ行くからである――」
蘇我野神父は典礼書を掲げ、少しだけ時間を溜めたあと、言った。「キリストに賛美」
福音朗読は、会衆もまた、同じ台詞で締めくくる。「キリストに賛美」
「みなさま、お座りください」
そつなく福音朗読を済ませた蘇我野神父は、会衆を座らせてから、聖堂の後ろから多くのテレビカメラレンズが自分に向けられていることを意識することもなく、まずは、小山内家へのお悔やみを述べた。そして、今、話した〝ヨハネ福音書〟の箇所を少し解説し、一息を入れた。
「小山内秀樹さんの霊名は、みなさん、外の看板でもうご存じですね。そう。〝聖クリストフォロス〟。この〝聖クリストフォロス〟は不思議な聖人です。実を言うと、〝聖クリストフォロス〟は今、カトリックでは正式に聖人として登録されていません。えっ、と驚かれた方も多いのではないでしょうか。だってみなさん、旅行に出かける方に、旅の安全を祈って〝聖クリストフォロス〟のメダイを差しあげたり、新車に〝聖クリストフォロス〟の小さな御像をつけたりしますよね。でもふりかえってみてください? 典礼暦の中で、〝聖クリストフォロス〟の祝日というものを経験した方、いらっしゃいますか? いらっしゃらないでしょう」
いったん言葉を止め、会衆の様子を見る。みな、シンとして聞き入っている。マスコミの人々でさえも。
「でも、わたしは、こう思うのです。たとえバチカンが〝聖クリストフォロス〟を聖人としなくとも、われわれカトリックは日常生活の中で〝聖クリストフォロス〟を聖人だと思っている。それだけ、身近で、いつもともにいてくれる存在、それが〝聖クリストフォロス〟なのだ、と」
速くもなく、遅くもなく、蘇我野神父の声は、聖堂によく響く。みな、顔をうつむくこともなく、その言葉を聴いている。それは、最前列に座った小山内潤子と、その家族も同じであった。
「聖クリスフォロスは、もともとは別の名を持ったローマ人でした。彼はキリストに帰依し、流れの急な川を渡ろうとする人々を無償で助けるボランティアをしていました。そんなある日、小さな子どもが川を渡りたいというので、彼は快くそれを引き受け、子どもをおぶって川を渡り始めました。ところが、その子が途中から、どんどんと重くなっていくのです。その子はただ者ではないと察して男が名前を訊ねると、男の子は、自分がイエス・キリストであること、人々の罪を背負っているから重いのだと、彼に伝えたのでした」
誰しもが、この逸話から、小山内秀樹の最期を連想せずにはいられなかった。
「イエスを背負って川を渡り終えた彼に、イエスは〝キリストを背負った者〟という意味の〝クリストフォロス〟と名乗るよう伝え、また、持っていた杖を地面に突き刺すよう命じました。クリストフォロスがそうしてみると、杖はみるみるうちに巨大な木となり、この木を見た多くの者がキリスト教に改宗した、という――これが聖クリストフォロスの逸話です」
この霊名、〝聖クリストフォロス〟を小山内秀樹がつけていたこともまた、蘇我野神父が、彼が自殺ではないという確信を得たひとつの示唆だったのだ。
「帰天された小山内秀樹さんも、そんな聖クリストフォロスのようになりたい、人々をおぶって助けてあげたい、と、霊名にそれをつけたのではないでしょうか。ご病気でごミサにいらっしゃれない日が多かったと聞いています。それでも、ごミサにいらっしゃって、ご聖体を受け取るとき、それはそれは素敵な笑顔を浮かべていらっしゃったことを思い出します。小山内さんにとっては、キリストを背負うことがそれほど苦ではなかったのではないでしょうか。それはご自身の中に、すでにキリストがいらっしゃったからだと思うのです」
蘇我野神父はいったん言葉を切り、会衆と、マスコミを見渡した。みなの表情に、真剣に次の言葉を待つ瞳があった。
「――聖人は選ばれた人ではありません。それは、選択です。わたしたちはみなそれぞれ、神様から見ればひとりの【罪人/つみびと】でしかありません。しかし人生のことあるごとに、聖人であるか、罪人であるかを選択できる一瞬がある、と、わたしは思うのです。誰かが窮地に陥ったとき、スマホのカメラを向けるか、自分の荷物を捨てて助けに向かえるか、そのとき、その人が聖人か、罪人の選択をしたかがわかるのだと」蘇我野神父は顔を少し伏せ「小山内さんの選択は、ご家族のことを思うと胸が痛みます。しかし小山内さんは、そのとき、確かに〝聖・小山内秀樹〟としての選択をしたのです。なにが正しく、なにが間違っているのか、ただの人たるわれわれに答えがわかるわけもありません。それでもわたしは、その瞬間、神が、主が、小山内さんを突き動かしたのだと信じます」
そして、凜として、端正な顔を上げ「わたしは今日この日、この葬儀ミサの司式ができたことを、神様に感謝しています。小山内さんはまぎれもなく殉教しました。おそらく、今頃は、逆にキリストに背負われ、ペトロから天国の鍵を受け取っているに違いありません。小山内さんの魂のために、しばし、祈りましょう――」
お聖堂に沈黙が満ち、そして――まず、まばらにマスコミの人々から拍手が起きた。こういうとき、たとえ素晴らしい説教でも、拍手をするという習慣はカトリックにはない。しかし、それにつられて、信徒たちも拍手をしだし、やがて、聖堂が雷鳴のような拍手で満ちた。
それは、蘇我野神父の説教が優れていたからというからだけではないだろう。小山内秀樹の行為へ向けた、この世に残った罪人たちの、惜しみない讃辞として――。
小山内潤子は、うつむき、泣いていた。涙を拭うこともなく。
葬儀ミサは以後も滞りなく進み、派遣の祝福を迎えた。
「派遣の祝福を行う前に、閉祭の歌について、ひとつ、説明させてください。いつもの葬儀ミサならば、〝いつくしみ深き〟などを歌うところですが、今日は小山内さんの奥さまから、ご主人が好きだった曲で送ってほしいとお願いがありました。わたしは快く了解しました。ふだんは堅信や叙階式のときに歌われる曲ですが、小山内さんの生き様にふさわしいと思います。それでは、行きましょう。主の平和のうちに」
一同が答える。「神に感謝」
ミサ進行が言った。「閉祭の歌。典礼聖歌四百八番」
カメラを構えていたマスコミは、その曲に一同、度肝を抜かれたのだった。こんなに前向きな曲が、葬儀ミサで歌われるということに。
「行け、行け。地の果てまで。救いの訪れを告げるために。行け、行け。地の果てまで。救いの訪れを、告げるために――」
* *
「そうでしたか。それは良いごミサになりましたね」
パソコンのディスプレイ、スカイプ越しに映る蘇我野神父の神妙な顔に、スペインにいる片目のヨゼ神父は微笑んだ。
『あの説教で良かったのだろうかと、いつも葬儀ミサのときはいろいろと考えてしまいます。今回は特に』
取材していたマスコミの間から拍手が、そしてそれが波紋のように会衆に広がっていったことは、蘇我野神父にとっては想定外のことであったのだ。
もちろん、司祭の守秘義務として、告解室で小山内潤子が話したことや、それにまつわるドタバタを、ヨゼ神父には伝えていない。
「信仰は結果ではありません。プロセス――過程ですね」ヨゼ神父はうなずきかけた。「拍手が起こったのは、結果ではありません。プロセスです。あなた自身の、これからの司祭生活にとっても、ね」
『なんだか禅問答のようですね』
「おう、そう。ゼンモンドウ。日本人の蘇我野神父さまの方が得意でしょう?』
スカイプの向こうで、蘇我野神父は苦笑した。『残念ながら、わたしは僧侶でなく、カトリック教会の司祭になってしまいました』
「道はたくさんありますが、頂上はひとつですよ。これもゼンモンドウですか?」
『――それは、わかるような気がします』
スカイプを切ってから、そういえば――と、ヨゼ神父は少し記憶の糸をたぐった。日本から出国する直前に、誰にも内緒ということで、小山内秀樹に〝病者の塗油〟の秘蹟を授けたことがあったような気がする。ただ、心の病ではなかったような気がするが――。
しかしその記憶は、水に落とした涙のように、すぅっと消えていった。ベテランの司祭ほど、過去を忘れる術に長けるものだ。
それはもう、神様と、小山内秀樹だけの秘密になったのだ。
それでいいのだ。そう。なにもかも、主がうまくとりはからってくださったのだから。
( 了 )
※注:典礼聖歌四百八番「行け地のはてまで(作曲:高田三郎/作詞:典礼委員会)の歌詞はJASRAC無信託曲です)